noteから飛んでくれたあなたへ|物語の続きが始まります
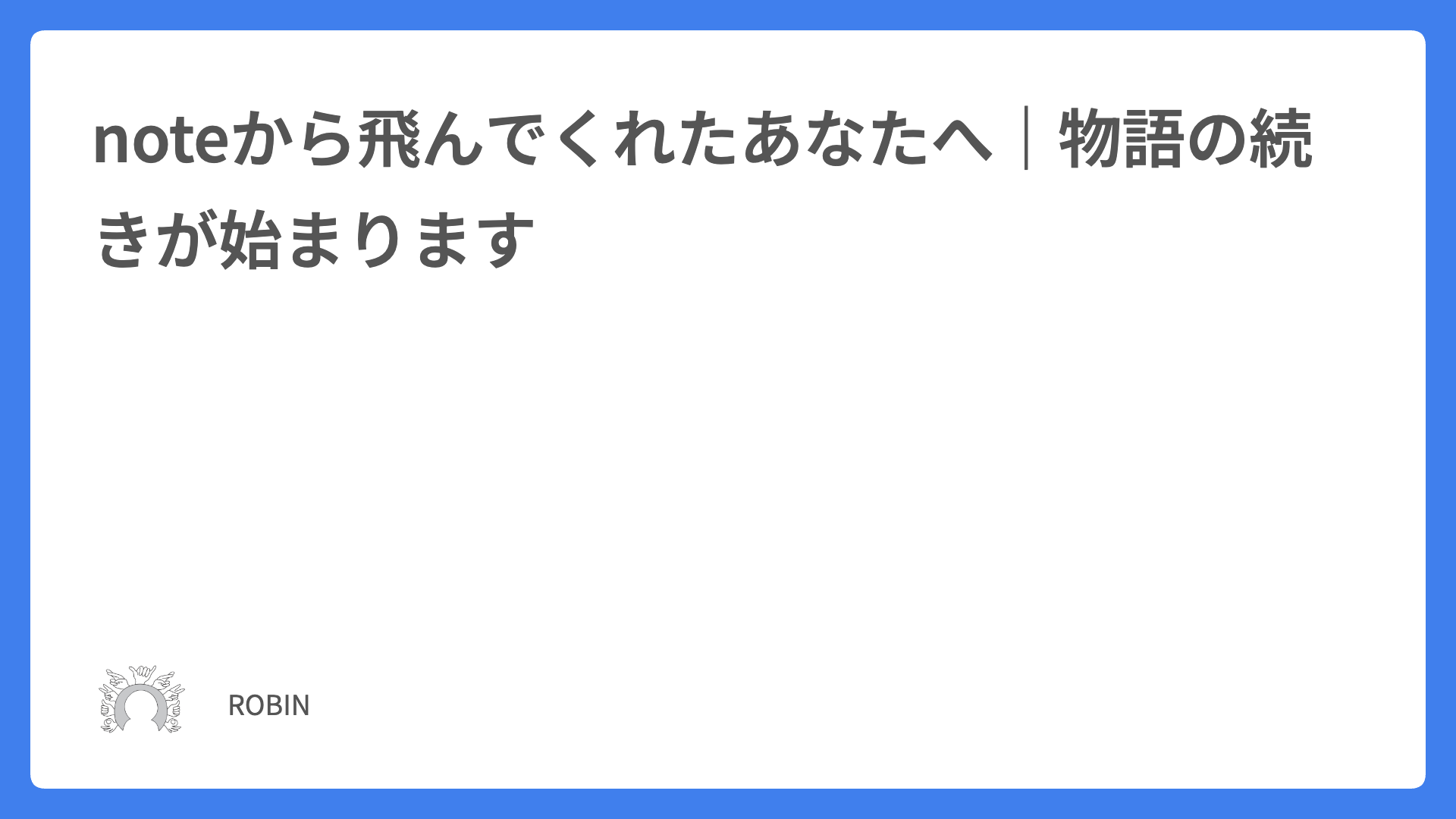
かつて一歩が踏み出せなかった僕へ。そしてあなたへ。|INFJという特性を通して、自分と誰かの再起動を願った物語
——noteで語ったあの物語の続き。
僕は、薬に手を伸ばしかけた。
「この苦しみから解放されるなら……」
そう思った夜。
全てを終わらせようと決めた。
そのとき——
一瞬の奇跡が起きた。
あなたにもきっと届く、その光の話を、
今ここから始めます。
さて、ここから更生施設に入った初日、
予想もしなかった事件が起こります。
あの出来事が、僕の人生の歯車を大きく
動かした瞬間でした。
ぜひ、続きをご覧ください。
更生施設の夜の試練
『ライオンの檻に入った夜』——孤独という試練と影との出会い
児童相談所の先生と担任と母親が帰ると、
空気が一変した。
それまで味わったことのない
強烈な不安感と
緊張感が、僕の全身を包み込んだ。
背中に冷たい汗がじわりとにじみ、
喉がカラカラに乾いたのを覚えている。
寮長先生が寮生たちの前で淡々と言った。
「今日から入ることになった足立だ。
みんな頼んだぞ。」
それだけだった。僕は耳を疑った。
寮長先生はそれ以上何も言わず、自分の住む
寮長室のドアを開け、さっさと中に
消えてしまったのだ。
心の中で叫んだ。
「おいおい、もっとあるでしょ!
紹介の仕方って…。
初めてなんだよ、こっちは。
もっと優しく、もっと丁寧に
取り持ってくれてもいいんじゃない?…」
でも、この場所は、僕が知っている
世界とは何もかもが違っていた。
寮生たちは鬼のような目つきで
僕を睨んでいた。
…いや、睨んでいるのではない、
完全に無視していたのだ。
無視される恐怖は、睨まれる以上に
冷たかった。
その場の正解が分からず、僕はただ
立ち尽くした。
時間だけが、無音の空間を裂くように
過ぎていった。
「自己紹介を待ってる?いや、でも…
誰に話せばいい?
どんな言葉が正解なんだ…?」
頭の中を焦りが渦巻き、
蛇に睨まれたカエル…いや、
蛇にすら気づかれていない
カエルみたいな気分だった。
無力感に潰されそうなまま、
1時間近くが過ぎた頃だった。
時計のカチ、カチ…という音が
やけに大きく響いていた。
「足立君、これ食べる?」
背の低い、僕より明らかに年下の
子がアメを差し出してくれた。
ただ、その子にも剃り込みが入っていた。
その小さな手と声に、
本当に救われた気がして、心がほどけた。
「ありがとう」
アメ玉を受け取ったときの温かさは、
今も忘れられない。
その子はすぐに続けた。
「イザワ君がこっち来いって。」
視線の先、寮の奥の暗がりに、
一人の男がいた。目がライオンの
ように鋭く、僕をじっと見据えていた。
「あの人、人間を食べたり…しないよね?」
そんな冗談を口にしたかったが、
喉は声を出す余裕もなかった。
アメをくれた少年は役目を果たすと、
スタスタと去っていった。
僕は勇気を振り絞り、その暗黒地帯の
檻の中へと足を進めた。
まるで武器も持たず、ライオンの檻に
入るような気分だった。
救いのアメが、逆に恐怖を2.5倍に
増幅させていた。
暗がりの中、イザワ君は無言で椅子を
指さした。
心臓の音が、自分にだけでなく周囲にも響
いてしまうのではと不安になるほど、
大きく、速く、鳴り響いていた。
「何をやってココに入って来た?」
その一言に、頭が真っ白になった。
登校拒否。格好悪い。
なめられるかもしれない…。
でも僕は決めた。ここで嘘をついても、
何も変わらない。
「登校拒否。」
「は???」
驚いたイザワ君は一瞬目を丸くし、
次に鋭く詰め寄った。
「ウソつけ。その顔はワルの顔だ。
何やった?薬か?売人か?傷害か?」
中学生とは思えないその言葉の数々。
僕は
「ここは別世界だ」
と心の奥で思った。
けれど、その口調、表情の奥に、
なぜか温かさを感じた。僕は直感した。
「この人となら仲良くなれる。」
初日、イザワ君が僕を受け入れて
くれたことで、寮全体の空気が変わった。
あの怖かった顔の寮生たちも、
よく見ればあどけなさが残る
少年たちだった。
窃盗、泥棒、薬物、傷害、恐喝…。
理由は様々だった。
でも、彼らの目の奥には、
人としての温もりが確かにあった。
僕はすぐにイザワ君にため口で
話すようになった。
彼は笑って許してくれた。
誰もそんなことをする寮生はいなかった。
それだけ、彼が一目置かれ、
恐れられる存在だったのだ。
そして、他の寮生たちも皆、
一見怖そうに見えて、本当に優しくて、
楽しい奴らだった。
「良かった、これで一つ不安が消えた。」
どんな世界も、頂点に立つ人と心が
通じれば、事はスムーズに運ぶものだ。
人は、偽りのない正直な心に引き寄せられる。
裏表のある人間は、その影がどこかで
露わになってしまうのだろう。
だが、その安心の影で、僕はまだ知らなかった。
心の奥に張り詰めた糸が、あんな形で切れて
しまう日が、すぐそこに迫っていたことを。
「2度泣いた1日、僕は“ここで生きる”と決めた」
覚悟を決めた瞬間に消えていった不安
保健室のやさしさ
更生施設に入って10日ほど経った頃。
地元での怠惰な生活で
すっかり鈍り切っていた僕の体は、
急激な変化にまるでついていけなかった。
野球部の練習中、何度もダッシュと
守備練を繰り返すうちに、
目の前がグラグラしてきた。
気分が悪くなって、
そのまま保健室へと運ばれた。
ベッドに横になっていると、
30歳くらいの髪の長い保健室の
先生がそっと声をかけてくれた。
「足立くん、どう?
ここの生活には、もう慣れた?」
その一言に、胸がジンと熱くなった。
優しさに触れたのは、
いつぶりだっただろうか。
ただの気遣いの言葉なのに、
それがまるで救いのように思えて、
目頭が一気に熱くなった。
「う、うーん…」
言葉にならず、声がかすれた。
先生は察したように、
「先生、職員室に行ってくるから、
ゆっくり休んでていいよ」
とだけ言い残して、部屋を出ていった。
その背中を見送った瞬間、
なぜか涙が止まらなくなった。
声を殺して、布団の中で
子どものように泣いた。
ここに来てからずっと
押し殺していた感情。
恐怖、不安、孤独
——それらが一気に
あふれ出した瞬間だった。
面会拒否
その夜、僕は寮長先生に頭を下げて
「話があります」と申し出た。
思い詰めた末の問いだった。
「僕は、いつここから出られますか?」
寮長先生は
苦笑いを浮かべながら答えた。
「まだまだ先だ。お前、
入ったばっかりだろ。
そんなこと考えるな。」
その言葉に、心がズシンと沈んだ。
絶望という言葉では足りない、
真っ暗な穴に
落ちたような感覚だった。
「じゃあ、児童相談所の先生に
会わせてください。親でもいいです!」
僕は必死だった。
「ダメだ。
最低2ヶ月は面会は無理だ。」
「……2ヶ月……?」
目の前が真っ白になった。
頭では理解していても、
心がついていかない。
崩れそうな声で「2ヶ月…」と
つぶやいた直後、涙が溢れた。
大声を上げて泣いてしまった。
噂と恐怖
泣きながら、
ふと頭をよぎったのは、
数日前にニシムラ君が言っていた
言葉だった。
「剪定係は長くいる奴が選ばれるんだ。
お前、もうここから出れないぞ。」
あの言葉が現実になるんじゃないか。
もう一生、ここから出られないん
じゃないか。
焦りと恐怖が一気に押し寄せた。
僕は、必死に尋ねた。
「剪定係は出られないって本当ですか?」
ニシムラ事件
寮長先生は一瞬
きょとんとした顔をしたあと、フッと笑い、
扉を勢いよく開けた。
「おい!ニシムラ!こっち来い!」
寮中に響き渡る怒声。
そして僕の目の前で、
ニシムラ君は殴られた。胸が痛んだ。
僕は、ただ真実を
知りたかっただけだった。
こんなつもりじゃなかったのに…。
その場にいたイザワ君が言った。
「ニシムラ君は、足立君のことが
気に入らなかったんだ。
いつもいじめてただろ。」
僕は悟った。
この世界にも、理不尽な上下関係や、
感情のぶつかり合いがあることを。
そして、その中で、誰かが自分を
守ってくれることもあるということを。
覚悟と切り替え
「……もう、ここで
生きていくしかないんだ」
その夜、僕はそう覚悟した。
覚悟を決めた瞬間、不安は
驚くほどすっと消えていった。
心の霧が晴れたように、
胸の奥が軽くなった。
この施設の中で、誰よりも
早く起きて、誰よりも真面目に
生活してやる。
逃げ出すことではなく、
ここでやり抜くことにこそ意味がある。
そのとき、僕は気づいた。
ネガティブな感情は、
「今やるべきこと」
に意識を向けた瞬間に、
力を失うということに。
この体験は、のちに僕の人生に
おける行動原則となっていく。
けれども、覚悟を決めたその先で、
僕を待ち受けていたのは、
想像を超える
「塀の中の現実」だった――。
更生施設
施設生活の“異空間”感と、柵が締めつける日常
朝の寮での雑務を終えた僕たちは、
給食当番が用意してくれた
温かな朝ご飯を静かに食べ終えると、
無言のまま学生服に袖を通し、
施設の敷地内にある
学校へと歩き出す。
5寮から学校までは、ほんの徒歩2分。
その短い距離すらも、異空間に
繋がる儀式のように感じられた。
小道の先に現れる校舎は、
どこか色を失っていて、その寂しげな
佇まいが、まるで
「お前たちはここで何を
学ぶべきか分かっているのか」
と問いかけてくるようだった。
毎朝、8つの寮から生徒たちが
一斉にぞろぞろと集まってくる光景は、
異様な迫力があった。
皆、同じような髪型、
同じような目つき、同じような
強がりの仮面を被っていた。
剃り込みの入った髪、
鋭く整えられた眉、表情の奥に
見える不安と怒り。
その仮面の下に隠された本音は、
誰も語ろうとはしなかった。
校舎の構造自体は、普通の中学校と
変わらない。
けれど、その外周にそびえ立つ
5メートルの高いフェンスが、ここが
「塀の中」
であることを日々僕たちに思い知らせた。
その鉄柵はどこにいても視界に入り、
僕の胸にじわじわと圧迫感を与えた。
体育の時間、その圧迫は特に強くなり、
まるで呼吸すら制限されるような
苦しさが込み上げてきたのを、
今でも鮮明に思い出せる。
朝礼になると、施設長
――つまり校長にあたる人物が、
淡々と新しく入所した“生徒”を紹介する。
けれど、僕たちにとってそれは
“新入り受刑者”
の紹介にほかならなかった。
生徒という言葉が、この場では
妙に空虚に響いていた。
新入りがいない日は、普通の学校と
同じように行事や諸連絡が
読み上げられるが、どこか張り詰めた
空気が支配していた。
教室の隅々まで、見えない緊張が
流れていた。
この更生施設内の学校には、
約80人の寮生が4つのクラスに
分かれていた。
中学1・2年の合同クラスが2つ、
3年男子のクラス、
そして女子のクラス。
どのクラスも、それぞれに独特の
空気が漂っていた。
授業は驚きの連続だった。
小学1年生の教科書から始まる
国語の授業に、最初は冗談だと思った。
けれど、それはこの場所の
“当たり前”だった。
1日で小学3年生の教科書まで
進んだとき、別の寮の子が僕に
「足立君、頭良いな、天才だな」
と真顔で言ってきた。
その言葉に、僕は衝撃を受けた。
けれどすぐに分かった。
彼は本気でそう思っていたのだ。
この施設では、九九を
覚えられないまま来た子たちが、
決して少なくなかった。
僕は小学5年の教科書あたりで
進みが止まったが、それでも
「優等生」
と呼ばれるようになっていた。
その頃、僕が頼りにしていたのが
ナカタ君だった。
彼は暴力団組長の息子で、落ち着いた
芯のある真っ直ぐな目をしていた。
彼だけが、中学2年の教科書を
自力で解いていた。
僕は彼に憧れ、そばにいたくて、
学ぶことを通して距離を縮めようとした。
彼との会話は、僕の中にある“普通”の
感覚を少しずつ取り戻してくれる気がした。
教師たちもまた、この施設の
空気を象徴していた。
国語の先生は早口で
何を言っているのか分からず、
からかわれるたびに本気で怒り、
寮生たちの格好の笑いの種となった。
担任のムトウ先生は、いつも
竹刀を持ち歩いていた。
竹刀が机を叩く音は鋭く、
教室全体がその一振りで
一気に凍りついた。
怒声とともに響くその音は、
今でも耳に残っている。
女子という存在は、目の前にいて、
けれど決して届かない存在だった。
校舎は階で分けられ、男女の
接触は厳しく制限されていた。
言葉を交わすことすら禁止だった。
その理由は、過去の“事件”だった。
施設内で起きた妊娠騒動。
それ以降、男女の接触は
厳罰対象となった。
けれど、だからこそ、
男子たちは短い昼休みや
登下校の時間に、密かに
見張りを立てながら、女子と
言葉を交わす機会を狙った。
見つかれば、即座に体罰と
2週間の特別作業。
そんなリスクを背負ってまで、
たった一言を交わすことに、
僕らは全てを賭けていたのだ。
女子たちもまた、皆が過去に
不良の名を馳せていた。
月に一度の床屋の日。
男子は皆、丸坊主。
女子は皆、決まりきった
オカッパ頭。
その中でも髪の色の違いは、
入寮時期を示す目印となっていた。
金髪の根元が黒くなっている
女子は古株。
全体が黒髪の子は、既に
“更生”した者として扱われていた。
そんな中に、一際目を引く女子がいた。
美しかった。
けれどその理由を知れば知るほど、
彼女は僕にとって遠い存在になった。
暴走行為、薬物。
彼女がここにいる理由は、
僕には理解しきれなかった。
けれど話したかった。
たった一言でもいい。
ある日、給食当番中に目が合い、
彼女がほんの少し
微笑んでくれた瞬間があった。
声をかけるチャンスだった。
けれど、声が出なかった。
勇気が出なかった。
その悔しさは、今でも胸の奥に残っている。
40年経った今でも、あの瞬間に
戻ってやり直したいと思う。
たった一言が言えていれば——。
僕はそこで学んだのだ。
チャンスは、勇気がなければ掴めない。
一生後悔することになるのだと。
この場所で、僕にとっての
支えだったのは、イザワ君の存在だった。
同じ寮で日々を共にし、彼が
そばにいてくれたことで、
僕はこの環境に順応するための
覚悟を固めることができた。
そして僕は、心の中で一つの決意をした。
ここで「一生を生き抜く」と。
それは、かつての僕からは
想像もできなかったほどの、
強い覚悟だった。
だが、その決意は、やがて訪れる
“絶対命令”によって、真に
試されることになる。
この施設での日々は、
まだ序章に過ぎなかった。
「限界を超えて出会った、僕たちの本当の力」
終わらないマラソン —— 無言の恐怖と一体感の芽生え
更生施設の絶対命令更生施設での
思い出深い出来事は
数えきれないほどあるが、その中でも
僕の心に強烈に刻まれているのが、
あの日の出来事だ。
朝の全校集会で、僕たちはいつものように
ラジオ体操をしていた。
空気はまだ冷たく、湿った土の匂いが
運動場の端から立ち上っていた。
そんな中、僕たちのクラスだけが、
校長先生から注意を受けた。
それが、全ての始まりだった。
僕たちの担任は、
泣く子も黙るムトウ先生。
手にはいつも竹刀を持ち、
背筋は一分の隙もなく伸びている。
無言で睨みつけられるだけで、
教室の空気が凍りつくような存在だった。
暴力団関係者の親を持つ、
筋金入りの不良の子供たちでさえ、
ムトウ先生の前では息をひそめていた。
竹刀が空を切る音は、いつも僕たちの
心臓を一瞬で締めつける。
集会が終わり、ざわつく心のまま
教室へ戻ろうとしたその瞬間、
ムトウ先生の鋭い声が
運動場に突き刺さった。
「おい、お前ら!運動場を走れ!」
僕たちは一瞬何が起きたのか分からず、
顔を見合わせ、戸惑いながら
バラバラに走り出した。
「馬鹿野郎!整列して走れ!」
怒号が飛び、でもまだ半分は
まとまりなく、ダラダラと足を
引きずるように走り続けていた。
一周、二周、三周……。
グラウンドの土は乾いていて、
足が擦れるたびに白い粉塵が靴の
周囲に舞い上がった。
次第に太陽が高くなり、照りつける
光に汗がにじみ始めた。
気づけば五周、十周……。
それでも、ムトウ先生は一言も
止めろと言わなかった。
むしろその無言の圧力が、
僕たちの背中を無理やり押しつけてきた。
最初はふざけていた悪ガキたちの顔が、
じわじわと真剣に変わって
いくのがわかった。
「これ、マジでヤバい……
ムトウ先生は本気だ」
——そんな空気が広がり始め、
やがて列は自然と揃い、
足並みも一致してきた。
だが一人、中学2年の
番長ウチムラ君だけは違った。
眉間に深いシワを刻み、
どこかにプライドと反発を漂わせながら、
ふて腐れた表情で走り続けていた。
彼に逆らえるのは、上級生の
イザワ君たちだけだ。
ムトウ先生は、そんなウチムラ君を
じっと見つめ、竹刀を持ったまま
グラウンドの一点を指しながら、一喝した。
「ウチムラ!お前、しっかり走れ!」
それでも、彼の足取りは変わらなかった。
そのうち、僕たちはグラウンドを
30周、40周、50周……と走っていた。
足音が泥に混じり、誰もが息を切らし、
苦しさで顔をゆがめていた。
それでも、誰も口を開けなかった。
声を出せば、
もっと走らされるような気がした。
僕は心の中で何度も叫んでいた。
「先生、今ので50周です!頼む、
終わりにしてくれ……!」
でも終わらなかった。
60周、70周、80周……90周。
空気は熱を帯び、泥の匂いと汗の
蒸気が混ざり合う。
地面を蹴るたびに、靴が滑り、
砂埃が舞った。
100周か…。
誰もが、ついに“100”を超えるのかと、
震えるような予感を抱きながら走っていた。
だが、ムトウ先生は何も言わない。
表情も変えず、ただ僕たちの
動きを黙って見ていた。
クラス全体の顔は汗と泥にまみれ、
息は荒く、顔も見えないほどだった。
だが、不思議なことに、誰一人として
遅れを取ることも、離脱することもなかった。
誰かの靴が擦れる音、隣の息づかい、
それらがリズムになり、気づけば
僕たちは一体となっていた。
——あの瞬間、僕たちは確かに
「ひとつ」だった。
そして、ついに200周目を迎えた。
夕陽がグラウンドの隅に差し込み、
長く伸びた影が僕たちの足元に重なった。
薄暗くなりかけた空の下で、
ムトウ先生の声が響いた。
「よし!暗くなったから止めだ!止まれ!」
その瞬間、全身の筋肉が崩れ
落ちそうになった。
膝が震え、胸の奥で、こらえていた
何かが一気に爆発しそうだった。
隣にいた仲間も、歯を食いしばりながら、
顔をゆがめていた。
でもその瞳には、どこか達成感と
誇りが浮かんでいた。
——やりきった。
俺たちはやりきったんだ。
だが、最も驚くべきは、なんと、
ムトウ先生もまた、
僕たちの最初の一周目から、
最後の200周目まで、
ずっと一緒に走っていた事だった。
汗ひとつ見せず、息を乱すこともなく、
僕たちの列の中で、あの重たい
空気を背負いながら走っていたのだ。
その背中は、鬼のようで、
同時に、誰よりも強い信頼を
抱かせる存在だった。
ムトウ先生の厳しさは、嫌われ役を
引き受けたうえで、本気の愛を
注いでくれていた証だった。
僕たちが将来、困難にぶち当たった時、
「あの日を乗り越えた自分なら大丈夫だ」
と心から思えるように
——あの200周は、罰ではなかった。
それは、
未来を生き抜くためのギフトだった。
自分の殻を破り、
限界を超えた自分に出会えた、
人生最大の贈り物。
その日を境に、ウチムラ君は
ムトウ先生とよく話すようになった。
あれだけ反発していた彼が、
先生に心を開き始めたこと。
それもまた、
あの日が残したひとつの奇跡だった。
人は、楽な方へと流れる。
でも、枠を超えていくためには、
時に鬼のような存在が必要なのだ。
僕たちの流した汗と涙が、
それを教えてくれた。
だが——その数週間後。
僕のその後の人生すら大きく変える、
忘れ得ぬ出来事が、真冬の闇の中で
静かに待っていたのだった。
◆ 静かな宿題
「あなたが心のどこかで“あの人の厳しさは愛だったのかもしれない”と気づきながらも、まだ認めきれていない誰かは、いますか?」
もしも、誰にも言えなかったその名前が浮かんだのなら、
その心の重みごと、そっと預けてみたくなる場所でありたい──
僕は、そんなふうに思っています。
「誇りは、汚水の中から現れた」
「俺、入ります!」と名乗り出たその理由
更生施設に入って、ちょうど
1ヶ月が過ぎた頃だった。
その夜は、骨の芯まで
凍えるような真冬の闇に包まれていた。
風はなく、空気は張り詰めていて、
吐く息は白く、皮膚に触れる空気が
まるで刃物のように感じた。
「トイレが、流れない」
そんな声が寮内を走ったのは、
夜点呼が終わった直後だった。
僕が暮らす5寮のトイレから、
突然水が引かなくなったのだ。
全寮生10人が、厚手の上着を
羽織りながら裏手へと向かった。
寮の裏は、普段は誰も寄りつかない場所。
霜が降りた地面が
「ザク、ザク…」と不気味な音を
立てるたびに、背筋が寒くなった。
寮長先生が、金属製の大きな蓋をギィィ…と
ゆっくり開けた。
その音が、耳に残るほど重く、鈍かった。
「おい、この中のどっかが詰まってるな…」
懐中電灯の頼りない光が、
浄化槽の底に沈む汚水の水面を
ぼんやり照らす。
光が揺れるたびに、濁った水がかすかに
波打ち、暗がりの中に異様な臭気が広がった。
その瞬間、誰もが無意識に
一歩後ずさった。
「誰か、この中に入って詰まりを取ってこい」
寮長先生は、まるで
冗談でも言うように笑った。
だが、誰も笑わなかった。
一瞬にして静寂が広がった。
空気が凍りついたようだった。
皆が互いの顔をちらちらと伺い合う。
「…じゃあ、ジャンケンで決めるか!」
その提案に、あちこちから叫びが漏れた。
「えぇ〜〜〜〜っ!?」
心の底から逃げ出したい、
という思いが顔中に浮かんでいた。
そのときだった。
「俺、入ります!」
夜空にその声が、
まるで鐘の音のように響き渡った。
声の主は…
一一僕だった。
時間が止まったように感じた。
周囲の視線が一斉に僕に集まる。
驚き、戸惑い、そしてどこかに
感嘆の色が混じった眼差しが、僕を包んだ。
「おぉ!すごいなお前!みんな見たか!?
これが潔さってもんだ!
よし、みんなで足立を支えてやれ!」
寮長先生の声に、
仲間たちがざわめいた。
僕は、ジャンケンで負けた誰かが、
引きずられるように
あの汚水の中に入るのを見たくなかった。
それ以上に、この施設でいちばん
新人の自分が、いちばん嫌な役目を
引き受けるべきだと思った。
5寮の仲間たちは、僕を温かく受け入れてくれた。
その恩を、どうしても返したかった。
そして何より、
自分自身に誇れる自分でいたかった。
あの日、「ここで一生を生きる覚悟」を
したあの夜の気持ちが、背中を押していた。
「やらされる」のではなく、
「自分で選ぶ」。
その一点だけが、僕の誇りだった。
僕はロープを身体に巻きつけ、
命綱を仲間たちに託した。
タラップを握る手に力を込め、僕は静かに、
そしてゆっくりと、
浄化槽の闇の中へと降りていった。
下半身から胸、そして肩まで、冷たい汚水が
ジワリジワリと這い上がってくる。
ジャージの上からでも冷気が突き刺さり、
皮膚が痺れていくのがわかった。
喉の奥を突くような異臭が肺に染み込み、
思わずえずきそうになった。
「口は絶対、つけるな…」必死で顎を引き、
水面と距離を保った。
手探りで、詰まりの原因を探し続けた。
時間の感覚が消えた。
何度も指先が空を掴み、泥を掴み、また外れた。
そして——ヌルッ、と
指に何かが吸い付く感触があった。
軍手を脱ぎ捨て、凍えた素手でその異物を掴む。
何度も引っ張ったが、水圧に阻まれて動かない。
右手の感覚が失われていく中、
僕は渾身の力を込めた。
「うおぉぉぉぉ…!」
そしてその瞬間——
『ギュルギュルギュル〜〜〜!!!』
轟音と共に、溜まりきった汚水が
渦を巻いて引き始めた。
「うおおお〜〜!!!」
寮生たちの歓声が、夜空を震わせた。
ロープを強く引き上げる手に力が入り、
寮長先生が叫んだ。
「見たかこれが勇気だ!
足立をすぐ風呂に連れてけ!」
「すごいよ、足立くん!」
「ありがとう!」
皆の顔が、確かに輝いていた。
みんなの素顔が見れた。
浄化槽から引き上げられたとき、
全身が冷え切っていたのに、
不思議と心だけが熱く、真っ赤に燃えていた。
「俺は今、生きてる…!」
寒空の下、震える身体の奥で、
胸の奥だけが熱く震えていた。
誰かに命じられてやったわけじゃない。
誰かのせいにして逃げたわけでもない。
自分で決め、自分で動いた。
たったそれだけのことで、
自分を少し好きになれた。
あの夜、僕はひとつ、
小さな誇りを手に入れたのだ。
だが——その小さな誇りが、本当に
揺るがぬものかどうか。
それを試すような“面会の日”が、
静かに、近づいていた——。
はじめての面会──母を恨んだ僕が、母を想った日
あの日の僕にはわからなかった“親の心”
寮長先生が言っていた通り、
僕が施設に入って2ヶ月ほど経った頃、
ついに両親がそろって
初めての面会にやって来た。
その姿を遠くに見つけた瞬間、
僕の中で何かがざわついた。
記憶が、一気に初日へと巻き戻った。
――更生施設に入所したその日。
母は、自分の息子が本物の不良たちに
囲まれ、たったひとり放り込まれるという、
あまりに残酷な
光景を目の当たりにしていた。
あのときの母の表情――強張り、潤んだ目。
声を出そうとしても出せず、
ただ震えるように立ち尽くしていた。
母の想像とは、
まったく異なる光景がそこにあったのだろう。
その姿を、僕は忘れたことがなかった。
いや、あの日からずっと、
心のどこかで引きずり続けていたのかもしれない。
きっと、あの夜から
母は眠れなかったのだと思う。
息子がどんな場所で、どんな顔を
して暮らしているのか
──想像するたびに、胸を潰されるような
思いに襲われていたに違いない。
あれほど母を恨んでいた僕が、
なぜかそんな母のことを案じている。
そのことに、正直、自分でも戸惑っていた。
けれど今ならわかる。
僕も、ひとりの親になってみて初めて、
その気持ちが痛いほど理解できる。
……けれど、その面会の日。
広い庭で、僕が仲間たちと笑顔ではしゃぎ、
木登りまでしている姿を目にした母は、
一瞬、ぽかんとしたように立ち止まり、
そして――表情をゆるめた。
安堵と驚きが混ざったような、
力の抜けた表情。
そのとき、なぜか胸が詰まりそうになった。
笑っている僕を見て、
母が救われたような顔をした。
それを見て、僕のなかの何かが静かに揺れた。
日曜日は、寮生たちにとって特別な
日だった。
少しだけ自由な空気が流れ、心の鎧が
ふっと緩む日。
仲間たちは、
面会に来た僕の両親に向かって、
元気に挨拶をしてくれた。
その光景が、僕と母が初めてこの5寮に
足を踏み入れたあの日のことを、
強烈に際立たせた。
あのときの緊張、重たい空気、不安で
足がすくむような感覚
――そのすべてが、今日のこの温度に
溶かされていくようだった。
気づけば、5寮には仲間意識が
芽生え、僕たちは
「ただの問題児の集まり」ではなくなっていた。
面会の席で、寮長先生の指示で
取り出されたのは、僕が以前、
両親に宛てて書いた手紙だった。
それは、ここに来て間もない頃、僕がまだ
絶望の中で泣きながら書いた手紙――
「一刻も早く、ここから出してほしい」
と訴える、あの頃の僕が刻まれた叫びだった。
母はその手紙を見て、そっと目を伏せ、
そして寮長先生に向かって声を震わせた。
「……寮長先生、こんな手紙を
息子が書けるようになるなんて……
ありがとうございます」
その目は、涙で滲んでいた。
……だけど、僕は、母を見ないようにした。
無視したのではない。見たくなかったのだ。
なぜなら、あの手紙を書いた頃の僕は、
もうここにはいなかったからだ。
あの頃の弱々しい自分は、
すでに置き去りにしていた。
ホームシックも過ぎ去り、施設の生活に慣れ、
仲間と笑い、日々が心から楽しかった。
だからこそ、母が見せた涙が、
どこか他人の涙のように思えた。
それが、逆に胸をえぐった。
面会の空気は、静かに、
しかし確実に凍りついた。
それでも僕は――心の底で、ほんのわずかに、
はじめて「親のありがたみ」というものを
感じていたのは確かだった。
世界で一番憎み、
顔も見たくなかった母に対して。
ほんの少しだけ……
「ありがとう」という気持ちに近い何かが、
芽生えていた。
だがその小さな感謝よりも、
遥かに濃く、
遥かに激しく渦巻いていたものがあった。
それが、抑えきれない反発心だった。
僕は、結局その面会で母と
一言も言葉を交わさなかった。
理由もわからないまま、身体の内側に
硬い棘のようなものを抱えたまま、
口を開けなかった。
「なんだろう、この異常なまでの
反発心は……この気持ちは一体どこから
来るのだろう?」
ずっと、ただの反抗期だと
片付けていた。
だが、それは違った。
その感情の正体に気づくのは、
もう少し大人になってからだった。
――それは、幼い頃からずっと
僕の心を蝕んでいたもの。
――母から受けた、あの暴力と、
言葉と、沈黙の中にあった
「虐待の記憶」だった。
ようやく、その存在に名を
つけることができたとき。
僕は少しだけ、
自分を許せたような気がした。
……けれど、理由が分かったから
といって、
現実の苦しみが軽くなる
わけではなかった。
僕はただ、ここで生きていく覚悟を、
またひとつ、静かに固めた。
「一生ここで生きていく」と決めた僕が、最短で自由を手にした理由
6ヶ月で出所――誰よりも早く、でも一番喜んでいなかったのは僕だった
6ヶ月。
それは、この更生施設の歴史の中で
最短の記録だった。
僕は、施設史上最も早く
出所することになった
――にもかかわらず、
その知らせを受けたとき、
喜びよりも先に胸を締めつけたのは、
「出たくない」という、
思いがけない本心だった。
なぜ僕が、そこまで変われたのか?
それは、ある“決断”の瞬間に
さかのぼる必要がある。
「ここから今すぐ出たい!」
そう思っていたあの頃の僕は、
毎日が息苦しく、
常に不安感に支配されていた。
「俺は、いつになったら
ここから出られるんだろう?」
その答えのない問いが、
じわじわと心を蝕んでいく感覚。
ただ待つだけの毎日は、
想像以上に辛く、気力も体力も、
音を立てずにすり減っていった。
あの日、僕は堪えきれず、
寮長先生に泣きついた。
「ここから出してください!」
でも、その願いは受け入れられなかった。
絶望の底に沈むその瞬間、
僕の中で、何かが静かに変わった。
「郷に入れば郷に従う」そう心に誓った。
そして、自分にこう言い聞かせた。
「新入りなんだから、
何でも1番最初にやるのが当たり前だ」
そうして、ついには
こう覚悟するまでになった。
「もうここから出られなくてもいい。
俺は一生ここで生きていく!」
極端すぎると思うかもしれない。
でも、あの時の僕にとっては、
それしかなかった。
そう意識を切り替えなければ、
この厳しい生活にはもう耐えられなかった。
擦り切れかけていた心の糸が、
あの覚悟によってギリギリのところで
持ちこたえたのだ。
本能的に気づいたんだ。
「その日を待たない生き方」
――出る日がわからず苦しむくらいなら、
「出ない」と決めてしまえば、
何も待たずに済む。
その瞬間、心の底から叫んだ。
「俺は、一生ここで生きていく!」
不思議なことに、
気持ちは驚くほど軽くなった。
それまで号泣するほど辛かったのに、
なぜか――楽しかった。
あの時、僕は初めて「今」に意識を
向けていたのだ。
僕はそれまで、
「どうにもならないこと」
にばかり意識を向けて、勝手に疲弊していた。
でも、本当に必要だったのは
「どうにかなること」に集中することだった。
日々のやるべきことに、丁寧に、淡々と取り組む。
それだけで、こんなにも気持ちが
変わるとは思わなかった。
親元を離れ、不安と緊張で
押し潰されそうだった僕の中に、
こんな強さがあったとは、
自分でも驚きだった。
覚悟を決めてからの僕は、誰よりも
ルールを守り、率先して何事にも
全力で取り組んだ。
朝6時の起床と同時に誰よりも早く目覚め、
布団を畳み、顔を洗い、
元気よく寮長先生に報告に行った。
今思い出しても、あの頃の自分は
本当に生き生きとしていた。
その姿勢が評価されたのかもしれない。
僕は、施設史上最短の6ヶ月で、
出所が決まった。
けれど――
周囲の誰よりも、その知らせを
喜んでいなかったのは…
僕自身だった。
「出たくない」
心の底から、そう思っていた。
ここでの生活が、
本当に楽しかったからだ。
でも、周囲の寮生たちは違った。
彼らは皆、「早く出たい」
という焦りと渇望に、心を飲み込まれていた。
誰かが出所を決めるたび、
5寮には重苦しい空気が立ち込めた。
ある日、イザワ君の出所が決まった。
僕は彼の笑顔を見て、心の底から
一緒に喜んだ。
すると、初日にアメ玉をくれた
ミヤタ君が、そっと耳元で言った。
「足立君、他のみんなの前で喜んだらダメだよ」
「なんで?」
と聞くと、彼は言った。
「みんな、嫉妬してるんだよ。
誰かが出て行くのを喜んだり話題にすると、
怒る子だっているんだよ」
信じがたかった。
でも、イザワ君が去ったその朝、
寮には沈黙が降りた。
優しかったニイミ君でさえ、
苛立ちを隠せずに言った。
「なんであいつが今出られるんだ?
次は俺かノグチ君のはずだろ」
僕はその時、改めて知った。
ここは塀の中。
皆が心の奥で、必死に出口を探し、
もがいている場所だった。
だから僕は決めた。
5寮の3年生たちが無事に出ていくまでは、
自分の出所は誰にも言わない。
それでもなお、僕は
「残りたい」と本気で思っていた。
かつて「今すぐ出たい」と叫んでいた
自分がいたのに、今はその真逆だった。
「一生ここで生きていく!」
その覚悟が、僕の心を強くし、目の前の毎日を
“生きる”ことに夢中にさせてくれた。
その結果、皮肉なことに
――僕は、
最短記録でこの場所を卒業することになった。
だが。
僕を待っていた地元での再会は、
決して温かいものではなかった。
校長先生のまさかの言葉。
そして、信じていた友人からの裏切り。
自由になれたはずの心は、
再び見えない鎖につながれていったのだった。
地元中学への復帰。戻りたかったのは自由じゃなかった
弱さを隠す仮面の下にいた、誰よりも臆病な自分
中学3年になるタイミングで、
僕は地元の中学に戻ることになった。
更生施設での最後の日。
校長室に通され、静まり返った
空気の中で誓約書を読み上げさせられた。
「中学校を無断で休んだり、
警察に補導されたら、再び更生施設に
戻らなければならない」
そんな項目が10ほど並んでいた。
僕の声だけが冷えた校長室に響く。
読み終える頃には、手がわずかに震えていた。
破ればまた“あの塀の中”に逆戻り
――その現実を、突きつけられた。
でも、そんな誓約をしたにもかかわらず、
僕は真面目に学校に通うことはなかった。
いや、通おうとしなかった、
と言った方が正しい。
僕の中には、どうしようもなく強い
二つの想いがあった。
ひとつは、“あの頃”の自分を、
誰にも知られたくなかったということ。
中学2年の途中で
学校に行けなくなった本当の理由――
それは、サトシ先輩たちに脅され、
探されるのを恐れていたからだった。
でも、そんな理由、
誰にも知られたくなかった。
あの逃げ出した自分、恐怖から隠れた自分の
“弱さ”を、何よりも僕自身が許せなかった。
だから、彼らが卒業して
いなくなった今でさえ、あえて学校に行かない姿を
演じていた。
まるで、「俺は怖くて来なかったわけじゃない」
そう周囲に見せつけるかのように。
本当は怯えていた。
だけど、それを隠すために、登校しないという
“仮面”を被った。
もうひとつの理由は、もっと切実だった。
誓約書を破れば、また更生施設に戻れる――
僕は、心からそれを望んでいた。
あの場所は、どこよりも
“本当の自分”でいられた場所だったからだ。
ごまかさず、演じず、弱さを
抱えたままでも受け入れられていた。
寮の仲間たちとの日々、
ルールの中で必死に生きた時間、
あの誓った朝6時の起床と寮長への報告――
僕の中では、あそこが唯一
“自分として生きられた場所”だった。
だから、昼の給食の時間に私服のまま
タクシーで学校に乗りつけたり、
禁止されていた自転車で堂々と通学したり――
わざと目立ち、ルールを破る
行動を繰り返した。
心の中で期待していた。
「また、あの場所に戻れるかもしれない」
と。でも、僕の計画は簡単には
思い通りにならなかった。
校内に足を踏み入れても、自分の教室には
向かわず、悪友たちの教室へ直行した。
給食を一緒に食べながら、
更生施設の話を武勇伝のように語る。
彼らは目を輝かせて聞いてくれた。
まるで、そこでの苦労や努力が
“すごい経験”だったかのように。
僕自身も、語ることで
“強くなったような気がしていた”。
でも、心では分かっていた。
それが“演技”であることも。
話をすればするほど、自分の弱さを
隠そうとしているのが
バレていくような気がしていた。
そんな中でも、僕の中にひとつだけ、
絶対に譲れないルールがあった。
それは、
「真面目に勉強している子には迷惑をかけない」
という線引きだった。
悪友たちが他の生徒の授業を
邪魔しようとすると、僕は必ず真剣に言った。
「他の子たちの邪魔するな!」
それだけは、どうしても譲れなかった。
なぜ、そんな線引きを大事にしていたのか。
それはたぶん、僕自身がなりたかった存在と、
今の自分とのあまりのギャップに、
ずっと苦しんでいたからだと思う。
僕は、ずっと憧れていた。
人を勇気づけ、皆の憧れになれるような、
頼れる人間に。
誰かが困っていたらさりげなく助け、
孤独な子のそばに寄り添えるような存在に。
僕の理想は、そういう
“かっこいい人”だった。
でも現実の僕は、誰よりも弱く、
誰よりも臆病だった。
その弱さを隠すために、嘘をついて、
演じて、見栄を張って、
仮面をかぶり続けていた。
その仮面の裏で、本当の自分は、
ただただ怯えていた。
恥ずかしさと後悔と、過去の影に怯えていた。
だからこそ、せめて――
「真面目に生きてる子にだけは
迷惑をかけたくなかった」
それだけは、唯一守れる
“僕なりの正義”だった。
そんなある日。
まるで静寂を打ち破る雷鳴のように、
僕の心を揺さぶる出来事が訪れた。
それは、想像すらしていなかった、
寝耳に水の“ある事件”だった――。
信じてくれてた後輩のために使った僕の拳
さかのぼる真実——後輩たちの“信頼”が裏切られていた
僕は、シバの肩を後ろから叩いた。
いつものように席で友達と
話していた彼は、何気なく振り返ったその瞬間、
僕の目とぶつかった。
その目に、いつもと違う
怒りの色が宿っていたことに気づいたのだろう。
シバの表情がこわばった。
「俺の名前で3万集めとる?」
僕がそう言った時、シバは明らかに動揺していた。
「え、集めてないよ」――嘘だ。
その瞬間、僕の中の怒りが、
理性の堤防を一気に突き破った。
気づけば、シバを引き倒し、
何度も拳を振り上げていた。
周囲は騒然となり、4人の先生に
取り押さえられ、シバは鼻血を流して
床に倒れていた。
怒りの理由は、暴力そのものじゃなかった。
僕の名を勝手に使い、後輩たちの信頼を利用し、
金を巻き上げようとした――
その行為が、何より許せなかった。
ことの発端は、
数日前の放課後のことだった。
タカハシという友達が、
どこか言い出しにくそうな表情で、
けれど覚悟を決めたような口ぶりで
僕に話しかけてきた。
「珍しいな……足立、
後輩たちから3万集めとるの?」
その一言に、頭が真っ白になった。
「は? 何それ?」
と問い返すと、
タカハシはこう話してくれた。
自分たちが後輩から
お金を集めようとしたら、
後輩たちはこう断ってきたのだと。
「足立先輩から3万円
集めろって言われてるんで無理です」
そんなはずがない。
僕がそんなことを言うわけがない。
タカハシもそれをわかっていた。
だからこそ、普段は僕に内緒で
集めていたお金を、今回は手を引いたという。
僕はタカハシに頼み、
すぐに後輩たちを呼び出してもらった。
タカハシが鋭く切り込んだ。
「お前たち、誰に3万集めろって言われた?」
一瞬の沈黙のあと、
後輩の口から名前が出た。
「……シバ先輩です。
足立先輩が3日以内に
3万集めろって言ってるって……」
僕の胸に、ズキッと痛みが走った。
「そんなこと、俺が言うわけないだろ!
おかしいと思わなかったのか?」
そう詰め寄ると、
後輩たちは申し訳なさそうにこう答えた。
「でも……足立先輩が
そんなこと言うってことは、
きっと余程の事情があるんだろうって
……信じてました」
その言葉が、胸に突き刺さった。
信じてくれていたからこそ、
傷つけてしまった。
僕の名前が、誰かの都合で“武器”のように
使われたことが、何よりも悔しかった。
すでに3万円は集まっていた。
後輩たちを幻滅させたくなかった。
その話を聞いて、
タカハシが苦笑まじりにぼやいた。
「マジか……もう集まったのか。
俺の時なんて5千円も集まらんのに」
少しだけ笑いが起きた。
けれど、僕の中では
笑うどころじゃなかった。
僕は、中1のときに
サトシ先輩にリンチされ、
心が壊れかけた記憶が
よみがえっていた。
あの惨めな、
尊厳を踏みにじられる感覚。
あれを、後輩たちには
絶対に味あわせたくなかった。
それは、後輩のためであり――
何より、
過去の自分を救うためだった。
お金を出してくれていた後輩たちには、
集まっていたお金から1人残らず返金した。
暴力は間違いだった。
それは、あとになって
痛いほど思い知らされることになる。
その場で感情に任せて
手を出したことが、
どれほど理想の自分から外れていたか。
先生たちに取り押さえられたあと、
僕は私服刑事によって覆面パトカーに乗せられ、
警察署へと連れていかれた。
取調室の壁に書かれた落書きの中に、
僕の中学の先輩の名前があった。
その下には、
「嘘とも知らずに」と書かれていた。
その言葉のセンスに、
感心をしている自分がいた。
その“無力な言い訳”が、
あの空間ではなぜかリアルに響いた。
刑事は机をドンと叩いて言った。
「お前が足立か。名前は聞いてるぞ。
お前、ワルらしいな。素直に全部話せ!」
僕が更生施設に入った、という噂が
近隣の中学校に広まり、
大きくなって一人歩きしていたのだ。
けれど、事情を話すうちに、
刑事の態度は
少しずつ和らいでいった。
昼になると、
「カツ丼にするか? 大盛りにしとくか?」
と笑顔になり、
最後にはこう言ってくれた。
「お前、悪い奴じゃないな。
会って話してみないとわからんな」
その言葉が、少しだけ救いだった。
後日、2度目の聴取で、
真相が明かされた。
シバは――ただ、自分の欲しかった
漫画の全巻セットを手に入れるために、
僕の名前を使ったのだった。
学校では、生活指導の先生に呼ばれ、
こんな言葉をかけられた。
「お前は、中2たちのヒーローなんだぞ」
僕は、他人と同じことを
するのが嫌だった。
後輩に偉そうにしたり、シンナーや
タバコに手を出すこともしなかった。
ただ、それだけだった。
でも、それが誰かの勇気になっていた。
後輩たちの「こんな理想の先輩像」
という希望になっていた。
それでも、手を出したことは
間違いだった。
僕の思い描き続ける理想の人間だったら、
暴力を選ばなかったはずだ。
あの時、怒りのままに拳を
振り上げた自分は、
目指していた
“かっこいい人”とは違っていた。
もっと賢いやり方があった。
僕が手を出さなければ、
きっと、未来は
変えられたかもしれない。
でも、僕は間違えた。
暴力は、新たな恨みを生むだけだった――
そのことを、
後に思い知る夜が来ることになる。
この傷害事件のあと、
僕は家庭裁判所に呼び出された。
正直、「これでようやく戻れる」
とすら思っていた。
けれど――更生施設には戻れなかった。
またも、“戻りたい場所”に戻ることは、
叶わなかったのだ。
そのあと、僕の人生で最も恐ろしく、
そして、“本物の友情”と“人間の裏側”が
交差する夜が――
やって来ることになる。
恐怖と信頼の狭間で——影に潜んでいた黒幕と僕の夜
呼び出し電話と震えた声——「俺は行かない」
傷害事件のあと、
僕はシバと表面上は和解した。
でも心のどこかには、
小さな疑念が残っていた。
その不安は、思いがけない形で現実となる。
ある日、地元の繁華街で、
僕の仲間5人が他校の不良集団に襲われた。
制服は破れ、顔には殴打の跡、
服は血に滲んでいた。
その姿は、冗談で
済まされるレベルではなかった。
彼らの一言が、僕の心を凍らせた。
「足立はどこだ?……そう相手が言ってた」
名前を呼ばれていた。
僕が狙われていた。
その場にいたのは、噂で聞いたことのある
名ばかりの強者――
柔道が強いイチムラと、
隣町の中学の“番長”と恐れられたオオタ。
冷たい汗が背中を伝い、心の奥にある
何かがズンと重く沈んだ。
その後も、友達たちが狙われる事件が続いた。
それでも誰も僕を責めなかった。
それどころか、
「次は絶対に負けない」
と、悔しそうに怒りを
滲ませる仲間の姿が、胸に刺さった。
なぜ僕だけが怖がってるんだろう。
なぜ彼らは、みんな強いんだろう?
その自己嫌悪が、静かに、
でも確実に僕の心を蝕んでいった。
日曜日、ハヤセの家に
みんなが集まっていた時、
一本の電話が鳴った。
受話器越しに響いたのは、
冷たい男の声だった。
「来週の日曜、神社に足立を連れて5人で来い」
一瞬、時が止まった。
僕は言葉を失い、タカハシが
「行こう」と言ったのに、
「俺は行かない」
と言うのが精一杯だった。
怖かったからだ。
心が支配され足が震えた。
でも、タカハシの勇敢さが、
眩しくて仕方なかった。
彼の背中を見ていると、
自分の弱さばかりが目についた。
その後、僕は名古屋にいる
旧友ユータに相談した。
肝が据わっていて、
どんな時でも冷静で圧倒的に強い――
僕とはまるで違って、本当の“男”だった。
呼び出しの日、
僕は神社に行かなかった。
その代わりに、ユータが
——名の通った仲間たちを連れて、
現地に向かっていた。
「足立に手を出したら、
お前たち全員、潰すぞ」
そう一言だけ放ち、ユータは
その場の空気を一瞬で黙らせたという。
それだけで、すべてが終わった。
暴力も、報復も、何も起こらなかった。
僕がその出来事を知ったのは、
何日も経ってからのことだった。
僕はユータにこの件を相談はしたが、
「助けてほしい」とは一言も言っていなかった。
彼はそのとき、ただ
「無視しとけばいいわ」
と言っただけだった。
けれど彼は、黙って動いたのだ。
僕が震えていた時間、彼は僕の名と、
僕の想いを守ってくれていた。
安堵と共に、自分が逃げたという事実が、
心の奥で重く沈んでいた。
だが、平穏はすぐに壊れた。
1ヶ月ほどして、白い車に乗った不良集団が、
僕の家の周辺をうろつき始めた。
竹刀やバットを持ち、大勢だ。
また友達が襲われた。僕はもう限界だった。
地元を離れ、
名古屋の友人宅を転々としながら逃げていた。
母との衝突も重なっていたけれど、
本当の理由は――ただ、怖かったからだ。
けれど、ある日。
地元の友達と会う約束があり、
ほんの一時だけ地元に戻ったタイミングがあった。
ユータとも仲間である旧友・カツヤと、
夜の地元を歩いていた。
その時だった。
……あの白い車が現れた。
静かに止まり、背の高い男が降りてきた。
「お前が足立か?」
その一言が、世界を凍らせた。
心臓が喉に上がってくるような、理屈じゃない恐怖。
強がって言葉を返した。
「お前誰だ?」
「深山中のユカワだ。お前、
なんで呼び出しに応じんのだ!」
横にいたカツヤが、毅然とした声で言った。
「足立に手を出したら、
俺たちがお前たちを潰すからな。
それを覚えとけ」
カツヤもユータと同じ事を言った。
その言葉に救われた。
その後、ユカワと道端に座り、
3人で1時間近く話をした。
そして、真相が明かされた。
すべては、シバの仕組んだ復讐劇だった。
僕が先頭に立って隣の中学校の番長
オオタを馬鹿にしている――
そう聞いている、と言うのだ。
そんな事実は一切なかった。
それなのに、
シバはその嘘をオオタに吹き込み、
火をつけたのだ。
和解したはずの、あのシバが。
ユカワは僕の目を見て、信じてくれた。
僕は、オオタについて
何一つ悪口を言ったことがないと、
はっきりと伝えた。
そして、シバと僕との間に何があったのか、
すべてを話した。
その誠意が伝わったのか、
ユカワは真実をオオタに話してくれた。
やがて誤解は解け、すべてが収まり
事件は静かに幕を閉じた。
でも僕の心は、完全には終わらなかった。
恐怖、情けなさ、
そして友人たちの優しさが
交錯する夜
――そのすべてが
焼きついて離れなかった。
それから一年後のことだった。
ある日、地元の先輩たちと一緒に、
暴走族の先輩たちが
たむろする場所へ
顔を出した時のことだ。
そこには、かつて
“番長”として恐れられていた
オオタの姿があった。
だが、彼はもう以前のような
威圧感をまとってはいなかった。
怖い先輩たちの指示を黙って聞き、
まるで使い走りのように動いていた。
僕は、黙ってその光景を見ていた。
何も言葉は交わさなかった。
ただ、近くの自販機で買った缶ジュースを、
無言のまま彼に手渡した。
オオタは一瞬、驚いたような
顔をしたあと僕に気付き
ふっと微笑んだ。
それだけだった。
でも、その一瞬の表情の中に、
すべてが詰まっていた気がした。
あれが、本当の
和解だったのかもしれない。
見えない正義に裁かれた日 — 僕が中学を中退した理由
正義の仮面を被った「排除」
他校とのイザコザがようやく収束し、
僕のまわりにも、
ほんの少しだけだが「平穏」と
呼べる空気が戻っていた。
だが、その静けさは、
まるで嵐の前の静寂だった。
何の前触れもなく、僕の人生を
根底からひっくり返す出来事が起こる。
それは、ある“権力を持つ人物”の
手によって、
静かに仕組まれていたのだ。
その人物は、表では秩序と
公正の象徴のように
振る舞っていたが、
裏では僕の存在を煙たがり、
静かに排除のタイミングを探っていた。
その日、僕は校舎の前で、
友達と他愛もない会話を楽しんでいた。
笑い声が交わる中、
遠くから異様な気配を感じた。
目を凝らすと、怒気に満ちた形相の
大人たちがこちらに向かって
一直線に歩いてくる。
その先頭には、校長先生がいた。
彼は僕の前に立ちふさがると、
怒りを剥き出しにして、
こう言い放った。
「お前が学校に来ると、
他の生徒に悪影響だ!
もう二度と学校に来るな!」
その瞬間、
周囲の空気が凍った。
背後には、
見慣れない大人たちが数名いた。
彼らがPTAの関係者だと知ったのは、
ずっと後のことだった。
隣にいたハヤセが怒りを爆発させ、
食ってかかった。
「なに!? おい校長!!
お前がやめろ! 黙って帰れ!!」
けれど僕は、すぐに彼を制した。
怒りや混乱が
なかったわけじゃない。
それでも僕は、あの瞬間、
心の奥でこう思っていた。
──校長先生の言っていることは
正しい。
荒れた中学。
追い詰められる教師たち。
そして、PTAや教育委員会が
守ろうとした“真面目な生徒たち”。
彼らの動機が「悪」
ではなかったことを、
僕は知っていた。
ただ、僕は
「そこにいないほうがいい存在」
として、完全に定義されていたのだ。
僕の意識の中では、真面目な
生徒たちとも対等に接していたし、
怖がられている実感もなかった。
でも──“シバの事件”があった。
あの一件が、“社会側”の目に僕を
「問題児」として映すには十分すぎた。
担任や生活指導の先生も、
こう言っていた。
「お前の名前は、毎回
会議で出てくるんだよ。
校長も大変なんだ」
僕の中の正義や信念なんて、
彼らにとっては理解不能の
“異物”だったのだ。
今思えば、あのとき真正面から
僕に向かってきた校長先生は、
「見て見ぬふりをしなかった」
数少ない大人だった。
あの日、彼は責任と覚悟を背負って、
堂々と“自分の足で”やって来た。
誰かの言葉を伝言するだけじゃなく、
自分の言葉で、僕を裁いたのだ。
僕はあの人を、憎むことができなかった。
むしろ──立派な大人だったと
今でも思っている。
その日、僕は中学校を中退した。
心のどこかで、こう思っていた。
「これで、今度こそ更生施設に戻れる」
僕が“本当の自分”でいられた、数少ない時間。
だけど──現実は甘くなかった。
僕の都合よく、人生が
運ばれることなんてなかったのだ。
僕が信じた初めての大人
誰かに甘えていい時間が終わった。
ふと立ち寄った、地元の中華料理屋
「高木飯店」。
よく遊びに行っていた馴染みの店だ。
その厨房から顔を出したのは、
仲の良い同級生の父親
──あの店の大将だった。
目が合った瞬間、彼はまっすぐに
僕を見て、こう言った。
「足立、お前、学校クビになったのか?
それなら、ここで働くか?
最初は給料も安いぞ!」
その一言を聞いた瞬間、心が一気に跳ねた。
迷いなんて、1秒もなかった。
「本当?やるやる!」
と即答していた。
考えるより先に、体が動いた。
というか、あの時の僕にとって、
その言葉は“救命ロープ”みたいな
ものだったんだと思う。
僕は大将のことが、本当に大好きだった。
あの声も、豪快な笑いも、たまに
見せる厳しさも。
だからこそ、その言葉がどれほどの
救いだったか、今でも忘れられない。
大げさじゃなく、あの日、大将のたった
一言が、僕の“居場所”をつくってくれた。
中学3年生にして、
誰よりも早く“社会”に出た。
僕の仕事は、皿洗い、餃子の仕込み、
油でギトギトになった床の掃除。
厨房は、熱気と湯気と怒鳴り声で満ちていた。
けれど、不思議と苦じゃなかった。
むしろその空間で、僕は“生きてる”って
感じていた。
逃げ場所じゃなく、“自分の居場所”が
そこにあった。
大将は、僕をとても可愛がってくれた。
ときに父親のように叱ってくれ、
ときに兄貴のように背中を見せ、ときには
くだらない話でゲラゲラ笑い合った。
僕も、彼には何も隠さず話せた。
怒りも、迷いも、悔しさも。
ありのままをぶつけられた。
それがどれほど特別なことだったか、
今になってよくわかる。
あんなふうに、真正面からぶつかれる
大人なんて、人生で
何人いたって言えるだろう?
仕事が終わると、大将は僕を連れて、
毎晩スナックに行った。
あそこが、僕にとっての
“初めての大人の世界”だった。
カラオケのリモコンを回しながら、
ウイスキーの水割りを作る店員の横で、
僕はただ静かにその空気を吸っていた。
集まっていたのは、20代から30代前半の男女。
元暴走族の男たちと、近所の総合病院で
働く看護師の女性たち。
今思えば、なんとも奇妙で、でも妙に
居心地の良い空間だった。
みんなが、15歳の僕を「子ども」
として扱わなかった。
むしろ“ひとりの男”として接してくれた。
女性たちは、笑いながら僕に言った。
「この子?15歳だって!?可愛い〜!」
男たちはご飯に連れていってくれたり、
バーに誘ってくれたり、ときには
ドライブやツーリングにも連れていってくれた。
あの世界にいた誰もが、自然に
僕を輪の中に入れてくれた。
もちろん、最初は緊張していた。
年上ばかりのその空間に、
ぽつんといる15歳。
肩がこわばって、笑い方もぎこち
なかったはずだ。
でも、彼らの自然な言葉や仕草が、
少しずつ僕の緊張を溶かしていった。
次第に僕は、勝手に勘違いしはじめた。
「もう俺は、大人なんだ」そう思い
込むようになっていた。
“守られる側”であることを、自分から手放した。
そしていつの間にか、“戦う側”に立っていた。
あの日々は、強烈だった。
忘れられないほど鮮やかで、
息が詰まるくらい濃密だった。
そして、少しだけ寂しかった。
あの世界は、確かに僕に“居場所”をくれた。
だけど同時に、僕から
“子どもでいられる最後の時間”を、
そっと奪っていった。
僕は気づかないうちに、もう戻れない
場所まで来てしまっていた。
その一言が信頼を終わらせた
言い訳をする者に、成長はない
ある日、10歳年上のサワムラさんと会う約束をしていた。彼は元暴走族で、どこへ行くにも僕を連れていってくれる、兄のような存在だった。気づけば僕は、誰よりも彼に頼り、誰よりも彼を信じていた。その日も、サワムラさんの経営する会社で落ち合う約束だった。けれど僕は、約束の時間に1時間ほど遅れてしまった。理由がなかったわけじゃない。でも僕の中には、「怒られることはないだろう」という甘えがあった。あれだけ可愛がってもらっていたし、僕がちょっとくらい遅れたって、笑って許してくれるだろうと――そう、思い込んでいた。ところが、そんな僕の考えは、あっさりと打ち砕かれた。会社に着くやいなや、サワムラさんは鋭い目で僕を睨みつけ、怒声を浴びせた。「おい、足立!いい加減にしろ!時間を守れない奴は、大事な約束でも簡単に破る奴だ!」一瞬、何を言われているのか分からなかった。でもすぐに、その言葉の意味を理解した。
サワムラさんは、その日、僕をある“知り合い”に紹介する予定だったのだ。けれど、僕の遅刻によって、その約束をキャンセルせざるを得なくなってしまった。その結果、彼は自分の顔に泥を塗られた形になったのだ。それでも僕は、自分なりの理由を必死で説明しようとした。「こういう事情があって…遅れたのは俺のせいじゃなくて…」でも、そんな言葉を聞いたサワムラさんは、さらに怒った。「お前、全然反省してないな!それ、全部“言い訳”だぞ!!」その言葉が胸に刺さった。けれど僕は、それでもなお食い下がった。なぜなら本当に仕方のない理由があったからだ。それをわかってもらえれば…と、まだ信じていた。「謝ることもできんのか?それにな、遅れるなら電話ぐらいできただろうが!」その一言で、初めて僕は自分の無責任さに気づいた。
でも――その時にはもう、手遅れだった。僕は最後の最後まで、自分の態度を変えることができなかった。
素直に頭を下げることもできず、心から謝ることもできず、ただ“事情”を話すことしかできなかった。その日を境に、あれほど可愛がってくれていたサワムラさんは、僕を完全に突き放した。
どこに行くにも一緒だったのに、もうどこにも連れていってくれなくなった。
連絡も、ぷつりと途絶えた。その時、ようやくわかった。
“言い訳”というものが、どれほど人の心を遠ざけてしまうのかということを。言い訳をするというのは、つまり「自分は悪くない」「これは自分の責任じゃない」と言っているのと同じだった。そして、そんな姿に人はがっかりする。心が離れていくのも当然だった。「言い訳をする者に成長はない」
そうはっきりと、この時、僕の中に刻まれた。大切な人を、自分の手で失った。兄のように慕っていた人の背中が、もう二度と振り向かなくなった――
その現実を噛み締めたとき、僕は、ただただ愚かだった自分を、心の底から悔やんだ。悔やんでも、悔やみきれなかった。※その後、20年以上の時を経て、関係は再びつながっている。
やめられなかった夜遊び
守りたかった人たちから、僕は逃げた。
僕はその後、地元のひとつ年上の先輩から、400ccの改造バイクを5万円で売ってもらった。免許は持っていなかったけれど、そんなことは気にも留めなかった。僕はそのバイクを無免許で乗り回すようになった。エンジンをかければ、町中に爆音が響く。どこへでも行ける。どんな夜にも飛び出せる。その感覚は、確かに僕を自由にしてくれた。ヘルメットもかぶらず、爆音を響かせながら町を走る僕。危険なんてことよりも、ただその“開放感”に酔っていた。なのに、そんな僕を近所の人たちはなぜか嫌わなかった。むしろ、好意的に接してくれた。「おばさん、こんにちは!」と、笑顔で挨拶をすれば、
「いい色になったねぇ〜」と返してくれる。
「でしょ〜?塗るのが大変だったんだよ」と、僕も自然に応じていた。あの町には、僕を1人の人間として受け入れてくれる人たちがいた。
自由を手に入れた僕は、地域にも愛されていた。――そんな気がしていた。けれどその一方で、僕の生活リズムは完全に崩れていた。
夜は遊びに出て、朝に帰ってくる。そんな日々を繰り返していた僕は、次第に中華料理屋の営業時間に間に合わなくなっていった。「はっはっは!若いうちだけだぞ〜!」
大将は笑って受け流してくれた。でも、従業員のカガミさんやマツモトさんには、そうはいかなかった。
「おい足立!仕事をなんだと思ってるんだ!?遊びじゃないぞ!!」
厨房に響くその一喝が、胸に突き刺さった。僕は、はっとした。「こりゃダメだ。ここのみんなには、これ以上迷惑をかけられない」
そう思った僕は、1年半ほどお世話になった中華料理屋を辞めることを決めた。大将も、カガミさんも、マツモトさんも、大好きだった。
辞めたくて辞めたわけじゃない。でも――遊びをやめる覚悟もなかった。
本当は、生活を改めるだけでよかったのに。
それすらも、当時の僕にはできなかった。その後、カガミさんもマツモトさんもそれぞれ独立して、自分の店を持った。
特にカガミさんとは家も近く、今でもたまにご飯を食べに行くしよく会う。
そのときには、あの頃の話が笑い話として出てくる。バイクにまたがり、先輩たちと走り回る夜。
朝まで遊ぶことが当たり前になった僕は、こう思い始めた。
「次は、朝寝坊しても心が痛まないような、知らない人のもとで働こう」好きな人たちに迷惑をかけるくらいなら、
最初から何の情もない場所で、何の責任も感じずに働こう。――僕は、大切な人たちから目を逸らすように、“逃げる”という選択をした。
刺青の背中と、最後の晩餐
その背中は、恐怖ではなく安らぎだった
中華料理屋を辞めた僕は、朝まで遊び、夕方からは毎日のようにパチンコ屋にいた。
とはいえ、僕がパチンコを打つわけじゃなかった。パチンコをする先輩たちの隣に座って、話し相手になっていただけだった。毎日のようにパチンコ台に向かう先輩たちを眺めていて、気づいたことがあった。
「パチンコって、勝てないんだな」と。
ほとんどの先輩たちは、負けて帰っていった。16歳の僕は、そんな先輩たちを見ているうちに、ギャンブルへの欲がまるで湧いてこなかった。
タバコも酒もゴルフも…みんながハマっていくものに、僕は全く興味が持てなかった。
時間が、もったいないと思えてならなかった。
その時間とお金を、もっと自分の興味あることに使いたかった。そんなある日。
友人のタカハシと2人で、いつものようにパチンコ屋の駐車場で先輩を待っていると、背の低い愛嬌のあるおじさんが声をかけてきた。「兄ちゃんたち、景品交換所ってどこにある?」そこから、10分ほど雑談をした。話しやすくて、面白くて、不思議と惹かれるおじさんだった。
次の日も、そのおじさんはパチンコ屋に来て、また僕たちと話した。
そんなやりとりが数日続いたある日、そのおじさんがふと聞いてきた。「兄ちゃんたち、仕事してないのか?」「してないよ」と答えると、すぐに返ってきた言葉が――「うちで働いてくれんか?」
彼は鉄工所を経営している社長だった。
僕たちはすっかりこのおじさんが好きになっていて、迷わず「お願いします」と答えた。鉄工所は隣の市にあり、僕たちは原付で通うことになった。
初出勤の日、おじさんの他に、見るからに“悪そうな男”が2人すでに作業していた。
鉄筋の溶接が主な仕事で、朝から黙々と作業が続いた。昼になって、4人分の弁当が届いた。
僕とタカハシ、そしてその2人で一緒に食事をしたのだが、話す内容に、妙な違和感を覚え始めた。1人は僕たちと同じ16歳。もう1人は28歳。
どちらも二グロパーマに剃り込み、見るからに“その筋”の雰囲気だった。でも驚いたのは、外見じゃない。
2人とも、驚くほど気さくで優しかったからだ。
ただ、口にする話がどう聞いても「暴力団の会話」だった。僕とタカハシは顔を見合わせ、無言で首を傾げた。色々と話を聞いていくうちに、この鉄工所は――
暴力団の“表向きの会社”だということが分かってきた。「最近は忙しいから、組事務所より鉄工所に来ている」そんな言葉が、あたりまえのように交わされる職場だった。16歳の彼は「ヤクザになるのが早すぎた、18くらいがちょうどよかったな」
28歳の彼は「俺は逆だ、もっと早く入っておけばよかった」
と笑いながら話していた。僕は頭の中でずっと考えていた。
“僕らは今、この人たちと同じように組員にされようとしているのか…?”でも、その2人は僕たちを勧誘することもなければ、怖がらせる言動も一切なかった。むしろ気遣ってくれていた。ある日の仕事が終わると、おじさんが「うちで晩ごはん食ってけ」と言ってくれた。
車の後ろを原付でついていくと、着いたのは小料理屋。どうやら奥さんが店をやっているらしく、出てきた食事はとても美味しかった。
奥さんも、明るくて気さくで、どう見ても“良い人”だった。そのとき、おじさんが「温泉でも入りに行くか」と言って、服を脱ぎ始めた。奥さんがニコニコしながら「…あーあ、見られちゃったね」と言う。その瞬間、目の前に現れたのは――
おじさんの全身に彫られた、美しいほどに鮮やかな刺青だった。そう、おじさんは現役の暴力団幹部だった。
鉄工所も、その組織が経営する会社だった。でも、驚きや恐怖よりも先に湧いたのは、「やっぱり、そうだったか」という納得と、
「でも、この人が怖いと思ったことは一度もない」という、不思議な安心感だった。次の日から、タカハシは無断欠勤した。
僕は1人で鉄工所に通った。
ただし、1ヶ月で辞めようと心に決めていた。ある日、僕は意を決しておじさんに辞めたい旨を伝えた。「そうかぁ、残念だけど仕方ないよな。分かった、それじゃあお前にはちゃんと給料を払うからな」優しい口調だった。でも僕は、その給料を受け取らなかった。
怖かったからじゃない。
裏の世界に深入りしたくなかったからでもない。最初から最後まで、おじさんのことが好きだった。
その人の期待に応えられなかったことが、ただ申し訳なかったからだった。最後まで、あの2人もずっと優しくしてくれた。
今でも思う。
あのおじさんは、本当に――心から、僕たちを“鉄工所の仕事だけ”させようとしていたんだろうと。
自由にされた朝、僕はなぜか立ち上がった
義務じゃない責任
明日来なくていいと言われて、なぜか通い続けた鉄工所を辞めたあと、僕は地元の先輩の父親が営む防水工事の会社に拾われた。
その社長とは面識すらなかった。
けれど、だからこそ、なぜか気が楽だったのを覚えている。面接らしい面接もなく、即採用。
給料は、これまでの中華料理屋の倍の20万円。
“うわ、俺の人生、やっと上向いてきたんじゃないか?”――その時は、本気でそう思った。けど、それ以上に衝撃だったのは、就業ルールが常識の範囲を遥かに超えていたことだった。「朝6時半に来れたら現場行こう。無理なら来なくていい。電話も連絡も要らない。
若いんだし、遊びたいなら遊べばいい」そう、社長は言い切った。
信じられないくらい自由なシステム。
連絡も不要、自己申告も不要、欠勤も評価に一切影響しない。
まるで、“遊び人にとっての理想郷”みたいな職場。実際、僕は歓喜した。
ようやく、誰にも縛られない自由を手にした気がしていた。
遊びまくってもいい。明日、寝坊しても誰にも責められない。
「明日」という存在すら、好きなように扱える感覚。だけど――不思議なことが起きた。僕はその職場を、一度も休まなかった。何度も朝帰りしたのに、
何度も眠くて朦朧としたのに、
不思議と「休もう」とは思えなかった。たしかに僕は、自由を手にした。
なのにその自由の中で、なぜか、自分で自分を律するようになっていた。自由ってなんだろう。縛られていたときほど、逃げたかった。
でも、逃げていいと言われた瞬間、なぜか立ち止まってしまう自分がいた。誰かに課された義務じゃない。
“自分で決めた責任”の方が、ずっと重く感じることがある。あれは、初めて自分の意思で働いた感覚だったのかもしれない。しかし、その後、現場では最古参の従業員から、社長不在の時を狙った理不尽な要求を何度も押し付けられた。限界を感じ、僕は現場をボイコットしてその場を離れ、そのまま退職した。退職後に、社長の奥さん、つまり、先輩の母親から「あの人は以前から同じようなトラブルを何度も起こしていた」と経緯を聞かされ、逆に謝られた。仕事自体は楽しく、やりがいもあっただけに、とても残念だった。
皆勤賞だった、間違った自由
心の中にいた、もう一人の僕
毎日、僕は1つ年上のカナモリ先輩の家へ通った。
その離れの部屋は、誰にも見られず、咎められず、ただ自由だけが漂っていた。そこには、毎日20人近い不良仲間が集まっていた。
僕がジョギング中に出会った、あの地元で有名な凶暴なサトシ先輩も、カナモリ先輩の仲間だったらしい。
だが、僕が通い出す頃にはサトシ先輩はもう地元におらず、住み込みでどこかへ行っていた。カナモリ先輩は、韓国籍の先輩で、見た目こそやんちゃだったが、後輩を虐めるような人ではなかった。
むしろ、後輩をいじめているサトシ先輩を怒鳴りつけるような、義理堅い人だった。その部屋に集うのは、市内の様々な中学校の不良たち。
暴走族のリーダーやメンバー、隣町の先輩、みんな揃いも揃って“問題児”と呼ばれたような面々。
彼らはシンナーを吸っていたが、僕に勧めてくることは一度もなかった。部屋でマンガを読み、話をし、飽きれば誰かが「このあとどうする?」と声を上げる。
夜になるとご飯を食べに行き、そしてバイクの爆音を響かせながら、小高い山のてっぺんまで走る。「誰にこの音、聞かせたかったんだろうな…」
今思えば、ただ“何かを叫びたかった”のかもしれない。
本当は、みんな将来が怖くて、不安で、でもそれを隠す術しか持ってなかったのかも知れない。日曜だけは、ボウリングやホームセンター巡りが追加される。
そんなローテーションを、僕は365日、1日も欠かさずに続けた。
学校へは通えなかった僕が、唯一“皆勤賞”だった場所。昼間でも必ず誰かがいる、不良たちのオアシス。
安心感。
だけどそれは、本当の安心ではなく、“孤独を見ないための安心”だった。そんな日々が1年を越えた頃、ふと心の奥の扉が開いた。
不意に押し寄せてきた、初めての感情。「このままでいいのか…?」それは確かな“もう一人の自分”の声だった。
あの更生施設で変われたはずの自分は、また流されていた。
また“楽な方”へと身を委ねていた。人は、ひとりでは簡単に堕ちていく。
あの頃の僕が変われたのは、寮長や寮生たち――“誰かに見られている環境”があったからだ。
「みんなで頑張る」という空気が、僕を持ち上げてくれていた。でも今は違う。
誰も僕を見張ってくれない。
誰も僕を変えてくれない。
ここに居てはダメだ。僕は、もう一度変わらなければならない。あの頃より強く、そう思った。そして僕は決意した。
「1人の時間を作ろう」と。このまま、ただ流れに身を委ねていては、理想の場所には辿り着けない。
自分の流れを、自分の意思で創らなければならないのだ。
最初の記憶と、しげちゃんの背中
しげちゃんが、人生の始まりに灯した光
僕がこの世に誕生してから、思い出せる最初の記憶。それは、隣に住んでいた3つ年上の幼なじみ、しげちゃんとの記憶だ。何度思い出そうとしても、それ以前の記憶は、音のない白い霧のように曖昧で、何も掴めない。
ただ、その霧の中から最初に浮かんでくるのは、夏の日差しに照らされた、しげちゃんの後ろ姿だった。太陽が真上から降り注ぎ、アスファルトがかすかに揺らめいている。
僕はその背中を追いかけて、少し小走りでついていく。まるで兄弟のように、当たり前のように、いつもしげちゃんの後ろを歩いていた。「ひろし、これ出来る?」その一言が合図のように、僕のなかの“挑戦”が始まる。
しげちゃんは僕にとって、世界で一番かっこいい“先生”だった。
何でも軽々とやってしまうしげちゃんを見ていると、「できない」なんて発想は浮かばなかった。僕がまだ2歳や3歳だったから、難しさなんて概念がなかったのもある。
でも、それ以上に、“目の前にお手本がいる”ということが、僕の中に安心と自信を与えていた。このしげちゃんとの思い出は、のちにラジオ番組でも紹介され、ラジオドラマになったほどだ。
それほどに、この記憶は特別で、まっすぐで、今でも僕の胸の中に静かに息づいている。まだ4歳の僕が自転車に乗れるようになったのも、まぎれもなくしげちゃんのおかげだった。
毎日、しげちゃんは自転車の後ろを押してくれた。
ある日、母が聞いた。「しげちゃん、ひろしどう?自転車、乗れそう?」しげちゃんは、少し照れながらも自信たっぷりに答えた。「もうすぐ乗れるよ」その言葉に、僕はひと欠片の疑いも抱かなかった。
しげちゃんが言うなら、間違いない。僕は純粋に、「すぐに乗れるようになる」と信じていた。そして、いよいよその日がやってきた。
しげちゃんは、僕の背中に手を添えながらこう言った。「ひろしは真っすぐ前だけ見て漕ぐんだぞ!絶対に後ろ見るなよ、いいな!」「うん!」僕は全力でペダルを踏んだ。
しげちゃんが後ろにいてくれる、という安心感。
その温もりに包まれながら、僕はひたすら前を見て、がむしゃらに漕いだ。――でも、ふと気づいた。
今日はなんだか、やけに長く走っている。
しげちゃんの足音が、聞こえない。僕は思わず後ろを振り返った。――そこには、遥か遠くで両手を大きく振るしげちゃんの姿があった。「お~い!ひろし~!やったなぁ~~!」胸が熱くなった。
嬉しくて、嬉しくてたまらなかった。「やった……乗れた……乗れた……」初めての“独り言”が、口からこぼれた。
今でも、その時の感覚を鮮明に覚えている。
ぐらぐらと不安定な足取りでペダルを踏みながらも、自分が“自由を手にした”ことに、確かに気づいていた。「しげちゃんの言う通りにすれば、なんでもできるんだ」
そう信じていた。心の底から。僕はしげちゃんのことが大好きだった。
僕にとってのヒーロー。僕の人生の土台を作ってくれた人。
野球も、縄跳びも、水に潜ることも、すべてしげちゃんが教えてくれた。「自分にもできるんだ」と思えること。
それは、子どもにとって何よりの力になる。
しげちゃんの存在は、僕にその“力”を与えてくれた。でも――
そんなしげちゃんとの日々は、長くは続かなかった。ある日、突然聞かされた。
「しげちゃんが、病気になったんだよ」僕の中で、季節が止まった。このまま物語が次へ進む場合は、最後に次のようなフレーズで締めると効果的:そして僕は、この“最初の記憶”が、人生のどんな嵐にも消えずに灯る、小さな光になるとはまだ知らなかった。
居なくなった僕のヒーロー
“遊べない病気”が教えてくれた終わり
いつものように、しげちゃんを呼びに行った。
ドアをノックすると、しげちゃんのお母さんが玄関からゆっくりと顔を出した。「あぁ、ひろし君……ごめんね、しげちゃんね、今日はお病気で遊べないのよ」その声には、かすかに張りつめたような寂しさが滲んでいた。
僕は素直に聞き返した。「どんなお病気?」おばさんは少し困ったような顔をして、優しく言った。「お外で遊べないお病気なの。ごめんね、また元気になったら遊ぼうね」僕は「うん」とだけ答えた。けれど、胸の奥に小さな不安が灯っていた。
次の日も、その次の日も。しげちゃんは、やっぱり“病気”だった。
遊べない理由が、少しずつ言葉にならない違和感に変わっていった。僕は、しげちゃんがいない日々に慣れられなかった。
何をするにも、しげちゃんの真似をしていたから、ひとりになると何も自信が持てなくなってしまった。しばらくして、僕たち家族は引っ越すことになった。
あの空き地も、あの坂道も、しげちゃんとの思い出が詰まった町を離れることは、子どもながらにとても寂しかった。新しい町。新しい幼稚園。
新しいクラスメートたちの中に入っていくのは、まるで水に潜るような不安だった。しげちゃんのことは、少しずつ思い出の中に沈んでいった。
小学1年生になる頃には、ほとんど彼の顔も思い出せなくなっていた。でも――ある土曜日。
小学校が半日で終わり、ランドセルを投げ出してお気に入りのテレビ番組を観ていたときのことだった。「リ〜ン、リ〜ン」電話の音が鳴った。
その瞬間、胸の奥が一気に凍りついた。
理由なんてなかった。ただ、わかってしまった。
――しげちゃんのことだ、と。心臓の鼓動が、爆発するように跳ね上がった。
全身の血が逆流するような感覚と、寒気。
それでも僕は、テレビの画面を見つめ続けた。「はい、もしもし足立です」母の声が、受話器の向こうに沈んでいった。
その声の調子が、どんどん変わっていく。「あぁ、こんにちは……」……沈黙。「……うそ? うそ……」母の声が震えたかと思うと、その場に崩れ落ちた。泣き崩れる母。
その姿は、普段怒鳴るときの強い母とはまるで別人だった。
嗚咽と嗤(わら)いの区別もつかないような声で、泣きじゃくっていた。僕は、怖くなって言葉を探した。
テレビの中の話を無理にでも喋り続けた。
何か話していないと、自分が壊れてしまいそうだった。電話を切った母が、僕の方を見て、ゆっくりと口を開いた。「ひろし……」僕は、何も知らないふりをした。
でも本当は、すべてわかっていた。「……しげちゃん……死んじゃったんだって……」その一言が落ちてきた瞬間、世界が静止した。
音が消えた。
空気が止まった。僕は、泣くこともできなかった。
母が泣き崩れている姿を見て、「泣いたらいけない」と思ってしまった。
でも本当は、怖くて、寂しくて、どうしようもなかった。どうして、わかったのだろう?
電話の音を聞いた瞬間に。
なぜ、僕はあの予感を受け取ってしまったのだろう?しげちゃんは、白血病だった。
“お外で遊べない病気”――それは、もう“戻れない病気”だった。僕のお手本で、いちばん近くにいたヒーローのような存在が、もうこの世にいない。
その現実を、7歳の僕はどこまで理解できていたのだろう。けれど確かに、僕は初めて知った。
人は死んでしまうんだ。
そして、もう二度と会えないんだ。
この喪失が、幼い僕の心に刻んだ感情――
それは、「悲しみ」よりも「恐怖」だった。
死とは、いつ訪れるかわからない、言葉の通じない終わり。
それを、僕はしげちゃんの死から、痛みとともに学んだ。しげちゃんは、どんな気持ちであの時間を過ごしていたのだろう?
寂しかっただろうか? 怖かっただろうか?
僕のこと、思い出してくれたことはあっただろうか?胸の奥で静かに響き続けるこの問いは、今でも僕の中で、完全には消えていない。
しげちゃん探しの終わりと、僕の始まり
誰かを探す心が、“自分で選ぶ力”に変わった日
僕が物心ついた頃にはもう、いつもしげちゃんの背中を追っていた。
しげちゃんは、僕にとって“安心”そのものだった。大人になった今、ようやくわかる。
僕は、しげちゃんの中に「未来の自分の姿」を見ていたのだ。しげちゃんが亡くなったあと、僕の中に、ぽっかりと空洞ができた。
どんなに笑っていても、どんなに賑やかな場にいても、心の奥にずっと付きまとう不安。その不安は、元々抱えていたPTSDの症状とも重なってしまい、
世界が急にぐらつき始めるような感覚に、僕は毎日飲み込まれていった。
あの感覚を、僕は一生忘れないと思う。――その不安を埋めようと、僕は無意識に“しげちゃんの代わり”を探し始めた。年上の人に出会うたび、
「この人は、僕を安心させてくれる人だろうか?」
「この人は、僕のお手本になってくれるだろうか?」
そんな基準で、いつも心の中でジャッジしていた。でも、どれだけ優しそうに見えても、どこかで違う。
「これだ!」と思っても、時間が経つと、しげちゃんとは違う部分が浮き彫りになる。
僕は気づかないうちに、“理想のしげちゃん像”を、頭の中に作り上げていたのかもしれない。しかも、その理想像のしげちゃんは、僕の成長と共に“勝手に大人へと成長していっていた”。
生きていたら今ごろ、こんな風な大人になっていただろうな――
そんな風に、僕の空想の中で、10歳で止まったはずのしげちゃんは、年を重ね、
どんどん高い理想像へと膨らんでいった。そして僕は、幼いなりに思っていた。
――「じゃあ、これから誰を見習って生きていけばいいんだろう?」何か困ったことが起きると、いつも僕は心の中で問いかけた。
「しげちゃんだったら、こんな時どうするんだろう?」しげちゃん探しは、ずっと続いた。
小学4年生になるまで、ずっと。
しげちゃんを探し続けた、4年間の問い
ある日、僕は2つ年上の野球部キャプテン・タッちゃんに出会った。
優しくて、面倒見が良くて、誰からも慕われている人だった。「あ、しげちゃんみたいな人だ」
僕はそう思った。そう信じた。だけど、タッちゃんが中学に進むと、
僕を“ただの小学生”として扱うようになった。
少しずつ、距離ができた。それが、悲しくてたまらなかった。「しげちゃんは、もうどこにもいないんだ」ようやく、僕はその事実を受け入れた。
そして、しげちゃん探しをやめた。でも、心の奥にはずっと“しげちゃんの理想像”が残っていた。
それはまるで、僕自身の“進むべき人間像”のようだった。
もう居ないのに、今も導いている存在
時は流れ、僕は17歳になった。
カナモリ先輩たちとダラダラ過ごす毎日のなかで、
ふと、あの頃のしげちゃんを思い出すことが増えていった。「しげちゃんがいたら、きっとこんな生活にはなってない…」そう思った時、僕の中に「変わりたい」という想いがふつふつと湧き上がった。――変わろう。しげちゃんみたいな人間になろう。そう決意した僕は、心の中で何度も何度も叫んだ。
「絶対に今度こそ変わる。絶対に!絶対に!!」毎朝、自分に言い聞かせた。
心の中にしげちゃんの声を思い浮かべながら、理想の姿をなぞった。けれど、10日が過ぎ、2週間が過ぎる頃、
あの強かった気持ちが、すっと霧のように薄れていった。「あれ……?どんな気持ちで変わろうと思ってたんだっけ?」焦った。どうしようもなく、焦った。
2週間前の“決意”を取り戻そうと必死になった。
だけど、何度探しても見つからない。まるで、昨日まであった地図を失くしたような感覚。
心が折れそうだった。――「俺は一生、このままのダメ人間なんだ」そう思った瞬間、何かが音を立てて崩れた。
僕の中で、“変われる希望”がしぼんでいった。
希望が消えたあとに残ったもの
それでも僕は、惰性のように先輩たちのたまり場に顔を出した。
変わりたいのに、変われない。
その無力さに押し潰されそうだった。そして、ふと考えた。「しげちゃんのような人はいない。自分では自分を変えられない。
――なら、環境を変えるしかない」そう決めた時、初めて“自分の足で人生を変える”という発想が生まれた。「ここにいたら、また同じだ。独りになろう」そう思った僕は、すぐに住み込みの仕事を探し始めたのだった。
ぬるい檻の中で腐る前に
“ここ”を出る、それがすべての始まり
「“優しさ”って、時に麻薬になり得る事なんだと思う。
心地よさの裏側で、ゆっくり壊れていくことに、人はなかなか気づけない。」
僕は今、逃げ場のように見えていたこの場所が、実は“ぬるま湯の檻”だったことにようやく気づき始めていた。意志が弱く、甘えてばかりで、ただ流されるように生きていた僕は、この環境から脱出したい、いや、脱出しなければいけない──そう思うようになっていた。住み込みの職探しは主に大工や鳶だった。探し始めて2週間が経った頃、3軒ほど目星をつけていた中から、僕は県外にある大工の会社に電話をかけてみた。「もしもし、あの〜、住み込みで働くことはできますか?」「あぁ、できるよ。いつから来れる? 大工の経験は? 今、何歳?」思いがけず、電話の向こうはとてもウェルカムな雰囲気だった。住込みの職探しは、思ったほど難しくなさそうだった。その日の夜も、いつものようにカナモリ先輩の家には先輩たちが続々と集まってきた。その中で一番仲の良かった、例の隣町のオオタと同じ中学で番長だった先輩──ヒロマサ先輩にだけは、僕の決意を伝えようとした。「ヒロマサ先輩、俺、住み込みで働きに行くことにした。ここに居るとダメになっちゃいそうでさ……」すると、思いがけない返答が返ってきた。「何!? 足立もか!! 実は俺も住み込みの仕事探してるとこだぞ。そうか、お前も同じこと考えてたか!」ヒロマサ先輩もまた、この生活から抜け出そうと決意していたのだった。それから、僕たちは職探しの情報交換を始めた。「おい、碍子屋で給料が良くて住み込みのとこがあったぞ」 「先輩、岐阜県の各務原で、1日8千円で大工の住み込みはどうです?」探しているうちに、僕はふと思った。これまで毎日溜まり場で同じような会話を繰り返していた時間が、ものすごくもったいなく感じられてきたのだ。一刻も早く、ここから抜け出したい──そんな焦燥にも近い感情が僕を動かしていた。数日後、ヒロマサ先輩が興奮気味に僕に言った。「おい足立、いいとこ見つけたぞ。建設会社の住み込みで給料も良いし、前借り制度もあるし、重機の免許も取らせてくれる。ちょうど2人募集してる。一緒に行こうぜ」僕は考えた。ヒロマサ先輩と一緒に行くことで、また流されてしまわないか……。でも、それは違った。ヒロマサ先輩もまた、先を見据えてこの環境から抜け出そうとしていた。同じ方向を見ている人と一緒なら、成長できると思った。そして僕は、共に行くことを決意した。
誰もいなくなった溜まり場
僕たちの一歩が、誰かの檻を壊した
あの頃の僕らの世界には、ただ“時間”だけがだらだらと流れていた。
昨日と同じ今日。今日と同じ明日。
変わらない場所に、変わらない顔ぶれ。ただそれだけで、どこか安心していた。だけどある日、僕らはそこからほんの一歩だけ踏み出した。
その一歩が、僕の中にあった“気づかぬ檻”を壊す始まりになるなんて、
あの時の僕は、まだ何も知らなかった。僕たちは、慣れ親しんだ地元を離れ、建設会社での住み込み生活を始めた。
現場は国道や橋、下水道の工事。重機が鳴り響き、土煙が舞う中、僕は助手として毎日動き回った。
「あれ持ってこい!」「これ片付けろ!」
言われた通りに走るだけの毎日だったけど──楽しかった。何もなかった場所に、ひとつずつ新しいものが立ち上がっていく。
その“創造の瞬間”に立ち会えることが、幼い頃から「何かを創ること」に惹かれていた僕には、
たまらない喜びだった。住み込み先は、建設会社の事務所の2階。
社長の奥さんはまるで母のように、朝昼晩の食事に加え、弁当まで用意してくれた。
あたたかく、やさしく、僕らを家族のように受け入れてくれたその場所は、
それまでの僕の“狭い世界”を、静かに、でも確実に塗り替えていった。その頃、かつて溜まり場だった地元には、少しずつ人が来なくなった。
一人、また一人と、あの場所を離れていったと聞いた。
カナモリ先輩も、いつの間にかトラック運転手になり、数年後には独立していた。もしかしたら──
僕たちが地元を出たその一歩が、誰かの心にも火を灯したのかもしれない。
人は、不安だから動けない。
でも、誰かが先に動く姿を見ることで、「自分にもできるかもしれない」と思えるようになる。あの頃の溜まり場には、たしかに“安心”があった。
誰かがいる。ただそれだけで、妙に心が安定した。
だけど同時に、僕らは少しずつ、何かを失っていたのかもしれない。
「変わらない」という心地よさの裏に、気づかぬうちに虚しさが積もっていった。でも──その虚しさは、ただの空白じゃない。
正しく燃やせば、エネルギーに変わる。
燃やす方向さえ間違えなければ、その火は、未来を照らす光になる。
変われない僕と、変わった先輩
サトシ先輩との再会
あのとき、俺は本気で信じていた。
「環境が変われば、人は変われる」──そう思っていた。
でも、現実はそんなに甘くなかった。地元を離れ、住み込みの現場で汗を流した日々。
あの時間が、人生のターニングポイントだったのは間違いない。
だけど、あのときの“変われた自分”は、本当の意味での変化じゃなかった。それは俺自身の意志や力じゃなくて、ただ流されていただけだったんだ。
環境の波に押されて、変わったように“見えていただけ”だった。1年半ほど経った頃、地元の彼女と付き合い始めた。
それをきっかけに、実家から現場に通うようになり、やがて会社も辞めた。
当時の俺は、「もう大丈夫」と思っていた。
けれど──すぐに気がついた。頑張れなくなっていた。実家での生活は、あまりにも快適すぎた。
母はもう俺に何も言わなくなっていた。
まるで、俺の顔色を伺うように、腫れ物に触れるような接し方だった。
それはきっと、あの頃の俺が母を無視し続けた“代償”だったのかもしれない。でも、その優しさは、俺の弱さを見逃し、甘やかしていった。
そしてまた、俺は流された。
環境が変わった瞬間に、俺の中の“変わったと思っていた自分”は簡単に崩れ落ちた。そんなとき、偶然、あのサトシ先輩に出くわした。
かつて、俺を敵視し、いつも威圧的だったあの人に。
心臓が跳ねた。足が震えた。
でも目の前にいた彼は、まるで別人のように穏やかだった。「ここで何してんの?」
優しい声だった。
「友達と待ち合わせです」と俺が答えると、
「呼んできてあげよっか?」と、柔らかな笑みを見せた。その後、人づてに何度も耳にした。
あのサトシ先輩は、すっかり変わって、まるで別人になっていたという話を。
何年にも渡って、彼の“良い噂”を聞き続けた。──あのサトシ先輩ですら、変われた。じゃあ、俺は?
一度は変わったように見えたけど、気づけばまた元に戻っていた俺は……?あの頃、変われたと思ったのは、ただ環境に引っ張られていただけだったのかもしれない。
それとも、俺自身が本当の意味で“変わる”ことを、どこかで拒んでいたのかもしれない。……いや、違う。きっと俺は、まだ“変わる理由”を見つけていなかっただけなんだ。
「楽な道」を選んだ代償
冷房の中で忘れた、汗と夢の重み
あの瞬間、僕は“楽な人生”に手を伸ばしてしまった。
ほんの軽い気持ちだった。
まさかその選択が、のちに心を削り、身体を蝕み、人生の軌道をねじ曲げる引き金になるなんて――あの時の僕には、想像すらできなかった。やがてまた、「このままじゃダメだ」と、何度目かの嫌気に突き動かされて、僕は地元の建設会社に就職した。
同級生の中では一番給料がよく、現場でも頼られるようになっていった。
「いずれは独立して、自分の会社を立ち上げたい」
そんなことを思うようになった。──けれど、それはただの“理想ごっこ”だった。その“薄っぺらさ”を容赦なく突きつけられる出来事が起きた。
2歳上で仲の良かったカキタニ君が、建設会社を辞めて運送会社に転職したのだ。
数ヶ月後、彼が僕の元を訪ねてきて、こう言った。「足立くんも来いよ。仕事は楽だし、給料も今よりいいぞ!」たった一言だった。
でも、その一言で、僕の決意はあっけなく崩れた。
あれほど「独立する」と息巻いていたはずの自分が、簡単に揺らいでしまった。――まただ。変われたと思っていた自分が、何も変わっていないことに気づいてしまった。
情けなさが込み上げてきた。思い出されたのは、真夏の地獄のような現場の記憶だった。
朝起きたら、鼻血で枕が真っ赤に染まっている。
炎天下で朦朧とする意識。昼休みに倒れて、救急車で病院に運ばれた日もあった。
まだ10代の身体には、あまりに過酷だった。そんな僕にとって、エアコンの効いたトラックの運転席は、天国のように思えた。
しかも、給料は今より良い。
魅力に感じてしまうのは、無理もなかった。僕はあっさりと「独立」の夢を手放し、カキタニ君の誘いに乗って運送業に転職した。
そして──その判断こそが、僕の人生を大きく動かす“最初の転機”となったのだった。トラックに乗り始めて、まず感じたのは衝撃だった。「これが仕事か!? 楽すぎるだろ……!」エアコンの効いた車内でラジオを聴きながら、歌を唄っている。
真夏の炎天下で、意識を飛ばしかけていたあの日々とは、まるで別世界だった。
しかも、手取りは30万円以上。
心の底から、何度も思った。「もっと早く、トラック運転手になっていればよかった」でも、もしかしたら、
あの地獄のような日々を経験していたからこそ、今のこの快適さに“幸せ”を感じられたのかもしれない。朝6時に仕事が始まり、午後3時には終わる。
荷物を運べば、工場のスタッフがフォークリフトで降ろしてくれる。
ほとんど力仕事がない。
これまで全身で耐え抜いてきた僕にとって、「運転するだけ」という現実は信じられないほど“楽”だった。「こんなに楽して、今まで以上の給料をもらってもいいのか……?」そんな罪悪感すら覚えた。やがて、僕はその運送会社を辞め、個人事業主として運送業を始める決断をした。だけどその選択が、のちに僕を──心も身体も──じわじわと蝕んでいくことになる。そう、この“楽さ”の裏には、想像もしていなかった代償が待っていたのだ。
8月が黒く染まった日
「快適な日々」の終わりに、地獄は口を開けていた
自営業で小さな運送会社を始めた僕は、それまでの収入の約3倍を稼ぐようになっていた。
企業と年俸制で直接契約を結び、その金額を12で割った額が、毎月きちんと口座に振り込まれる。
それは、誰にも頼らず自分の手でつかみ取った、誇れる安定だった。毎月50万円を貯金に回しても、手元には信じられないほどの金が残った。
僕は「毎日1万円使っていい」と決めて、必要のないものを買い、外食を重ね、金を消費することで、自分を満たそうとした。
それはまるで、過去の空白を、お金で埋めようとする行為だった。仕事内容も、これまで経験してきたどんな仕事よりも楽だった。
朝と昼に分かれて、合わせて1日5時間ほどの労働。体も心も、軽かった。
当時の僕は、心から思っていた。
「自営業にして、本当に良かった」と。──まさか、その選択の先に、人生を狂わすほどの深い闇が潜んでいるとは、夢にも思わずに。
満たされない心の声
仕事は午前8時から10時半までの“午前の部”、午後1時から3時半までの“午後の部”という二部制だった。
最初のうちは、「理想の働き方だ」とすら思っていた。けれど、その快適さが、いつしか僕の内側をじわじわと蝕み始めていた。
毎日同じ時間に、同じ作業を、同じようにこなすだけ。
誰からも必要とされていないような感覚。
仕事を終えても、達成感も充実感もない。そこにあったのは、目的も意味もない、ただ過ぎていくだけの時間だった。「面白くない」
「やりがいがない」
「つまらない」そんな言葉が、気づかぬうちに、僕の心に根を張り始めていた。お金は順調に増えていく。
なのに、心はその逆を進んでいた。
不自由は何もないのに、どこにも「楽しい」という感覚がなかった。──気づけば、僕は少しずつ、でも確実に病んでいっていた。心の奥に、ずっとくすぶっていた“何か”があった。
それは、何年も前から、ゆっくりと気配を濃くしていた、言葉にならない重たい影のようなものだった。
気づいていながら、見ないふり
その“何か”が、心のほとんどを覆い尽くすようになっても、僕は見て見ぬふりをしていた。
快適な生活、潤う貯金、短い労働時間。
「これでいいじゃないか」
「これ以上、何を望むというんだ」
そう自分に言い聞かせながら、心の声に耳を塞いでいた。
だけど、あの真夏の昼下がり――
それは、何の前触れもなく襲ってきた。
“普通の午後”に起きた異変
午前10時半、いつものように仕事を終えた僕は、近所の喫茶店でランチを済ませ、アイスコーヒーをゆっくり飲んでいた。
その後、一度家に戻り、午後の部に向けて12時55分に家を出た。その日、例の「くすぶる何か」は、いつにも増して重くのしかかっていた。
今思えば、あれが前兆だったのだと思う。トラックを走らせ、積み込み先の会社がある交差点へと近づいた時、
左にハンドルを切ろうとした、まさにその瞬間だった。電撃のような不安感が、首筋から背中を走り抜けた。
次の瞬間、目の前が真っ暗になった。地面が抜け落ちるような感覚。
真夏の車内に突然寒気が立ち込め、心拍数が跳ね上がった。
激しい震えが全身を襲う。
ハンドルを握る手が震え、前の車に突っ込みそうになり、慌ててブレーキを踏んだ。
だけど、そのブレーキの感覚すら曖昧だった。
まるで、浮かんだままの車を操っているような不確かさ。「なんだこれは……!?」身体がいうことをきかない。
冷や汗が滝のように流れ落ち、動悸、めまい、視界の消失が一気に襲ってくる。「死ぬ……!」
本気でそう思った。けれど、奇跡的に会社の近くだった。
僕はなんとかトラックを駐車場に滑り込ませ、転がるようにして外に飛び出した。全身汗でびっしょりなのに、体は震え、寒さでこわばっていた。
目の前は真っ暗なままで、地面がぐらぐらと揺れているように感じた。やがて、ゆっくりと視界が戻ってきた。
真夏の太陽が、まるで何事もなかったかのように、ギラギラと照りつけていた。
それは、僕の異変をあざ笑うようでもあった。これが、僕が成人してから初めて経験した「パニック発作」だった。
出口の見えないトンネルへ
でも、これはほんの序章に過ぎなかった。この瞬間から、僕は「出口の見えない地獄のトンネル」へと入り込んだのだった。ここから始まる3年半――
僕の人生で、最も辛く、最も暗く、最も必死にもがき続けた日々が幕を開ける。この地獄が、やがて人生を大きく好転させるきっかけになるなど、
あのときの僕には、想像すらできなかった。
思い出せない地雷が、音もなく爆発した
声にならなかった叫びが、今も響いていた
あの日の午後、何の前触れもなく、それは僕を襲った。
突然、心臓が異常な速度で脈打ち始め、視界の端から世界がゆっくりと閉じていく。自分の体に、何かとてつもない異変が起きている──そう理解したときには、すでに思考が追いつかず、脳内をぐるぐると回り続けていた。「……このまま死ぬんじゃないか?」そんな考えが、本気で浮かんだ。あの感覚には、確かに覚えがあった。
幼い頃、夜中に突然目を覚ましたときに感じていた、名前のつけようのない恐怖。姿も正体もない“何か”に追われているような、不気味な気配と胸のざわめき。
あの夜の震えと、まったく同じだった。初めての発作の直後、僕は午後の仕事を休んだ。
震える手でハンドルを握り、なんとか自宅まで帰り着いた。
部屋に閉じこもり、ただ呆然としながら繰り返していた。「……何が起きたんだ?」だが、信じられないくらい早く、落ち着きが戻ってきた。
あれほど激しかった不安と恐怖が、嘘のように消えたのだ。
不思議なほど冷静な感覚に包まれて、「もう大丈夫だ」とすら思えた。
光の中に走る黒い稲妻
「午後から出勤しよう」
そう思い、玄関に向かった。――その瞬間だった。再び、容赦なく発作が襲いかかってきた。ドアノブに触れた手がビリビリと痺れ、膝が崩れ落ちた。
しゃがみ込んだ目の前で、また視界が外から真っ暗に閉じていく。鼓動が、ひとつひとつ重く深く、胸の内側に響く。
まるで、自分の中から“生”そのものがじわじわと抜け落ちていくような感覚だった。真夏のはずなのに、なぜか身体が震え始めた。
凍えるような寒気。止まらない手の震え。
喉の奥では、声にならない叫びがぐるぐると渦巻いていた。逃げたい──。
どこでもいい、この場所から、とにかく逃げ出したい。
心の奥から、必死の叫びがこみ上げてくる。
でも、身体は動かない。その場に取り残された僕を包んでいたのは、“死ぬかもしれない”という、圧倒的で底なしの恐怖だった。幼少期のあの恐怖とは比べものにならない。
それは、はっきりと「命の危機」だった。10分ほどで発作は収まった。
けれど僕の中には、はっきりとした確信が残った。──このままでは、生きていけない。
記憶の底に沈んでいた“何か”へ向かって
「これは、なんなんだ……?」正体の見えない発作。
原因もわからない。病気なのか?精神的なものなのか?
もしくは、もっと別の……何か?答えの見えない問いの中で、僕は自分の“過去”に目を向けざるを得なかった。
あの頃の僕は、確かに“何か”を経験していたはずだ。
言葉にできず、記憶の奥に沈んでしまった、衝撃的な出来事。
自覚はしていなかった。でも、それはずっと、心のどこかに居座っていたのかもしれない。そういえば──
子どもの頃から、似たような症状はあった。
でも、今回のそれは、次元が違っていた。
桁違いの強さと恐怖だった。「思い出せないトラウマがある」僕はそう結論づけた。ずっと忘れていた“地雷”が、ある日突然、音もなく爆発したのだ。記憶は、生きている。
意識の中では忘れていたとしても、過去の出来事は、魂のどこかでずっと脈打っていた。
まさかそれが、現在の僕をここまで揺さぶってくるなんて。……思ってもいなかった。
母が過去を隠した夜
乗り越える準備ができるまで、恐怖は何度でも来る
母がパートの仕事から帰宅したのは、夕方遅く。
玄関の扉が閉まる音を聞いた瞬間、僕はまるで反射のように飛び出していった。
逃げるように、でも縋るように──詰め寄った。「俺の過去に、何か発作とか、トラウマになりそうな出来事ってなかった? 隠さずに教えてくれ!」声は震えていた。自分でもわかるほど、切羽詰まった声だった。
母は突然の尋問のような僕の剣幕に、目を丸くして驚いた。「な、何でそんなことを聞くの……?」「いいから! 頼むから、早く教えて!」その時の僕の顔は、おそらく鬼気迫るものがあったのだろう。
母は片手をあごに当てて、黙り込んだ。
まるで、買い物帰りの主婦がスーパーの値引き棚の前で考え込むような、そんな日常的で無防備なポーズだった。「う〜ん……思い当たることは、何もないよ……何かあったかなぁ……」曖昧な答えだった。
僕は信じられなかった。いや──信じたくなかった。「嘘つくなよ。本当に、何もないのか? 本当に……?」再び沈黙が流れた。母は表情を消し、ゆっくりと言った。
母の沈黙が、僕を孤独にした瞬間
「……何もないと思う」胸の奥で、ギシッと音がしたような気がした。
信じたかった。でも、信じられなかった。――なぜだ。
なぜ、あの夜中に起きた、あの小学一年の時の恐怖を覚えていない?
どうして、語ろうとしない?
本当に忘れてしまったのか? それとも……何かを隠しているのか?時間だけが、空虚に過ぎていった。
夜10時を過ぎた頃、父が帰宅した。「もうこんな時間か……」僕は迷った。けれど、言わざるを得なかった。
実家で暮らしている以上、黙っているわけにはいかない。
“それ”が、いつまた襲ってくるか分からない以上、親にだけは伝えておかなければならなかった。僕は、昼間に起きた“あの発作”のことを、父にも打ち明けた。母はその話を聞いても、なお「何もない」と言い張っていた。
けれど──
のちに、母が死の間際に語った、あるひと言によって、僕は知ることになる。
母は、“思い当たる何か”を、やはり心の奥に持っていた。
ずっと、僕にだけは黙っていたのだ。その時、父も腕を組み、目を伏せて何かを必死に思い出そうとしていた。
そして──あの発作が、またやってきた。最初の前兆は、震えだった。
体が、ガクガクと音を立てるように震え始めた。「寒いの?」母が僕に問いかけた。
その一言を聞いた瞬間、僕は静かに絶望した。――今日は、真夏の8月。
湿気にまとわりつかれるような、重苦しい熱帯夜だ。寒いわけが、ない。次の瞬間だった。
あの“嫌な感覚”が、容赦なく僕を、現実という地面から引き剥がしていった。
闇に引きずり込まれるような感覚。
世界の光が、音もなく、スッと消えていった。「……また来た」僕は短く、そう告げた。
母は明らかに動揺していた。
肩で息をしながら、立ち上がり、僕を見つめることしかできなかった。父も顔を曇らせたまま、低く問いかけてきた。「……何をしたらいい?」僕は歯を食いしばり、体を震わせながら、必死に声を絞り出した。「……何もしなくていい」それが、精一杯だった。「何もしないでいいんだな?」父はもう一度、確認するように言った。
僕は、うなずいた。2人は、黙って、僕を見守った。立て膝をついた僕は、その日3度目の発作に耐えるしかなかった。
それは、しげちゃんが死んだあとに現れた“あの症状”と、あまりに似ていた。そして僕は、静かに確信した。──あぁ、きっと俺は、死ぬんだ。
それでも、原因を探す旅は始まっていた
歯が擦れ合う音だけが、ギシギシと頭の中で反響していた。
息は浅く、視界は狭く、世界の温度がどんどん下がっていく。それでも、僕は原因を見つけることができなかった。
この恐怖が、どこから来たのか。
なぜ、今、こうして僕を襲ってくるのか。だけど今なら、ほんの少しだけわかる気がする。人生に起こるすべての出来事は、
その人が“乗り越える準備が整ったときにだけ”現れる。あの時の僕は、きっとまだ、
その準備が整っていなかったのだろう。
地獄の扉を、自分で開けた日
“助け”と“依存”の境界線で、僕は迷った
最初の発作のあと、僕は午後の仕事を休み、ぐったりとした身体を引きずって帰宅した。
「もう、大丈夫だろう」
そう自分に言い聞かせながら、玄関に向かったその瞬間だった。全身を電流のような恐怖が貫き、視界の端から世界が閉じていく。
骨の芯まで凍りつくような寒気。止まらない手の震え。胸を内側からかきむしるような激しい動悸。逃げたくても身体が動かない。自分の意思など一切通用せず、体も心もすべてが“見えない恐怖”に支配された。
僕はただ、玄関先で立ち尽くすことしかできなかった。眠れぬまま朝を迎えた。
「このまま、自分という存在が壊れてしまうんじゃないか」
そんな得体の知れない恐怖を胸に押し込め、震える手で総合病院の精神科へと向かった。ただ車に乗っているだけなのに、心臓は暴れ馬のように跳ねる。
赤信号に止まるたび、不安が身体の奥底からせり上がってくる。
寒気と熱気が同時に体を襲い、もう自分の中で何が起きているのか、理解できなくなっていた。病院に着き、精神科の扉の前に立ったとき、心の中で誰かが小さく呟いた。
「……まさか、自分がこの扉をくぐる日が来るなんて」呆然としながら入った待合室には、
僕が想像していた“心を病んだ人たち”とはまるで違う人たちが座っていた。
普通の服装。普通の顔つき。普通の時間を過ごしているような、そんな人たちだった。その光景を見た瞬間、僕の中に根強く残っていた「精神科=異常者」という偏見に気づいた。
そして、恥ずかしさが一気にこみ上げてきた。診察室へ通され、僕は昨夜の出来事を、声を震わせながら必死に語った。
すると医師は、穏やかな表情のまま静かに告げた。「不安神経症ですね。最近では“パニック障害”とも呼ばれています」その言葉を聞いて、命に関わる病気ではないとわかった瞬間、ほんのわずかに安堵がこぼれた。
けれど同時に、すぐにこう尋ねていた。「……治るんでしょうか?」医師は僕の目をまっすぐ見つめ、優しく答えた。
「薬だけでなく、考え方を変えることも必要です」――あのときの僕は、とにかく「この苦しみから早く解放されたい」
それしか考えられなかった。本当は、病院に行くことすら強烈な抵抗があった。
なぜなら僕は、幼い頃から母にこう言われて育ってきたからだ。
「病院に行くような子は、死んじゃう病気なんだよ」その言葉が、まるで呪いのように心に染みついていた。
大人になった今でも、“病院=死を告げられる場所”としてインプットされたままだった。どんなに軽い病気でも、「病院に行けば、きっと“死”と診断される」
頭の中では、そんな恐怖だけが暴走していた。
僕にとって、病院はまさに“地獄の門”だった。でも、このときだけは違った。
「このままじゃ、本当に死ぬかもしれない」
そんな極限の不安が、僕の背中を無理やり押していた。だからこそ、診察が終わったあと、僕の頭の中にはただ一つの願いしかなかった。
「薬を、今すぐ飲んで、少しでもこの地獄から逃れたい」
薬がくれる安堵と、奪われる自由
当時はまだ薬局ではなく、病院の窓口で薬がそのまま渡される時代。
受付で薬の入った小さな袋を受け取ったとき、心の奥で、別の恐怖がふつふつと沸き上がっていた。――薬を飲めば、きっと楽になれる。
でも同時に、薬がないと生きられない体になるのかもしれない。つまり、薬に依存する人生の始まり。
そして、あの母の声が蘇る。「ほらね、やっぱり“弱い人間”だったじゃない」僕は迷った。
けれど、そのとき心のどこかで、こう決めてしまっていた。「……自分の力で治す。薬には頼らない」そう心に誓いながら、処方されたばかりの薬の袋を、そっと病院のゴミ箱に投げ入れた。その行為が何を意味するのか、当時の僕は深く理解していなかった。
ただ、それが“自分を信じる”ことのように思えたのだ。けれど──
あの一瞬が、僕自身の手で“地獄の扉”を開いた瞬間だった。そして僕は、その先に広がる果てしない闇を、まだ何も知らなかった。
離れていった友達
「嫌われたくない」という檻に、自分を閉じ込めた
「クスリで治すなんて、それは逃げだ。」当時の僕は、そう信じて疑わなかった。
だから、パニック障害と診断されても、僕は“薬を使わずに治す”という選択をした。
根本原因を突き止めさえすれば、自力で回復できるはずだ。
そのたったひとつの希望だけを頼りに、僕は処方された薬を手放した。けれど、それは想像していたよりも、はるかに過酷で、孤独な闘いだった。「自分の判断は正しい」と、何度も自分に言い聞かせた。
でも——実際に、何をどうすれば“正解”なのかが分からない。
ただ闇雲に耐えるしかない。そんな日々が続いた。最初の発作を起こしたのは、トラックの中だった。
それ以来、「車内」という空間が恐怖の対象に変わってしまった。
密閉された空間、冷房の匂い、シートの質感さえも、すべてが“あの恐怖”の再現スイッチになった。地下鉄。エレベーター。カラオケボックス。
以前の僕なら、何のためらいもなく入れていた場所。
それらすべてが、突然“猛獣の檻”のように思えた。けれど——
本当に怖かったのは、発作そのものじゃなかった。「人に見られること」だった。誰かの前で取り乱し、過呼吸になり、うろたえる自分。
その姿を想像するだけで、血の気がスッと引いた。
26歳のあの頃の僕は、まだ“かっこいい自分”でいようとしていた。
崩れかけのプライドが、最後の心の防壁だった。だから、誰とも会えなくなった。かつては、毎週末に仲間たちと海へ行き、サーフィンをした。
冬にはスノーボードを担いで雪山へ。
朝から晩まで笑い合い、ふざけ合い、バカみたいに夢中になっていた。
そんな日々が、ある夜を境に、すべて遠ざかっていった。それでも、毎日のように友達から誘いは届いていた。
僕はそれに、罪悪感を押し殺しながら、こう返した。「ごめん、今日は用事があるから行けないんだ。」
言えなかった本音が、僕を壊していった
本当は、心の底から叫びたかった。「俺、パニック障害って病気になったんだ。
発作が怖くて、外に出られないだけなんだ。
お前のことが嫌いになったわけじゃないんだよ。」でも、それは言えなかった。
それを言えないことこそが、発作よりもずっと、僕を苦しめていた。やがて、1人。また1人と。
誘ってくれる友達の数は減っていった。そして、とうとう誰も来なくなった。あとで数えてみたら——
僕が失った友達は、30人を超えていた。誰もいない静けさの中で、ようやく僕は泣いた。
泣きながら、同時にどこかホッとしている自分がいた。
これでもう、誰にも迷惑をかけずに済む。
誰の前でも取り乱さなくて済む。そう自分に言い聞かせた。
でも、それはただの言い訳だった。僕は、迷惑をかけたくなかったんじゃない。
嫌われるのが怖かっただけだった。
誰かに頼ることが、怖かっただけだった。
自分の“弱さ”を、見せるのが怖かっただけだった。そうして僕は、自分で、自分を檻の中に閉じ込めていった。
誰にも壊されることのない、自分だけの牢獄。
その中で、僕の心は音もなく、少しずつ崩れていった。やがて僕は、人と目を合わせることすらできなくなった。対人恐怖症。それは、「孤独」という名の副作用だった。
「明日、死のう」と決めた夜に見た光
闇の中にしか、見つからない宝物がある
精神科で処方された薬をすべて捨てた瞬間から、僕の心は、地図も方角もない荒野に放り出されたようだった。逃げ道のない空間で、ただ身ひとつで立ち尽くすしかない。パニック発作は容赦なく日に何度も襲いかかり、ただ息を吸うだけで胸が潰れそうになった。背後からずっと張り付いてくる予期不安の影に、心も体も、一瞬たりとも安らげる時間がなかった。過緊張で体は常に硬直し、いくら眠っても疲労は取れない。骨ばった身体が鏡に映るたび、10キロ以上も落ちた体重が、僕の内側がどれほど蝕まれていたかを物語っていた。頬はこけ、肩の骨が浮き上がり、肌の感覚さえ鈍っていた。世界全体が、僕に敵意を向けているような錯覚に陥っていた。僕は、夜が来ることを恐れていた。眠ることは、もはや「休息」ではなく「地獄への入り口」になっていた。仮に浅い眠りに落ちたとしても、その先に待ち構えているのは決まって悪夢だった。高層ビルの屋上に片手でぶら下がり、ビルごと傾いて都市の光の中に吸い込まれていく夢。池の縁を月明かりだけを頼りに歩き、泥沼に膝まで沈んで足を抜こうとした先に、無数の墓が現れた夜。あるいは、暴走する車が突進してくる光景。思い出すことさえ拒みたくなる恐怖が、毎晩僕を飲み込んでいった。「わぁぁぁーーっ!」という自分の叫び声で、汗びっしょりで目を覚ますこともあった。そのうち、僕は夜の訪れを心の中で否定するようになっていった。「もう、眠りたくない」と。夜という概念ごと忘れたくて、朝までファミコンをやり続けた。音と光に意識を向け、暗闇の存在を塗りつぶすように。しかし、睡眠不足は確実に心の芯まで蝕んでいく。「なんで、こんな苦しい人生になったんだ?」「こんな自分は、もういやだ」——そんな言葉が、ひっきりなしに心の表面に浮かび上がってくる。「嫌だ嫌だ嫌だ!」という否定の渦に、僕は自分を突き落とし続けた。発作への恐怖、治る見通しのない焦り、未来のすべてを閉ざす絶望、自信の欠片も見つけられない自分への深い嫌悪。それらの感情がぐるぐると回転しながら混ざり合い、ついに僕は、感情をコントロールできなくなった。ファミコンの操作がうまくいかなかっただけで、怒りが爆発した。ソフトを引き抜き、テレビに叩きつけた。画面に亀裂が走り、それがまるで自分の心の割れ目のように感じられた。そして、ある日。
すべてが耐えられなくなった。張り詰めていた糸が、静かに、しかし確かに、音もなく切れた。「今日だけは、ゆっくり寝てみたい。そして、明日、死のう。」そう心に決めたその夜。
奇妙なことに、いつもは寝つけなかった僕が、その夜に限って、深く、深く、眠りに落ちた。翌朝。
まぶたを通して差し込んだ太陽の光が、久しぶりに僕の体の奥にまで染み込んできた。何年も忘れていたような、澄みきった気分に包まれていた。「あれ?あんなに苦しかったのに、こんなにも清々しい朝があるんだ。」その瞬間、ひとつの考えがふっと浮かんだ。——死を恐れているとき、死の恐怖はどんどん膨らむ。でも、死を覚悟したら、その恐怖は消えていくんじゃないか?その小さな気づきは、のちの人生のあらゆる場面で、何度も僕を救ってくれる“光”になった。この朝、僕は確かに決意を変えたのだ。「死のう」から、「生まれ変わろう」へと。振り返れば、あの頃の僕は真っ暗闇の世界に、一人きりで取り残されていた。
泥沼に膝まで沈み、たった一歩を踏み出すことさえ、信じられないほどの苦痛と恐怖を伴った。光など、どこにも見えなかった。けれど、僕はその闇の中で、這いずりながら、ある“もの”を見つけたのだ。それは、キラリとわずかに光る、小さな宝物だった。明るい場所にある宝物は、誰もが簡単に見つけられる。けれど、本当に大切なものは、暗闇の中に、誰にも気づかれずに埋まっている。その宝物は、目ではなく、“心の手”でしか見つけられないのだ。
ノート4冊分の過去が、僕を再構築し始めた
僕は「なるべくして、なった」──ならば、積み直せるはずだ
僕は、本屋を巡り続けていた。どこかに、自分と同じようにパニック障害を乗り越えた人がいて、その体験を残していてくれていないかと願いながら。けれど、どんなに大きな書店に足を運んでも、棚にはそのような本は一冊もなかった。パニック障害という言葉自体が、まだ社会に知られていない時代だった。僕は思った。――だったら、自分がその一冊目を作ろう。「絶対に克服して、誰かの光になる体験記を書く。」その決意が、心の底から湧き上がった。その日から、僕は過去を掘り起こす旅に出た。物心ついたころから、発作に至る直前までを、ひとつずつ。ネガティブな記憶を時系列で思い出し、大学ノートに書き連ねていった。過去の出来事、そこで感じた感情、そこで生まれた思考。その全てを細かく並べながら、自分の中にある「何か」を見つけ出そうとしていた。だがこれは、想像を遥かに超える過酷な作業だった。外にも出られず、誰にも会えず、たった一人で、自分の心の闇に毎日向き合い続ける。忘れていた記憶の扉を無理にこじ開け、そこから噴き出す感情を浴びる。それをノートに書きながら、僕は何度も何度も、深く沈んでいった。4冊分になったノートには、僕の黒い歴史が、ありのまま刻まれていた。そのノートを何度も読み返しているうちに、ある「構造」が見えてきた。出来事が感情を呼び起こし、感情が思考を作り、思考が行動を選ばせる。そしてその行動がまた、新しい出来事を生む。たとえば――
「母に叱られ、強く叩かれた」という出来事。
そこから、「母が怖い」という感情が湧き、
「自分は母から嫌われている存在だ」という思考が生まれる。
やがて、「母の機嫌を損ねてはいけない」というルールに変わり、
いつしか僕は、母だけでなく他人全員の顔色を伺うようになっていた。そうやって、ひとつの出来事が、その後の人格の形成にまで影響を及ぼしていく。その連鎖は、子どもの頃から静かに、けれど確実に進んでいた。つまり、僕の思考も、行動も、すべてが「パニック障害になりやすい土壌」で育っていたのだ。これが原因だ、という決定的な一因などなかった。むしろ、「そうならざるを得なかった人生」があった。僕の発作の引き金は、自分で見つけることができた。でも、もっと大きな真実は、「それまでの人生全体が、すでに爆発へと向かっていた」という事実だった。僕は、成るべくして成った。パニック障害は、突然空から降ってきたわけじゃない。長い年月をかけて、僕の中に、静かに積み重なっていったものだった。そのことに気づいた瞬間、僕は震えた。でも同時に、確信した。「ならば、壊れた人生もまた、積み重ね直せるはずだ。」だから僕は、今もこうして書き続けている。自分自身を深く知ること。
それは、誰よりも自分を救うための行為であり、
同時に、見えなかった他者の心の構造にも光を当てるものだった。
母という名の檻。愛を知らずに育った僕が憎しみの奥で再開した虐待の記憶
“説明のつかない憎しみ”の正体を、僕はずっと知らなかった
僕は、物心ついたときから、母のことが心の底から嫌いだった。単なる「反抗期」では説明がつかないほど、その感情は異常なほど強く、13歳のとき、ついに心の奥に押し込めていた何かが爆発した。僕の中で、母という存在に対する怒りが臨界点を超えたのだ。当時の周囲は、それを“思春期の反抗”と軽く捉えていたし、僕自身もどこかでそう思い込もうとしていた。けれど、本当は違っていた。【拒絶と復讐】
僕は、家では母に対して暴言しか吐かなくなっていた。何かにつけて干渉してくる母の存在が鬱陶しくてたまらず、ある日、怒りに任せて母の足を思いきり蹴飛ばした。
母のふくらはぎは内出血で真っ黒になり、数日間はまともに歩けなくなった。それでも、僕の心はまったく痛まなかった。やがて、暴言さえやめて、僕は母を「完全に無視する」ことで、自分の存在を母から切り離すようになった。
母が何を話しかけてきても、一切返事をしなかった。うなずきさえもしなかった。「無視されることが、母にとって一番こたえる」と思ったからだ。
それは、僕なりの“復讐”だった。母は日に日にやつれ、10キロ以上も痩せた。そしてある日、「お母さん…気が変になりそう」と、僕の前で泣き崩れた。
でも、僕は何も感じなかった。ただ冷たく、その姿を見ていた。なぜここまで母が憎くてたまらなかったのか、その理由を、僕は長い間、理解できずにいた。【過去との再会】
だけど、26歳のとき——
僕はパニック障害を発症した。息が詰まるような発作の中で、「この症状の原因は、いったいどこから来たのだろう?」と、自分の過去を掘り返しはじめた。大学ノートを1冊取り出し、記憶の奥に沈めていた出来事を、1つ1つ時系列で書き出していった。
書いても書いても終わらなかった。2冊目を買いに行き、3冊目を開き、それでも足りず、4冊目までがすべて、黒く淀んだ“記憶の断片”で埋め尽くされた。そして気づいた。
それらの大半が、ずっと心の奥底に沈めてきた、母から受けた“虐待の記憶”だった。
授業参観と“母の恐怖”の始まり
母の前で間違えるのが、何より怖かった
4冊のノートには、母の怒りと理不尽に塗りつぶされた日々が、ぎっしりと詰まっていた。小学校1年生のある土曜日——その日は授業参観の日だった。教室に母が来ると聞かされたときから、僕の心は重く沈んでいた。みんなが親に来てほしくて浮き足立っている中で、僕だけは憂うつな気持ちで席に座っていた。授業は国語だった。先生は、全員が手を挙げられるようにと、あえて簡単な問題を出した。僕にも、その答えはすぐに分かった。
でも——僕だけが手を挙げなかった。間違えるのが怖かったんじゃない。
「母の前で間違えること」が、どうしようもなく怖かったのだ。もし答えを間違えたら、その場では何も起きなくても、家に帰った後、母の怒りが僕を待っている。それが想像できてしまって、手が上げられなかった。僕にとって、すでに母は「絶対に怒らせてはいけない存在」だった。
たとえ何もしていなくても、母の機嫌ひとつで罰が下される。そんな恐怖の中で、僕は日々を過ごしていたのだ。授業が終われば、そのまま親子で下校するという決まりだった。
でも、母は僕を置いて、ひとりで帰ってしまっていた。その時点で僕は、母が怒っていることを本能的に理解していた。不安と恐怖で足がすくみながら、ひとりで家に帰った。
玄関のドアを開けて、いつも通り「ただいま」と声をかける。だが、返事はなかった。靴を脱ぎながら、ふと視線を上げると、化粧台の前で足を組み、化粧を落としている母の姿が見えた。
その横顔には、表情らしい表情がなかった。けれど、僕は知っていた。この静けさが、嵐の前触れだということを。母の怒りに気づいていないフリをして、なるべく静かに動いた。こういうときは、息を潜めるしかない。何もなかったようにふるまうしかない。それが、僕の“生き延びる術”だった。すると母は、鏡を見たまま僕に背を向けたまま、顔も見ずにこう言った。「ここに正座しなさい」アゴで指し示されたのは、化粧台の前。いつも通りの、恐怖の儀式の始まりだった。僕は音を立てないように、板の間に正座した。冷たい床が足に食い込む。すでに心臓はバクバク鳴っていた。「なんであんな簡単な問題が分からないの!」
「みんな手を挙げてたのに、お母さん、恥ずかしくて穴があったら入りたかったわ!」母は、急に振り向いて、椅子に座ったまま僕の頬を何度も往復ビンタした。
右、左、右、左。大きく振りかぶっては叩かれた。顔がジンジンと熱を帯び、口の中が切れて鉄の味が広がっていった。
舌に触れるたび、そこに生々しい痛みがあった。僕は何も言わなかった。言葉を発することさえ、許されていないのだ。これが、いつもの「儀式」だった。
理由はなんであれ、母の気に障ることがあれば、2時間の正座と往復ビンタ。
それが僕の日常だった。時には「外で反省してらっしゃい!」と怒鳴られ、家の外に立たされた。
ドアは閉められ、僕は外気にさらされながら、母の怒りが収まるのを何時間も待つしかなかった。
“正解”を叫び続けた、閉ざされた玄関の前で
ノートにネガティブな記憶を綴っていたある日、ふいに、ひとつの出来事が蘇った。あれは、たしか小学校の低学年の頃——
夕方、友達と遊んで帰ってくると、家の玄関の扉は閉まっていて、チャイムを鳴らしても、ノックしても、中からは何の反応もなかった。僕は、すぐに悟った。
「あ、母が怒っている」と。でも、なぜ怒っているのかが分からなかった。
今日、何か悪いことをしただろうか?何か母の機嫌を損ねたのだろうか?…何も思い当たらなかった。それでも、家に入れてもらえなかった。その場で立ち尽くしながら、母に聞こえるように、大声で謝るしかなかった。「ごめんなさい!!」それでも返事はない。やがて、僕は、「母が何に怒っているか」を自分で当てなければならないという、暗黙の“ルール”に従うようになった。「帰りが遅かったから?」「妹とケンカしたから?」「“行ってきます”の声が小さかったから?」間違った理由を、玄関ドアの新聞受けの小さな口から家の中に向かって叫んでも、答えは返ってこない。母は沈黙したまま、僕の“正解”を待っている。でも、その“正解”なんて、母の気分次第で変わる。存在しないこともある。
僕は、薄暗くなった玄関前で、寒さと孤独と恐怖に耐えながら、ひたすら謝り続けるしかなかった。何時間経ったのかもわからない。
と、ふいに声が聞こえた。「ひろしくん、どうしたの?」近所に住む同級生の女の子が、外に立たされている僕を見つけて声をかけてくれた。
僕は恥ずかしさと情けなさとで、いっぱいだった。でも彼女は、「一緒にあやまってあげる」と言って、僕に代わって玄関のドアを叩き、母に向かって「ごめんなさいって言ってるよ、中に入れてあげてください」と伝えてくれた。そのとき、ようやく、家の鍵が開いた。けれど——中に入れてもらえたからといって、終わったわけではなかった。待っていたのは、いつも通りの“儀式”だった。
化粧台の前に正座させられ、往復ビンタ。理由が分からなくても、泣きたくなくても、痛みが続いた。僕は、母の“雷”を避けるために生きているような子どもだった。毎日が、“地雷”を踏まないように歩くゲーム。
でも、その地雷の場所は毎日変わる。昨日はセーフだったことが、今日はアウトになる。ルールはいつも母の機嫌次第だった。そして、僕は、その理不尽な怒りの矛先を誰にもぶつけられず、無意識のうちに妹へと向けてしまった。妹を叩いたり、いじわるをしてしまう。すると、妹は泣いて母のもとに逃げる。
そうすると、今度は僕が呼び出されて、また往復ビンタを受ける。
まるで出口のないループだった。感情のやり場がなかった。泣くことも怒ることも、自分の気持ちを表すことすら許されなかった。
泣いたら怒られた。泣かなければ叩かれた。感情は罰の対象だった。
ある日、友達と外でドッジボールをして遊んでいたときのこと。夕暮れが近づく頃、妹が走ってきて言った。「お母さんが呼んでるよ」その言葉を聞いた瞬間、胸がズンと重くなった。
遊んでいたテンションの熱が一気に冷え、代わりに胃の奥がギュっとした。仕方なく家に戻ると、僕は無言のまま、いつもの場所——板の間の冷たい床に正座させられた。そして母は開口一番、怒鳴った。「お母さん、恥ずかしかったでしょ!」何のことだかわからなかった。けれど、説明も反論も許される空気ではなかった。
いつものように、椅子に座った母の手が、右、左と、僕の顔に往復ビンタを繰り返す。その理由は、「近所の人への態度が悪かったから」だったという。でも、誰に何をしてしまったのか、すらわからなかった。僕の中には悪意もなければ失礼な自覚もない。
怒られた理由が理不尽だとわかっていても、僕には抗議する権利などなかった。悔しくて、どうしようもなく泣きたかった。
でも、泣いてしまうと、さらに怒られるのは分かっていた。だから必死でこらえた。唇を噛みしめ、肩を震わせながら、目の奥に溜まる涙を押し戻す。…でも、ある瞬間、どうしてもこらえきれなかった。一滴、涙がこぼれた瞬間、母の怒号が飛ぶ。「泣くな!男でしょ!」怒りのこもった往復ビンタが、また何発も飛んでくる。
泣いてもダメ。泣かなくてもダメ。逃げ道など、どこにもなかった。母は、他人の目を極端に気にする人だった。「恥ずかしい」という感情が、彼女の中ではすべてに勝っていた。いつしか僕は、「失敗=母の恥」という恐ろしい思い込みの中で生きるようになっていた。泣くことも、間違えることも、失敗することも、許されなかった。そうやって僕は、自分の感情や反応のすべてを“凍らせていく”ことを覚えていった。そしてそれは、やがて外の世界にも及ぶ。
怖かったのは、失敗じゃなく“注目”だった。
運動会の前日、僕は毎年、眠れなかった。小学校の頃、僕は運動が得意で学級対抗リレーの選手にも毎年選ばれていた。でも、嬉しさや誇らしさなんて、まるでなかった。ワクワクするどころか、ただ、ただ、怖かった。「母が観に来る」——
その事実が、僕にとってはプレッシャーでしかなかった。「転んだらどうしよう」「誰かに抜かれたらどうしよう」「母の期待を裏切ったらどうしよう」寝ようと目を閉じるたび、失敗した自分の姿と、それを見て冷たい目を向ける母の顔が浮かんだ。足が速いことなんてどうでもよかった。ただ、失敗しないこと。それだけが僕の目標になっていた。そして気づけば、僕は運動会だけじゃなく、あらゆる“挑戦”を恐れる子どもになっていた。失敗が怖い。
何かに取り組むこと自体が怖い。
人前で注目されることが怖い。
母の前でミスをすることは“罪”であり、その罰がいつ下るか分からない恐怖に常にさらされていた。特に人前で話すことが怖かった。僕は、いつしか母の顔色をうかがいながら、感情を殺して生きるようになっていた。楽しいはずの出来事も、心から笑えることも、全部、どこかに置き忘れてきたままだった。
僕の緊張は、“母の視線”の続きだった。
大学ノートに書き続けた記憶の破片は、まるでダムが決壊するようにあふれ出してきた。
そこには、ひとつ残らず僕の“恐怖の起点”が刻まれていた。ノートを埋め尽くしたのは、母の姿だった。
怒鳴る顔、睨む目、無言で指をさす仕草、そして何度も繰り返されたビンタの衝撃。
どのページにも、母の感情が支配する世界があった。僕は、体罰と暴言の中で育てられた。
叱責は指導ではなく、抑圧であり支配だった。それがどれだけ深く、僕の心に根を下ろしていたのか。
それは、26歳でパニック障害を発症して、はじめて気づかされた。人前に出ると心臓がバクバクと暴れ出し、息が詰まり、汗が止まらなくなる。
声を出そうとしても喉が締まり、体が凍ったように動かなくなる。そんな症状の正体は——
「母の前で萎縮していたあの頃の感覚」そのものだった。母の前では、間違えてはいけない。
気分を損ねてはいけない。
泣いてもダメ、笑ってもダメ、ただただ“完璧”でなければならない。その呪いは、いつの間にか僕の中で、「すべての人の前でも完璧であらねばならない」という“生きるルール”にすり替わっていた。そして、そのルールに縛られたまま、社会に出た。どんな場でもミスを恐れ、注目されることを怖れ、息をするように自分を責めつづけた。その結果が、パニック障害だった。この事実に気づいたとき、僕の中にある感情が、改めてくっきりと浮かび上がった。——「ああ、僕は母を、本当に心の底から憎んでいるんだ」と。普通なら、“親を憎む”という感情は、どこかで罪悪感が伴う。
けれど僕は、その感情を否定することができなかった。だって、僕の人生を“恐怖”という形に塗り替えたのは、紛れもなく母だったからだ。母の視線ひとつで震え上がり、母の怒りひとつで自分の価値を見失っていた幼い僕。
自分の感情を殺し、人に合わせ、顔色を読み、萎縮して生きる癖が、今も抜けない。なぜ僕の母に対する憎しみが、常軌を逸していたのか——その理由が、ようやく腹の底から理解できた。僕は、「愛されなかった」のではなく、「傷つけられつづけた」のだ。
しかも、逃げ場もなく、誰にも助けを求められない場所で。
「もう死んじゃおうかな」──その一言のあとを、僕は思い出せなかった。
僕には、もうひとつ——
ずっと心の奥に沈めてきた、重大な記憶がある。それは、ノートに過去を書き連ねていくうちに、ふいに蘇ってきた。たしか、小学校1年生か2年生の頃だった。
夜遅く、母の怒りのまなざしが僕に突き刺さった日。
その日も、理由は分からなかった。いつも通りの理不尽な怒りだった。けれどその時、僕の口から自然と出てきた言葉がある。「……もう、死んじゃおうかな」それは、泣きながら言ったわけでも、叫んだわけでもなかった。
ほんの少し、声に出してしまっただけの“本音のかけら”だった。その瞬間、母が動きを止めた。言葉を失い、一瞬だけ、顔から表情が消えた。
僕は、子どもながらにも分かった。母が戸惑い、動揺していることを。けれど——その先の記憶が、どうしても思い出せなかったのだ。母が何を言ったのか。
僕がどう返したのか。
その夜がどう終わったのか——何も思い出せない。ただ、その“空白”だけが、今でも僕の心の奥に沈んでいる。たったひとつ覚えているのは、
「僕はその頃、すでに限界だった」ということ。毎日が地雷原。
誰も味方のいない家庭という密室で、恐怖と孤独に支配されていた。
そしてその中で、自分が“生きている意味”を見失いかけていた。あの瞬間、僕の中で何かが壊れた。
それが、ずっと沈黙していた“もうひとつのトラウマ”だったのかもしれない。僕は今でも、あの空白の夜を、完全には思い出せない。
けれど、あのとき確かに、“限界のサイン”を母に向けて出していたのだと思う。
それを誰にも拾ってもらえず、大人になった今も、ずっと自分で握りしめたままだった。……もし、ここまで読んでくれたあなたが、かつての僕と同じように
「なぜかいつも、生きることが苦しい」と感じているなら、
あなたの中にも、ずっと拾われないままの“言葉にならない感情”が眠っているのかもしれない。そこで、そっと問いを置いてみたい。
❖ 静かな宿題(あなた自身への問いかけ)
あなたが今、「頑張らなきゃ」と思ってやっていることは、
本当に“今のあなた”が望んでいることだろうか?
それとも、あの頃の“傷ついた小さなあなた”が、
誰かに認められるために頑張っているのだろうか?
夜中の恐怖
「自分も死ぬのかな…」──はじめて感じた“死の恐怖”
あれは、しげちゃんが死んでしまってから、数日後のことだった。その夜、僕はふと目を覚ました。目を開けた瞬間、音も光も消えたような静寂の中で、僕は宇宙の果てにひとりだけ投げ出されたような感覚に襲われた。
誰もいない。誰の気配もしない。
世界のすべてから切り離されたような、そんな感覚だった。その孤独が、瞬く間に正体不明の恐怖へと変わり、次第にそれは「絶望」という重たい影に姿を変えた。──「僕もしげちゃんみたいに、死ぬのかな…?」ふと頭をよぎったその考えが、僕を奈落の底に突き落とした。寒くもないのに、体中がガクガクと震え出した。
膝を立ててうずくまり、太ももを両手で必死に握りしめる。
歯はカチカチと音を立て、止めようとしても止まらなかった。どうしようもなく、怖かった。そのとき、僕には「ひとつの希望」しか残されていなかった。
母のそばへ行けば、きっと安心できる。母の言葉を聞けば、怖さは和らぐはず——そう信じて、僕は母の枕元へと歩み寄った。「…怖い。お母さん、怖いよ…どうしよう……ねぇ……」体を小さく揺すりながら、何度も呼びかけた。
だけど、母はなかなか起きてくれなかった。
ようやく目を開けたかと思えば、僕の顔を見るなり言った。「怖い夢を見たんでしょ?早く寝なさい!」その瞬間、僕は世界から完全に拒絶されたような気持ちになった。こんなにも震えて、怯えて、助けを求めているのに——
母の言葉は、まるで氷のように冷たかった。そのまま、母の隣で立膝をついたまま、ひたすら震え続けた。
抱きしめられることも、言葉をかけられることもなかった。僕はただ、「なんでこんなに怖いんだろう」と、
歯を食いしばって、朝が来るのを待った。そして、朝方。
窓の外がわずかに明るくなりはじめたころ、ふいに震えはピタリと止んだ。
恐怖も消えていた。
まるで、最初から何もなかったかのように。「今のは、なんだったんだろう……?」だけど、それは終わりではなかった。
それから何度も、あの“死の予感”に襲われた。そのたびに、僕は母の枕元に立ち、何度も揺り起こした。
でも、返ってくるのは決まって——「早く寝なさい!」の一言。そのたびに、僕はまたひとつ、母に助けを求めてはいけないというルールを学習していった。そしてある日、僕は起こすことすらやめた。震えながら、真っ暗な部屋の中で母の寝顔を見つめ、
何も言わず、ただじっと、立膝をついて恐怖に耐えた。
“頼ってはいけない”という孤独の中で。安心を与えられた記憶は、ひとつもない。
誰にも頼れない小学一年生の僕は、毎晩、自分の震える体と心をひとりで抱えていた。そしてこの症状は、夜中だけでは終わらなかった。
昼間にも突然やってきた。
そしてそれは、大人になっても消えることはなかった。長いあいだ、僕を苦しめつづけてきたこの「死の恐怖」は、
しげちゃんの死をきっかけに、僕の中で目覚めてしまったものだった。
「あんた、死んじゃう病気だよ」
その一言が、僕の人生すべてを呪いに変えた
あれは幼稚園の頃。
今になって思えば、ただの風邪だったのかもしれない。
でも、当時の僕には、その小さな体調不良が“死の予兆”に感じられた。母は、いつものように不機嫌で、苛立ちを隠さず自転車の後ろに僕を乗せ、家から15分ほど離れた澤田医院へ向かっていた。道中、母は何度も僕にこう言った。「あんた、死んじゃう病気だよ」まるで呪文のように、繰り返し、繰り返し。それは怒りというより、怒鳴りながら吐き捨てるような言い方だった。僕の体調が悪くなると、母の機嫌は必ず悪くなった。
心配されるどころか、責められた。
まるで僕の体調不良が、母の機嫌を損ねる“罪”だったかのように。あれから少し時が経ち、小学1年生の土曜日。
あの日も僕は、風邪気味で学校を休んでいた。昼過ぎ、布団の中にいる僕を、同級生のヤマザキくんが「ドッジボールやろう!」と誘いに来た。母は言った。「学校を休んだんだから、行ったらダメ!」けれど僕は、ドッジボールがしたくてたまらなかった。
友達が見ている手前、強気になっていた僕は母の言葉を無視した。「行く行く!」玄関へ走ると、母が怒鳴った。「昼ごはん食べてから行きなさい!」仕方なく食卓へ戻る。昼ごはんは、うどんだった。急いで食べて「もういいや」と席を立とうとした僕に、背後からまた怒声が飛ぶ。「まだ残ってるでしょ!」僕は咄嗟に言った。「不味いから食べれない!」ヤマザキくんがそばにいることで、母もあまり強く出られないだろうと、心のどこかで思っていた。玄関のドアを開けた、その瞬間だった。「あんた、死んじゃう病気だから不味く感じるんだよ!」背後から泣きながら叫んだ母の声が、僕の全身を貫いた。僕は走って外へ飛び出し、ドアをバタンと閉めた。
けれど、母の泣き声が、あの言葉が、頭の中でずっと鳴り止まなかった。「やっぱり、僕は……本当に死ぬんだ」昼間なのに、視界の端から中央にかけてグワーッと暗くなっていく感覚。
頭の中が真っ白になり、全身が冷たくなり、猛烈な恐怖が心を支配していった。「死ぬ」「死ぬ」「死ぬ」——その思いが止まらなかった。後年、大学ノートに自分の記憶を綴っていたとき、僕はこの出来事を思い出した。そのとき気づいた。この記憶は、夜中に突然目覚め、震えながら母の枕元で怯えていたあの時期と重なっていたのだ。
断片的だった記憶が、ひとつに繋がった。
- 夜中の発作的な恐怖
- しげちゃんの死
- 「あんた死んじゃう病気だよ」という母の言葉
これらが結びついて、僕の中で“死への恐怖”という暗示が完成してしまったのだ。本来、最も安心できるはずの母という存在。
弱く、未熟で、誰かを頼らなければ生きられなかった僕にとって、
その母が発した「死ぬ」という言葉は、神の言葉のように絶対だった。だからこそ、潜在意識に強烈な恐怖として染み込んだ。「僕は死ぬんだ」何度も体調を崩したのは、ただ身体が弱かったからじゃない。
“死ぬ病気”という母の言葉の暗示が、僕の免疫すら奪っていたのだ。それは、風邪や発熱のたびに、“自分は死ぬんだ”と本気で怯えるという地獄だった。時が経ち、僕はこうも思うようになった。母は、当時22歳。
父は毎晩帰りが遅く、母は僕をひとりで育てていた。思い通りにならない赤ん坊。
泣き止まない日々。
疲れと孤独と苛立ちの中で、母の中で何かが壊れていったのかもしれない。「思い通りにならないなら、恐怖で支配すればいい」
それを、母は無意識のうちに学んでいったのかもしれない。もちろん、母はそんなつもりじゃなかったのかもしれない。
だけど結果的に、僕はその恐怖の中で育てられた。
- 「あんたには無理だ」
- 「ケガするよ」
- 「失敗したらどうするの」
- 「できるわけないでしょ」
そんな言葉ばかりを浴びせられ、“挑戦しよう”という気持ちは、育つ前に折られた。母の言葉が怖かった。
でも、母から離れるのも怖かった。否定され続けたのに、依存してしまっていた。
母がいなければ生きられないと思い込んでいた。母が、そう思わせることに成功していたのだ。けれど、僕は、ある日爆発した。
そして、精神的にも物理的にも、母から離れた。もし、あの時に離れなければ、今も僕は、母の中に閉じ込められていたかもしれない。トラウマのある人は、人生の中で「生きづらさ」に何度もぶつかる。
でも、こう思うんだ。この人生で、そのトラウマを克服することこそが、
自分に与えられた“本当の目的”なのかもしれない、と。
❖ 静かな問いかけ
あなたが今、無意識に避けていることや、どうしても踏み出せない一歩は、
かつて誰かの「言葉」が、心の奥でまだ響いているからかもしれません。それは、あなた自身の声でしょうか?
それとも、誰かの“声色をした呪い”でしょうか?
「殺したのは、僕だった。」
逃げ癖と仮面が育てた“見えない病”
僕がパニック障害になった原因は、決して一つの出来事ではなかった。
ノートに記憶や思考、感情の断片を吐き出していくうちに見えてきたのは、それが長年にわたって積み重ねられてきた“僕の生き方そのもの”だったという事実だ。母の支配のもとで育った僕は、心の奥にある“本当の自分”を封印してしまった。泣きたい気持ちも、甘えたい気持ちも、怒りすらも、「母に嫌われるかもしれない」という恐怖の前に沈黙させてきた。
その代わりに、僕は“好かれるための仮面”を身につけた。でも、それは自分を守るための術なんかじゃなかった。
それは、自分で自分を、ゆっくりと殺していく行為だった。「失敗=死」の刷り込み失敗すれば怒鳴られ、叩かれ、見捨てられる。
だから挑戦しない。だから無難に生きる。だから自分を偽る。
そうやって、僕の中には「失敗=死」という回路が刷り込まれていった。偽って生きれば生きるほど、本当の僕の声は失われ、
気づけば“生きているのに生きていない”という感覚が心を支配していた。この“空洞”のような感覚は、やがて“理由のない死の恐怖”へと姿を変え、
何の前触れもなく僕を襲うようになった。母からの虐待は、神経系そのものに“死の条件反射”を刻みつけた。
ちょっとした不調すら命に関わる危機だと錯覚させるほどに、
僕の身体は過剰に反応するように訓練されてしまっていた。発作の裏で発動する“母の声”初めてパニック発作が起きたあの日、
僕の自律神経は異常を訴え、身体は暴走を始めた。その瞬間、心の深くに埋め込まれていた「母の声」が、スイッチのように作動した。
——「あんたは死んじゃう病気なんだよ」それは、言葉というよりも“呪い”だった。
疑う余地もなく僕の中にインストールされていたその一言が、発作の引き金になった。もし、あの言葉を一度も聞いたことがなかったら。
もし、「死んでしまう病気」への恐怖がなかったなら。
僕はただ「体調が悪いな」と思って済ませられていたかもしれない。でも、僕にはそれができなかった。
逃げる癖と偽りの人生
僕の中には、「これは命に関わる」と瞬時に直結してしまう思考回路が組み込まれていた。
それは、薬ではどうにもならなかった。
根本にある“思考の歪み”を変えなければ、僕はこの恐怖から永遠に逃れられない。
そう確信した僕は、ある2つの誓いを立てた。
「逃げないこと」
「偽らないこと」この2つは、これまでの僕が最も避けてきたもの。
だからこそ、それが僕にとっての“挑戦”であり、必要な決意だった。何かを始めようとするたびに、僕は強烈な不安に襲われ、逃げていた。
その逃げ癖こそが、パニック発作を育てていたのだ。母から繰り返し浴びせられた
「あんたは臆病で弱い」
という言葉通りの人間に、自分を固定してしまっていた。でも気づいた。
“臆病だから逃げる”のではない。
“逃げる癖があるから臆病になる”んだ。
ありのままの自分へ
僕はまず「逃げない」と決めた。
どんなに怖くても、どんなに不安でも、
起きている症状から目を背けず、立ち尽くしてでも、その瞬間に向き合う。
そしてもう一つ——
僕はずっと、自分を偽って生きてきた。泣けば叱られ、
弱音を吐けば怒鳴られ、
甘えれば“罪”のように扱われた。そのたびに僕は本音を飲み込み、“強いフリ”を覚えた。
母に認められるために、本来の僕を、封印してきた。
そう。僕は、自分で“本当の僕”を殺したのだ。その殺人は、自分にしか見えない、静かで長い、心の犯行だった。偽らない生き方へ母との関係は、あとで“共依存”だったと分かった。
支配されることで必要とされ、
必要とされることで意思を奪われていた。偽ることで生き延びようとした僕は、
やがて自己肯定感を失い、心と体を壊していった。だから、決めた。
もう偽らない。
恥ずかしいことも、隠したいことも、
自分の口で語っていく。今こうして、この文章を書いていること自体が、
偽らないという“実践”だった。なぜそれが可能になったのか。
それは、更生施設での経験があったからだ。嘘を見抜かれる世界で、
本当の自分を出せたとき、
僕はイザワ君と心を通わせ、居場所を見つけることができた。だから、僕は信じている。「逃げないこと」
「偽らないこと」この2つを取り戻すことこそが、
殺してしまった“本当の僕”を蘇らせる、唯一の方法なんだと。
静かな宿題
あなたが“生き延びるために”偽ってきた自分。
それは、今のあなたにとって、本当に必要なものですか?
引き金になった悪女
掴みどころのない女
心が壊れるときって、もっと派手な音がすると思っていた。でも僕の心は、気づかぬうちに静かに殺されていた。“恋”の顔をした裏切りによって。パニック発作が起きるおよそ6ヶ月前まで、僕にはナオミという彼女がいた。
けれど、その関係は最初から、どこか掴みどころのないものだった。いつも彼女の態度は曖昧で、僕はその言葉や反応の裏を必死に読み解こうとしていた。だが、どうしても見えない。霧の中をさまよっているようだった。1年後、僕は真実を知る事になった。本命の男が、最初から彼女の中に存在していたという事実。今まで感じていた、言葉にできない不安や違和感の正体が、ようやく一つに繋がった瞬間だった。彼女は、その男から連絡があればそちらへ行き、会えないときだけ僕に「会いたい」と言ってきていた。僕との時間は、いわば“保険”のようなものだったのだろう。僕が会おうと誘うと、「仕事の都合がギリギリまでわからない」と言って予定を保留にし、結局いつも前日の深夜になって「明日、大丈夫になった」と、まるで投げやりな連絡をしてきた。僕は彼女のその態度に、ずっと違和感を覚えていた。ある日、明らかに様子のおかしい彼女を問い詰めた。
そしてついに、その男の存在が明らかになった。僕は、その場で彼女との関係を終わらせた。
だが――それで終わりではなかった。3ヶ月後、「彼と別れたから、よりを戻したい。自分勝手でごめんなさい」と彼女から連絡が来た。
そのとき初めて、僕は彼女が僕と出会った時点で「彼氏がいない」と嘘をついていたことを知った。彼女は、彼と会えない寂しさを紛らわせるために僕に近づき、再び彼と繋がれば、僕を切り捨てる。そんなふうに、僕を“空白の時間”の穴埋めとして利用していたのだ。それでも僕は、彼女が僕を「選んでくれた」という事実が嬉しかった。
24歳、若かった僕は、彼女をもう一度信じてしまった。復縁直後、彼女はまるで別人のように優しかった。
でも、それも束の間だった。また突然、素っ気ない態度に戻り、予定も合わなくなり始めた。僕の不安は再び膨らんでいった。問い詰めても、彼女は「気のせいだよ」「仕事があるから」と言い張る。僕は次第に、「やっぱり彼のことが忘れられないんだ」と思い始め、自信を失っていった。そして僕は、彼女が望むであろう“理想の男”を演じ始めたのだ。それは、初めてのことじゃなかった。母の前では「良い子」を、友達の前では「強い男」を演じてきた僕にとって、“誰かの期待に合わせて、別の自分を演じる”ことは、もはや呼吸のようなものだった。ただ、今回ばかりは…その仮面の内側から、自分の本当の顔が消えていった。そのうち、彼女がいないときでさえ“本来の自分”が分からなくなっていった。
精神的に消耗し、偽り続ける自分に嫌悪を覚えるようになった。結局、彼女は再びその男と付き合い始めたと、僕に告げた。
それで全ては終わった。
――だが、僕の中には深い傷だけが残った。プライドを引き裂かれ、心はずたずたになった。
大学ノートに綴ったネガティブな記憶を読み返すと、その頃から僕の精神はボロボロになっていたことがわかる。2度にわたって裏切られたことで、僕は人間不信に陥った。
友達や先輩たちも「僕の元を去るんじゃないか」と疑い、常に不安を抱えていた。その不安を誤魔化すために、僕は“誰からも嫌われない自分”を演じるようになったのだ。
結果として、誰にでも気に入られようと振る舞う“奇妙な自分”が出来上がっていった。仲の良かった先輩にすら、敬語で話すようになって気味悪がられた。
「俺って本当は、どうだったっけ?」――自分の輪郭が、ぼやけていった。日によってコロコロと態度を変える彼女に合わせていたうちに、僕はどんどん自信を失っていった。それまで普通にできていたことが、ある日突然、できなくなった。
人の目を見るのが怖くなり、声が詰まって言葉が出なくなった。
会話の中で相手の表情が曇るだけで、「嫌われた」と思い込んでしまう。だから僕は、誰とも話さなくなった。
話しかけられても、言葉が浮かばず、ただ曖昧に笑うだけ。気づけば僕は、仲の良い友達の前でも、仕事中でも、誰かの視線を極端に怖れていた。“嫌われたくない”──その思いが、いつしか“誰にも関わりたくない”という恐怖に変わっていた。静かに、ゆっくりと、でも確実に、心の地盤ごと沈んでいくようだった。自分を偽ることで、ただでさえ低かった自己肯定感がさらに下がり続け、心がどんどん脆くなっていった。やがて――壊れた。この“悪女”との一連の出来事が、僕の自律神経を狂わせ、パニック発作の引き金になった。
僕は、はっきりとそう確信している。
自分と、初めて向き合った朝
信じられなかったのは、他人じゃなく、自分だった
過去を振り返る中で、僕は徐々に気づいていった。
パニック障害を引き起こした本当の要因は、「ナオミ」という彼女だけではなかった。彼女の裏切りは、あくまで引き金に過ぎず、その根底には、長年僕が無意識に選び続けてきた“生き方”があったのだ。その生き方とは──「演じること」だった。母の顔色を伺いながら、怒りを押し殺して“良い子”を演じた幼少期。
サトシ先輩への恐怖に怯えながらも、友達には“強い男”を演じた中学時代。
そして今度は、彼女の理想に応えるため、“完璧な男”を演じた恋愛。そう、僕は“自分を守るため”に、誰かの期待に合わせて演じることを、生きる術として身につけてしまったのだ。
それはただの“癖”なんかじゃない。生き残るための“戦略”だった。でも、あの発作を経験して、ようやく思った。
このままじゃ、きっとまた同じことを繰り返す。
だから僕は、今度こそ変わろうと決意した。だけど今回は、今までとは違っていた。
意志の力だけで自分を変えようとするのではなく、具体的な行動指針があった。
それが──「逃げないこと」「偽らないこと」。この2つを、どんな小さな場面でも意識する。
そうすれば、自分自身と少しずつ仲直りできるような気がした。
僕の発作も、少しずつ落ち着いていくはずだと信じた。ひとつひとつの行動は、すごく地味で単純だ。
だけど、やり続けることは思っていた以上に難しかった。
それでも、やるしかなかった。
なぜなら、僕は今、暗闇の中に居る。
そしてこの闇を抜けるには、何かを変えなければならなかったから。過去を振り返れば、変わるチャンスは何度もあったはずだった。
けれど僕は、いつも言い訳をし、自分に甘え、逃げてきた。
その“逃げ”のツケが、パニック障害という形で今、僕の前に突きつけられている。ここで向き合わなければ、僕はこのまま“何も変えられない人間”として、心まで壊れてしまう。だから、僕は自問した。
「俺はなんで、こんなに自信がないんだ?」そこで、ふと思った。
“自信”って、そもそもなんだろう──。僕は、ノートに「自信」という文字を大きく書いて、その文字をしばらくじっと見つめた。
すると、ふと気づいた。
自信とは、「自らを信じる」と書く。
つまり、自信がないというのは、“自分のことを信じていない”ということなのだ。この単純な事実が、胸に突き刺さった。じゃあ、なぜ自分を信じられないのか?それは──僕が、自分に嘘をついてきたからだ。
誰かに気に入られようと、自分を偽り、
「変わろう」と決めたくせに、その約束すら守らずに裏切り続けた。
僕は、他人を裏切る前に、何度も自分を裏切っていたんだ。このままでは、誰が僕を信じてくれるというのだろう?まずは、僕が僕を信じなきゃ始まらない。
だから、僕はこう決めた。
「自分と友達になること」──それが、僕が変わる第一歩だと。ちょうどいい。僕には、今、友達が1人もいない。
それなら、まず自分自身と友達になればいい。
その決意から、僕は“毎日ジョギングをする”と自分と約束した。雨が降ろうが、雪が降ろうが、台風が来ようが──絶対に走る。
一度でも「今日は休もうかな」と思ってしまえば、僕はまた「判断する側の自分」に戻ってしまう。
その迷いが、また自分を裏切る選択へと連れて行ってしまうのだ。だから今回は、逃げ道のないルールを自分に課した。
これは、自分との約束の練習であり、戒めであり、戦いであり、そして──
新しい扉を開くための、挑戦だった。──今、僕には、やっとひとり友達ができた。
それは、これまでずっと目を背けてきた“自分自身”だった。でも、あなたはどうだろう?あなた自身と、ちゃんと友達になれていますか?
本音で語り合える関係を、築けてますか?
目的が“自分”を変えていくとき
逃げ癖の正体と、渋滞という名の地獄
「自分との約束を破ることが、自信のなさを作っていた」
そう気づいた時、僕の中に“なぜ、今これをやるのか?”という動機と目的がくっきりと浮かび上がってきた。動機は──自信を取り戻して、自分を変えるため。
目的は──やりたいことに、堂々と挑戦できる自分になるため。動機と目的が明確になればなるほど、人は迷わず立ち向かえる。僕はそれを、この時期に身体で学んだ。走り始めて2週間が過ぎたある日、大雪だった。
道は真っ白に覆われ、僕は思わず「さすがに今日は無理だな」と思っていた。でも次の瞬間、ハッとした。
「雪が降っても走る」──そう、自分でそう決めたんだった。なのに頭の中では、
「道が凍ってるから走りづらい」
「こんな日に走る人なんか居ない」
「雪が止んでから走ろう…」
と、頭の中で言い訳のオンパレードが始まった。この瞬間、はっきり分かった。「だから俺は、いつも自分との約束を守れなかったんだ」と。自分の“気分”を最優先にする癖。
それが、僕を裏切る思考パターンだった。その事に気付いた僕は、とにかく、1周だけでも走ろう──そう決めた。
ダメなら歩いたっていい。まずは、外に出ることだ。わざと甘えた自分に喝を入れるように、ジーンズにトレーナーという、その時に着ていた格好のまま走り出した。すると──
「…あれ?こんなもんか」
寒さの中に飛び込んでしまえば、思っていたほど辛くなかった。想像していた寒さに、気分が負けていただけだった。「それなら今日はいつもの倍、走ろう」
そう決めた僕は、結局いつもの倍の距離を走りきった。「よくやった、俺」
誇らしくて、嬉しかった。この体験から学んだことがある。
感情と行動は、必ずしもセットではない。
「怖い」「嫌だ」「億劫だ」と思ったとしても、行動はできる。むしろ、そういう時こそ行動が必要なんだ。この日以来、土砂降りの日も、台風の中でも、僕は迷わず走れるようになった。
自分の“気分”じゃなく、“目的”を最優先する──それが、継続するうえで決定的に重要な考え方だった。僕には、もう友達が誰もいないんだ。
だからこそ僕は、自分自身と“友達になる”ことに、全ての時間と労力を注ぎ込んだ。あの更生施設で200周を走ったあの日も、思い出すたびに僕の背中を押してくれた。
「できたじゃないか。あの時は、実際に走ったんだ。今、できないはずがない」もしこの時期に誰かとつるんでいたら、僕はまた楽な方へ流されていただろう。
一人きりだからこそ、自分と真正面から向き合えた。もちろん、しげちゃんのように、近くで見守ってくれる存在がいれば話は違うだろうが。しかし、この当時の僕に必要だったのは、“自分だけの力で立ち上がる環境”だった。振り返ってみれば、あの孤独な時間こそが、僕に「自分との約束を守る力」を根づかせてくれた。
それは、確かな自信となって、やがて自分を変える土台になっていった。そしてもう一つ、僕には新しい課題があった。
「逃げない自分になる」──その第一歩として、僕はトラック運転中に渋滞に遭遇しても逃げないと決めた。だけど……これは想像以上に苦しかった。渋滞。それは、僕にとって“死”を連想させる場所だった。
健常な人から見れば、まったく理解されないだろう。僕は、自由が奪われると強烈な発作に襲われた。
渋滞にハマり、身動きが取れないと分かった瞬間、こめかみが熱くなり、心臓が爆発しそうなほど脈を打ち始める。「やばい、死ぬかもしれない!」
頭の中はその恐怖で支配され、視界は暗く、息が詰まり、まるで別世界に連れて行かれたような感覚になる。暗い、深い、闇の中。
そこは、生きながらにして地獄を味わう空間だった。僕は何度も、渋滞の気配を感じた時点で、あえて遠回りをして避け続けた。
「また逃げた」「また約束を破った」
そのたびに自分が嫌になり、怒り、悔しさが込み上げてきた。それでも、逃げずに向き合う勇気がどうしても持てなかった。
僕にとっては、立ち向かうこと=死と直面することだったから。でも僕は知っていた。
このまま逃げていても、パニック障害は決して自然に治ることはない。
あの恐怖を突破しなければ、未来はないんだ。「渋滞に遭遇しても、逃げない」
これは、自分が課した“本気の課題”だった。だけど、何ヶ月も何ヶ月も、それを実行できずにいた。──そんなある日。
僕の頭をハンマーで殴るような出来事が、ついに訪れることになる──
見えない少年が、見せてくれたもの
当たり前の奇跡に、ようやく気づいた日
相変わらず、パニック発作に怯えながら、出口の見えない日々を過ごしていたある日。僕はいつものように発作に怯えながら車を運転していた。信号が赤に変わり、交差点の先頭で車を止めたそのとき、不意に視線の先で何かが動いた。ふと、横断歩道脇の電柱の陰に目をやると、ひとりの中年男性が身をひそめるように立っていて、じっと何かを見つめていた。「ん?なにを見てるんだろう…?」気になって、彼の視線の先をたどった。すると、横断歩道の向こうから、エンジ色のジャージを着た中学生くらいの少年が、白い杖を手に、慎重に一歩一歩を踏みしめるように歩いてくる姿が目に入った。そう、目が不自由な少年だったのだ。もう一度、電柱のおじさんを見ると、少年を案じるようなまなざしで見守っていた。青信号の点滅が始まり、少年がまだ横断歩道の中央あたりにいた頃、ついにおじさんが電柱の陰から小走りで飛び出した。僕は「助けに行くのか?」と思った。でも、おじさんは手を差し伸べたい気持ちを必死でこらえるように、一歩引いて見守っていた。助けたい、でもきっと、この少年は“自分の力で渡り切りたい”んだ。そんな空気を読み取っているようだった。信号が赤に変わる直前、少年は一人で無事に渡りきった。その瞬間、おじさんがそっと彼の肩をポンと叩き、何か言葉をかけた。……次の瞬間だった。その少年が、にっこりと、嬉しそうに笑ったのだ。僕は、その笑顔に、雷を打たれたような衝撃を受けた。「……見えてないのに、笑った……」心の奥が揺さぶられた。少年とおじさんは、満面の笑顔で会話しながら、そのまま並んで歩いていった。その一部始終を車の中から見ていた僕は、堪えきれずに号泣した。涙が止まらなかった。隣の車の運転手に気づかれないように、あわててサングラスをかけ、震える手でハンドルを握り、ゆっくりと車を発進させた。僕はそのときまで、目が見えないというだけで、どこかで「不幸で可哀想な存在」だと思い込んでいた。だけど、違ったのだ。“笑っていた”のは、その少年の方だった。それに比べて、目が見える僕は、毎日、憂鬱なことばかり考えて、苦しい、苦しいと犠牲者になり下がっていた。目が見えるという“当たり前の奇跡”を何ひとつ感謝せず、誰かのせいにして、自分を被害者にして生きていた。心の底から情けなかった。僕の方こそが、よっぽど不幸な人間じゃないか。そのとき、ふと思った。――もし、あの少年が僕の悩みを聞いたら、きっとこう言うだろう。「え?そんなの、悩みのうちに入らないよ!」僕の中で何かが変わった。あの少年と、あのおじさんが見せてくれたたった数分の出来事が、僕の凝り固まった意識を、根底から揺さぶってくれたのだった。
恐怖のトンネルで見つけた、静かなヒント
“逃げなかった先”で、初めて出会えた感覚
僕は、あの目の見えない少年に出会い、心の奥に眠っていた勇気を呼び起こされた。
甘えていた自分の心に、しっかりと喝を入れたんだ。それからは、逃げたいという気持ちを抱えながらも、その声に従わないようにした。
渋滞中の道にも、ようやく怯えず突入できるようになっていた。けれど、現実は甘くなかった。
発作は、そんな僕の努力なんて関係ないと言わんばかりに、容赦なく襲いかかってくる。それでも、不安な気分を抱えたまま、“渋滞を避けない”という行動を徹底した。
そうするうちに、少しずつ、わずかずつだが、コツのようなものが掴めてきた。これは、自分の体で体験しなければ絶対に理解できない感覚だった。
「気分」で判断するのではなく、「目的」を基準に動くことで、確実に道が開けていく。
そのことを、僕は自分の身体で学んだ。そしていつの間にか、渋滞中の道路を通ること自体は、ほとんど平気になっていた。
ここまで来るのに、実に2年以上かかった。確かに、僕はパニック障害の克服に近づいていた。
でも――それでもどうしても越えられない壁が、まだ残っていた。それは、トンネルの中で起きる渋滞に、自分の意志で突っ込んでいくことだった。
僕にとって、普通の道路とトンネルでは、まったく恐怖の質が違っていた。普通の道路での渋滞なら、脇道に逸れるという「逃げ道」がある。
でも、トンネルの中には逃げ場がない。
前も、横も、後ろも塞がれたあの空間――
それは、僕にとって“死”に近い場所だった。逃げられない、閉じ込められる。
想像するだけで、心臓が暴走を始める。
電車も、新幹線も、飛行機も、同じ理由で想像するだけで怖かった。
乗った瞬間から逃げ道がなくなる、それがたまらなかった。僕はある日、思った。
「このまま逃げていたら、絶対に完全克服はできない」
だから、腹を括った。
自らトンネルの渋滞に突っ込む“リハビリ”を決行しようと決めた。その舞台として選んだのが、ある有名デパートの地下駐車場だった。
日曜日の夕方、そこは地獄のように混雑することを、僕は昔から知っていた。思えば、パニック障害になる前の僕は、渋滞がむしろ好きだった。
スノーボードに行く仲間たちとの車中、渋滞中の時間が何より楽しかった。
笑い声が飛び交い、他愛もない会話が続く時間。
そんな時間が、今ではただの恐怖に変わっていた。ある日曜日の昼過ぎ。
僕はその地下駐車場に、1人で車を走らせた。パニック障害を患ってからというもの、人混みさえ避けていた僕が、
こうして繁華街にあるデパートに来るのは初めてだった。
車から降りた瞬間、全身に不安が流れ込んできた。
呼吸が浅くなる。
胸の奥がざわざわと泡立つ。
それでも僕は決めていた。本来の予定では、夕方の渋滞が始まるまで街をぶらぶらするつもりだった。
けれど、とてもそんな気分にはなれなかった。
気を紛らわせるどころか、不安は増すばかりだった。以前の僕なら確実に発作を起こしていただろうが、発作を起こすまでには至らなかった。リハビリの甲斐は確実にあった。結局、僕はそのデパートの中のベンチに腰を下ろし、人々の行き交いをただ見つめていた。
誰が見ても「時間を潰してる人」にしか見えなかっただろう。
けれど僕の中では、不安で心が叫びを上げていた。「そろそろ…時間だ」
僕はそう呟くと、駐車場の車へと戻った。
時刻は午後4時半。車は地下2階に停めてあった。
今のところ、まだ渋滞は始まっていなかった。「ちょっと早かったかも知れないな」そう思っていた。
けれど、僕の内側ではすでに“警報”が鳴っていた。
不安がじわじわと押し寄せてくる。「早く出たい…早くここを抜けたい」
そんな焦燥を抑えつつ、ハンドルを握り直した僕の手は汗で濡れていた。
緊張で背筋がこわばる。
でも、これは想定内である。
今日がトンネルでのリハビリ初日だから、当然だ。初めて発作を経験した、あの夏からちょうど3年。
また同じ8月だった。
車内にはエアコンの冷たい風が流れていた。
以前なら、この冷気だけで発作が引き起こされることもあった。
でも今は違った。
僕は、日々のリハビリの甲斐あって、ほんの少し自分を信じられていた。ゆっくりと車が進む。
やがて、例の“狭い区間”が見えてきた。
車一台がやっと通れるほどの、あの圧迫感のある出口の直前。
ドキドキと脈拍が早くなる。「大丈夫、大丈夫…」
心の中で何度も繰り返し言い聞かせた。出口に向かう細いトンネルは右にぐるりとカーブしていて、その先が渋滞していたのだ。
1分に1台進むのがやっとという混雑ぶりだった。そのとき――
ルームミラーに、後ろから近づく1台の車が映った。
一気に、心臓が跳ね上がった。
「やばい…逃げ道が…塞がれる」僕の思考は一気にパニックモードに突入した。
呼吸が荒くなる。
体が動かなくなる。「ダメだ!バックしよう!」そう思ってギアをバックに入れた瞬間、
背後の車が――「プップー!!」大音量のクラクションが、地下空間に響き渡った。その音が、まるで怒鳴り声のように、
僕の脳に突き刺さった。パニックがピークに達した。
もうどうにもならない。
僕の車の後ろに、どんどん車が並んでいった。
後戻りは不可能だった。「あぁ、もうダメだ…」
絶望した。でも、その瞬間。
僕はもう一度、心の中で叫んだ。「もう、どうにでもなれ!」「発作が来るならこい!」そう開き直った、その“次の瞬間”だった。――奇跡が起きた。あれほどバクバクしていた脈拍が、
スッ…と、一瞬で正常に戻ったのだ。徐々に、ではない。
まるでスイッチを切り替えたように、
一気に静けさが訪れた。「これだ…これだよ…」初めて“感覚”として分かった。
逃げないと、こうなるんだ。
現実をまっすぐ見て、覚悟するだけで、
あれほど暴れていた恐怖が、霧のように消えていく。その瞬間、僕は確信した。
「これは、道が拓ける感覚だ」と。この感覚に出会うために、3年間、もがき苦しんできたんだ。
未知の世界に手探りで飛び込んだからこそ、掴めた一生の宝物だった。
誰かにとっては一歩の距離かもしれない道のりを、
僕は険しい山ひとつを越えるような気持ちで踏み出した。他のどんなルートでも、この感覚には辿り着けなかっただろう。
これが、僕にとっての“正解の道”だったんだ。その後、駐車場を抜け出すまでの時間――
僕は、完璧に平常心だった。
心の奥から、幸せが湧いていた。「今、ここ」と言う現実を見て感じた。
人生でいちばん穏やかな感覚だった。更生施設で「ここで生きていく」と腹を決めたあの日と、「今日寝たら、明日死のう」と、人生に幕を引く決意をした、あの夜と、まったく同じ感覚だった。
目の前の現実に意識を集中すると、心が一瞬で静まる。
あの感覚。渋滞から抜けただけなのに、
「こんなにも幸せを感じられるのか」と、心底驚き感動した。それ以来、僕は人生のどんな場面でも、
“小さな幸せ”を見つける目を持てるようになった。僕は、自分に問いかけた。「ここがゴールなのか?」すると、心の奥から声が聞こえた。「違う。ここがスタートだ」これからの人生は、
“本当にやりたいこと”に向かって生きていこう。
僕はそう、固く誓った。長い暗闇の中でもがき、苦しみ、
その果てに――
ようやく見えてきた。まだぼんやりとした地平線。
けれど、その地平線の向こうから、
静かに、光が滲み出していた。だけど――
まだ、その先にも
最後の試練が待っていたのだった。
「心の奥に落とすための、静かな一問」
あなたにとっての“恐怖のトンネル”は、どこですか?
もし今、その入り口に立っていたら――
そのまま、一歩踏み出せそうですか?
理想の人を、やっと見つけた──それは…
癒される側から、灯を灯す側へ
僕はこれまで、ずっと心のどこかで――
“しげちゃんのような人”を探し続けていた。
目には見えなくても、存在していてほしかった。
不安でたまらない夜も、孤独で胸が押し潰されそうな時も、
どこかに、しげちゃんのような人がいて、僕を見つけてくれる。
そんな淡い期待を、僕は何年も手放せずにいた。「こんな時には、こういう言葉をかけてほしい」
「孤独に潰されそうな夜には、ただそばにいてほしい」
「何も言わなくていい。ただ“いてくれる”だけで救われる気がする」
そんな思いばかりが頭をよぎっていた。一歩がどうしても踏み出せない時には、
背中を、そっと押してくれる人がほしかった。
辛い時、苦しい時、何をしてくれたら安心できるか。
そんなことばかりを、毎日のように考えていた。でも――
僕が心の中で思い描いていた“理想の誰か”に、
現実で出会うことは、とうとうなかった。
どんなに探しても、誰にもそれを重ねることはできなかった。そしてようやく、僕は気づいたんだ。
「しげちゃんみたいな人は、どこにもいない」
この事実を認めるには、時間がかかった。
それでも、自分の中に生まれたその“諦め”は、確かだった。でも――
諦めるということは、
誰かに頼ることを手放す、ということだった。
つまり、これからはもう、自分ひとりで立ち向かっていかなければならない。
それが“諦める”ということの本当の意味だった。そんな時、ふと頭に浮かんだ。
「だったら、自分が“その人”になればいい」と。
長年、僕が思い描き、求めてきた理想像。
その人物像に、自分自身がなればいい。
それが、いちばん早い方法なんじゃないか、と思った。僕は、あまりにも長く、苦しんできた。
その痛みのひとつひとつが、今では人の痛みに寄り添う“鍵”になっている。
だからこそ、その痛みと向き合える。
どうすれば人が安心し、どうすれば勇気を持てるのか。
どんな言葉が届き、どんな温度のまなざしが心を動かすのか。
どんなタイミングで、どんな声をかければ、その人が前に進めるのか。僕がこれまで、苦しい時に心の底から「こうしてほしかった」と思ったことを、
今度は僕が、誰かのためにやればいいだけなんだ。
自分がずっと求めていた“理想の人物”に、
自分自身がなっていけばいい。
それだけのことだ。――そう思うようになった。けれど、実際には簡単じゃなかった。癒す側になるということは、
自分が“癒される側”でいることを手放す、ということだ。
もう誰かに甘えたり、寄りかかったりするわけにはいかない。
誰かの灯になろうとするなら、自分の灯は消せない。
常に、自分の内側を燃やし続けなければならない。それは、思った以上に大きな決断だった。僕は、なかなか覚悟を決められなかった。
「本当に、自分にできるのか?」
「ずっと熱くい続けられるのか?」
何度も迷った。
そして、1年以上の時間がかかった。それでも、ようやく僕は腹を括った。
何年かかるかは分からない。
でも――行くしかない。
僕は、自分の人生の主語を変えると決めた。癒される側から、癒す側へ。誰かに助けてもらうことを待ち続けるのではなく、
かつての僕のように苦しんでいる人の“灯”になるために、
僕自身があの理想の人物になる。それが、僕にできる唯一の生き方なのだと思う。長い間、僕は“誰か”を待っていた。
でも、今ならわかる。
“その誰か”になるのは、僕自身だった。
あなたにとって──
「本当は、どんな人にそばにいてほしかった?」
「その人のように、自分が誰かに寄り添うとしたら、何ができるだろう?」そんな問いを、心の奥で、そっと抱いてみてほしい。
“本当の声”に従って生きると決めた日
“モヤモヤ”の正体と、偶然の顔をした運命のヒント
ようやく、僕は“元の場所”に戻ってきた。
ただし、もうあの頃の僕とは違う。パニック障害になる前、僕はずっと訳の分からない“モヤモヤ”に囚われていた。
何かが引っかかっているようで、でもそれが何なのか分からない。
あの違和感の正体を、今ならはっきり言える。――自分を裏切っていたのだ。本当はやりたくないことを、「仕方ない」と言い訳して選び、
心に嘘をついて生きていた。
その嘘が積み重なって、心の中の“本当の僕”が、ずっと叫んでいた。
「違うだろ?」と。このモヤモヤを断ち切る方法は、ただひとつだった。
それは、「本当にやりたいと思えることを、逃げずにやること」。しかも幸いなことに、今の僕には友達もいない。
誰にも気を遣わず、誰にも遠慮せず、たった独り。だからこそ、これはチャンスだった。
「今しかない」と思った。
新しい人生の扉を開けるなら――誰の目も気にせず、
誰の意見にも縛られず、ただ自分の“心の声”に従って進めばいい。だったら、今までの延長線にある仕事はやめよう。
人からよく見られるための選択も、もうやめよう。僕が知っている世界の中から選んでいたら、
結局また、同じ景色に戻るだけだ。僕が本当にやりたいことは、
“まだ見ぬ世界”の中にある。
それは、僕の興味。僕の好き。僕の中にずっとあった種。その道に進むには、覚悟がいる。
だけど僕は、あの苦しみの中で覚悟の意味を学んだ。
だから、もう逃げない。僕は、新しい人生を生きる覚悟を決めた。そんなある日のことだった。仕事を終えて家に戻ると、テレビのニュースが流れていた。
当時のアメリカ大統領、ビル・クリントンが演説していた。
その演説の中で、彼はこう言った。「21世紀、世界の目はアジアに向くだろう!」その瞬間、心の中に電流が走った。
なぜだか分からない。理由なんてなかった。
けれどその一言だけが、僕の耳に焼きついた。まるで未来からの“ヒント”のように。それ以来、その言葉がずっと僕の頭にこびりついて離れなかった。そして――
その言葉が、僕の人生を変えていくことになるなんて、
そのときの僕は、まだ知らなかった。モヤモヤの正体に気づいたとき、
それは、誰かに裏切られた痛みではなく、
自分がずっと、自分を裏切ってきたことへの気づきだった。だからこそ――もう二度と、自分の声を無視してはならない。
偶然のように見える“ヒント”は、
その覚悟を持った者にだけ、届くようになっている。では、あなたに問います。
「あなたの中にずっとある“モヤモヤ”の正体は、なんでしょう?」
「それは本当に、他人のせいですか? それとも……?」
自分の人生を取り戻す、最初の一歩
“発作が来ても、行く”と決めた日が、心の封印を破った
渋滞の中を発作なく運転できるようになったとき、僕は次のステージへ進む覚悟を決めた。「今度は対人恐怖症を乗り越えよう」と。人と話せないままじゃ、本当の人生は始まらない。パニック障害を発症して以来、僕は人と会うことすら避けるようになっていた。もともと、人間不信の火種はもっと前にくすぶっていた。あの時、恋人に裏切られ、心に深い裂け目が入った。そこからじわじわと、人と関わること自体が怖くなっていったのだ。でも、もう逃げてはいられない。僕はトラックの運転中に、リハビリのように道沿いの店に立ち寄ることを始めた。車を停めては、その場にある飲食店や雑貨屋に入り、店員と何気ない会話を交わす。それが「会話の練習」だった。もし不安が襲ってきたら、店を出ればいい。ただそれだけ。だからこそ、僕には続けられた。この方法は我ながら画期的だった。少しずつ人との距離感が掴めるようになってきたし、昔の自分を思い出すこともできた。忘れていた感覚が、少しずつ蘇ってきたのだ。ここでもやはり、「今、この瞬間」に意識を置くことが鍵だった。自分が話すことよりも、相手の言葉に耳を澄ます。ひとつひとつの言葉に、心を込めて聴く。すると、自分の中に渦巻いていた過剰な意識――「ちゃんと話せているか」「どう見られているか」――そんな自意識が、少しずつ薄らいでいった。「今、ここ」にいる。それだけを徹底する。ただ目の前の会話に集中する。未来でも過去でもなく、今この一瞬に心を置く。そうやって一歩ずつ、人と向き合う準備が整っていった。そんなある日、年上のサーフィン仲間から電話がかかってきた。「今日さ、家でバーベキューやるんだけど、お前も来ない?」彼は、僕が発症してからも変わらず気にかけてくれていた、数少ない存在だった。僕は反射的に断りそうになったが、ふと、「ダメでもいいから行ってみよう」と思った。そして、怖さを抱えたまま、その家のドアを叩いた。懐かしい仲間たちが、以前と変わらない笑顔で迎えてくれた。その瞬間、胸がいっぱいになった。僕は思わず泣きそうになった。でも、現実は甘くなかった。みんなの前では、練習の成果を発揮することができなかった。緊張と不安が一気に襲いかかってきた。場に馴染むどころか、ずっと浮いた気持ちのまま、ついに発作の予兆が来てしまった。そして、僕は最後まで居ることができず、途中で帰ってしまった。たぶんこの時の僕は、“期待しすぎていた”んだろう。
治っているはずだと、どこかで信じたくなっていたのかもしれない。悔しかった。でも、気づきもあった。やはり大切なのは「今、この瞬間」に集中することだった。僕はまた、「もし発作が出たら」「もし変な空気になったら」と、起きてもいない未来に囚われていた。頭の中は不安のシミュレーションでいっぱいになっていて、その場を感じるどころではなかった。心ここに在らず、だったのだ。このままじゃ前には進めない。停滞か、後退か――それはもう嫌だった。だから僕は、開き直った。「発作が来たって、もう知らん!それでも行くんだ!」半ばヤケクソのような覚悟だったが、その決意は、確かに僕を前に進めるための点火剤になった。ずっと胸に閉じ込めてきた想い――あの、正体の見えない焦燥――それをもう、外に出さなきゃいけない時が来た。でも、それは本当に怖いことだった。自分が本当にやりたいことをするというのは、「未知の世界に足を踏み入れること」だからだ。そこには地図がない。ルールも分からない。だから怖い。だからこそ僕は今まで、無意識に逃げてきた。けれど、パニック障害を薬を使わずに克服しようと決意してから、僕はもう十分に未知の世界を歩いてきたじゃないか。あの、先の見えない真っ暗な道を、歯を食いしばって歩き続けてきた。その日々に比べれば、これから進む道はきっと、光がある。怖さはあっても、あの頃のような絶望ではない。当時、自営業の運送業は収入も悪くなかった。でも、皮肉なことに、その安定が僕の目を本当にやりたいことから遠ざけていた。「このままでいい」と思いたい自分が、ずっと足を引っ張っていた。でももう、はっきりした。「ここから出してくれ!」僕の内側で、何かが叫んでいた。日々、体調が整っていくにつれ、自分の本当の願いが明らかになってきた。まだ輪郭はぼんやりしていたけれど、僕は「家具を作って生きていきたい」と思うようになっていた。そろそろ、この今の生活に区切りをつける時だ。僕は、自営業を辞めることを決意した。これはただの職業の転換ではない。これは、僕がようやく「自分の人生を生きる」と決めた、最初の一歩だった。逃げることが悪いわけじゃない。
でも、逃げ続けたその先に、
“心の叫び”がずっと待っていた。それは、「ここから出してくれ!」という声だった。あの頃の僕が見つけた“人と向き合うための訓練”。
それは、今になって振り返れば、自己流の対人恐怖克服マニュアルだった。
もし当時の僕と同じように苦しんでいる人がいるなら、
この章が、そのまま“第一歩”の参考になるかもしれない。だからこそ、自分に問いかけてほしい。
「あなたの中で、叫びを上げている“本当の声”は何ですか?」
「それを、いつまで閉じ込めておきますか?」
その“ソファの形”は、未来から届いた
“座る”という行為に宿る、僕の原点
あの日のことは、今でも鮮明に覚えている。
僕はいつものように、トラックの燃料を補給しようと、地元のガソリンスタンドに立ち寄った。
すると、偶然そこにいたのは仲の良かった同級生だった。「ひさしぶり!」他愛もない会話の中で、ふいに彼が話し始めた――バリ島での結婚式の思い出を。新婚旅行も兼ねてバリで式を挙げた彼は、現地で出会った家具に一目惚れし、何点か購入して日本へ送ったという。ところが、3ヶ月後に届いたその家具は、いざ開梱してみると、中から虫が湧き出していたらしい。楽しみにしていた新居で使うには到底無理で、泣く泣く処分したそうだ。それでも彼は諦めきれなかった。
あの、どこか懐かしく、自然の匂いがするようなバリ島の家具が忘れられなかったのだ。悔しさを抱えながら、彼は東京のインテリアショップを巡った。そして、同じようなバリ島家具を見つけたのだが――その値段は、現地の10倍だったという。彼の話を聞きながら、僕の中で何かが結びついていった。
バリ島、家具、サーフィン――。過去に旅したあの島で、ホテルのロビーや部屋に並んでいた洒落た家具たちが、脳裏に浮かび上がってくる。そして、不意に、目の前に「あるソファーの形」が浮かんだ。シルエット、質感、色合いまで、まるで手で触れられるようにリアルだった。見たことがある──そんな感じではなかった。むしろ、「これから自分が作るもの」として、内側から湧き上がってきた。その瞬間、心がズキンと鳴った。息が詰まり、鼓動が速くなる。なぜかは分からない。けれど、そのソファのイメージは、ずっと昔から僕の中にあった気がした。まるで“未来の僕”が、今の僕に見せてきた設計図のようだった。気づけば、あの頃の自分を思い出していた。
まだ何者でもなかった若い僕が、「家具を自分で作って商売にしたい」と無邪気に語っていた、あのころ。特に、椅子とソファー。
なぜだか昔から、僕は“座る”という行為に惹かれていた気がする。
座ることで、身体が沈み、心が落ち着き、自分に戻れる場所――。
家具というモノではなく、「自分の感覚を取り戻せる場所」を、僕はずっと、無意識に求めていたのかもしれない。ふと、あの言葉が脳裏をよぎった。「21世紀、世界の目はアジアに向く」何気なく耳にしたはずのあの言葉が、今になって、まるで未来の自分に送られたメッセージのように響いてきた。
点と点が線になった。
今までバラバラだった思いつきや感覚が、一瞬で一本の道に繋がった気がした。その瞬間、僕は確信した。「バリ島家具専門店をやろう。」考えたわけじゃない。決意が、内側から勝手に立ち上がってきた。それは、頭ではなく魂からの声だった。ずっと探し続けてきた道が、ようやく目の前に現れた。迷路に光が差したんじゃない。僕自身が、ようやく“光の方へ”踏み出そうとしていた。
心の扉に、初めて手をかけた日
“かっこ悪さ”を超えて、人と繋がる勇気が生まれた
その日は、意外なほどあっけなく訪れた。 5日間だけのバリ滞在。僕は“未知の旅”をリュックサック1つで始めようとしていた。空港まで車を走らせている途中、携帯にメールが届いた。相手は、長年本音で話し合える唯一無二の存在──姉のような人、ミホさんだった。 パニック障害のことは誰にも話していなかったが、「バリ島家具店を始める」とだけは、彼女に伝えていた。そのメッセージには、こう綴られていた。「今日ほど、あなたのことを尊敬できると思った日はないよ。
新しい人生のスタートだね。ずっと応援してるからね。」
その一文を読んだ瞬間、ハンドルを握る手が震えた。
あふれた涙が、前を見ていたはずの視界をにじませた。ほんの数ヶ月前まで、僕は誰とも会えず、言葉すら交わせなかった。
すべての人間関係が途絶えたと感じていたが、実際は違った。
世界を閉ざしていたのは、僕自身だったのだ。差し伸べられていた手に、気づこうとしていなかった。
ミホさんのように、静かに寄り添ってくれていた存在に、
僕はどれほど救われていたのだろう。──なぜ、頼れなかった?
──なぜ、弱さを見せられなかった?思考は、そこで止まる。
「かっこ悪い自分」を見せたくなかった。
ただ、それだけだった。中学生の頃からずっと、傷つかないために嘘をついていた。
“よく見られたい”という思いの裏に、恐れがあったのだ。
でも、その嘘は、じわじわと自分を殺す毒でもあった。偽りの仮面をかぶるたびに、本当の自分と現実のギャップが広がっていく。
そのギャップはやがて不安になり、発作になり、生きることの苦しさに変わっていった。あの最初の発作から、もう3年半。
何度も同じ場所で倒れ、立ち上がれずにいた。「今日ゆっくり寝たら、明日死のう」──
そう思った夜が、たった一度だけあった。
あの夜に限って、深く眠れた。
それだけのことなのに、翌朝はほんの少し、景色が違って見えた。きっと、そこから始まっていたんだ。だから今、空港へ向かう車の中で涙を流している自分を思うと、胸が熱くなった。
「よくここまで、頑張ってこれたな…」
自分で自分に、そう声をかけたくなるほどだった。まだ“過去”とは呼べない出来事たちが、
ようやく“物語”として振り返れる距離に来ていたのかもしれない。あの頃の僕は、這いつくばっていた。
それでも信じていた。
いつか、きっと光が差すと──。その小さな光を、ずっと信じ続けてきた自分を、今の僕は誇らしく思う。人は、他人と比べては絶望する。
でも今の僕は違った。
過去の自分とだけ、比べていた。
昨日より、ほんの一歩でも進めたか──
それだけを見つめられるようになっていた。そう思えた時、ようやく「出発」が、心の中でも始まった気がした。扉は厚い。
けれど、それは内側からしか開かない。
そして今、僕はようやく──その扉に手をかけていた。
あなたにとって、“物語になり始めた過去”はありますか?
それは、まだ痛みを伴う出来事かもしれない。
でも、いつかその傷が、誰かの光になる日が来る。
──その物語を、そろそろ語り始めてみませんか?
逃げ場のない空で、僕は決断した
“恐怖に飲まれずに生きる”という選択
「しまった……」
飛行機が滑走路を離れた瞬間、僕の心も現実から離れていった。
不安、後悔、焦燥――全てが一気に押し寄せる。家具の知識も、商売の経験も何もないのに、なぜ僕はバリ島家具店をやると決め、勢いでチケットを買い、この機内にいるんだ?
何も分からない未来に飛び込んでしまった自分を、急に恐ろしく感じた。しかもここは逃げ場のない空の上。発作が来れば、もうどうすることもできない。
心臓が爆音のように鳴り、顔から血の気が引いていくのがわかった。「ここまで来てこれか……もうこんな人生、嫌だ」誰にも言えず、誰にも頼れず、独りで苦しみ続けた3年半。
それでも僕は、「今、ここに集中するんだ」という、ただその一言を信じてやってきた。でも、現実は簡単じゃなかった。
集中しようとしても、意識は勝手に“最悪の未来”へ引きずられていく。
車なら脇道に逃げられた。トンネルなら最悪、降りて逃げられた。
でもこの飛行機だけは、逃げられない。
逃げ道のない密室の中、僕は問いかけた。
「このまま、怯えるだけの人生でいいのか?」そのとき、僕の奥にいる“もう一人の自分”が叫んだ。
「絶対に嫌だ!」僕は、現実に戻ると決めた。
もう、望まない自分に支配されない。
もう、嘘の妄想に飲み込まれない。だから、“今ここ”に目を開けた。
心臓の鼓動を感じながら、呼吸の震えをなぞりながら、
怯えている自分を、そのまま見つめた。「怖がっていてもいい。ただ、逃げずにここにいる」
そう言い聞かせながら、僕は微かな光に意識を合わせた。不思議なことに、恐怖の波がすっと引いていった。
静かだった。深海のような静けさの中、
僕は、自分の足で立っている感覚を思い出していた。やがて、機体は静かにバリ島に着陸した。
恐怖とともに、でも確かに、僕はここまで来た。
逃げ場のない空の上で、“意識を取り戻す”という生き方を選んだ。
それは、僕の人生のリハビリとしては、あまりにも象徴的で、あまりにも尊い一歩だった。けれど、今なら分かる。
あの飛行機の中での体験こそが、
渋滞の中で感じた“あの穏やかな感覚”──
「今、ここ」にすべてを委ねるという、生き方の本質が
本当に試された瞬間だった。あの感覚が本物かどうか。
それを確かめるための“最後の試練”が、
空の上で、静かに僕を待っていたのだ。
空港で終わった『いつもの自分』
“逃げない”と決めた、その一歩が殻を破った
バリ島の空港に降り立った瞬間、南国特有の湿度と香辛料のような空気が、身体の奥まで入り込んできた。「ようやく着いた…」そう息をついた矢先、僕の中にまたしてもあの“恐怖”がじわじわと押し寄せてきた。到着ロビーには、ちょうど4機の飛行機が同時に到着していた。
あたり一面、人、人、人。どこを向いても人の波。
身動きが取れないほどの混雑に、僕の心はみるみるうちに崩れていった。逃げられない──
戻れない──
どこにも出口がない──その感覚は、かつて地下駐車場で発作を起こしかけた時と同じだった。
呼吸が詰まり、胸がギュッと締めつけられ、
「ここから早く出たい!」という衝動が爆発しそうになる。だけど僕は、そこで気づいた。
これまで僕は、嫌なことがあるたび、逃げてきた。
気まずさからも、人の目からも、そして何より、自分自身から。──でも、逃げるたびに、人生は僕をまた同じ場所に連れ戻してきた。ここバリ島の空港は、そんな僕への「最終テスト」だったのかもしれない。
目の前には何千人という群衆。後ろにはもう飛行機の扉すら閉ざされている。
もう、逃げ場はどこにもない。僕はそこで、ひとつのルールを自分に課した。
「列を移動しない。焦らない。ただここに立つ」焦りの波が何度も襲ってくる。
「もう無理だ、抜け出したい!」という声が、心の奥で叫ぶ。でも、僕はその声に従わなかった。
それは、小さなようでいて、僕の人生で初めて「逃げない」を選んだ瞬間だった。結果、僕が空港の外に出られたのは、到着した何千人の中で、最後から2番目だった。
出口に辿り着いたとき、バリ島はすっかり夜の帳に包まれていた。だけど、僕の心には小さな光が灯っていた。
「逃げなかった」
その事実だけが、今までの僕を塗り替えてくれた。逃げ癖は、魂の奥に静かに根を張る。
小さな場面で逃げ続ければ、やがてすべてが“大きな苦しみ”に見えてくる。
だから僕は、ここで止めたかった。自分の中にあった“逃げるための習慣”を。この日、僕はようやく気づいた。
「男に生まれた」ことと、「男になる」ことは、まったく別の話なのだと。
試練を超えてこそ、人は“自分を生きる覚悟”を得られる。ふと後ろを振り返ると、中国人らしきおばさんがひとりだけ残っていた。
“彼女もきっと、何かから逃げ続けて、今ここに立っているのだろうか”
そんなことをふと思いながら、僕は出口の方へ、ゆっくりと歩き出した。それはただの入国ゲートではなかった。
自分という“逃げ癖の殻”を抜け出す、ひとつの通過儀式だった。
あなたが、何度も繰り返してきた「無意識の逃げ癖」は何ですか?
そして、いつまで、それを持ち続けますか?
異国で崩れた心の壁──ハムザーとの出会い
初対面の温もりがくれた、小さな大きな一歩
ホテルのスタッフ、ハムザーはとても人懐っこく、初対面とは思えないほどすぐに打ち解けた。日本語も半分くらいは話せるようで、片言だが意思疎通には特に問題がなかった。僕がホテルに到着すると、彼は「ちょっと街を案内するよ」と言って、そのまま車に僕を乗せた。「ねぇ、ハムザー。俺、お腹空いた」そう言うと、ハムザーは迷いなく車を走らせ、できたばかりの大きなショッピングモールへと連れて行ってくれた。中に入って案内されたのは、なんとマクドナルド。「バリに来てマックか…」と一瞬思ったが、ハムザーは胸を張ってこう言った。「どうですか?綺麗で、大きいでしょ!」その顔がまるで少年のように誇らしげで、僕は笑ってしまった。確かに、天井の高いそのモールは、日本でも見たことがないスケール感だった。マックがどうとかより、彼が僕を歓迎しようと一生懸命になってくれている、その気持ちが何よりも嬉しかった。「ねえ、あだちさん。バリに何しに来たんですか?」不意に聞かれたその問いに、僕は少し戸惑いながらも答えた。「家具が欲しいんだ。バリの家具。分かる?」「かく?…かくってなんですか?」ああ、“家具”って単語は通じないか。そこで僕は慌てて英語を思い出した。「ファニチャー。ファニチャー、分かる?」中学の頃に取り入れた睡眠学習、あの奇妙な努力がこんな所で役に立つとは。「おぉ、オッケーオッケー、ファニチャーね!」と、ハムザーは満面の笑みで応えた。その瞬間、「よし、買い付けはいける!」と、僕はひとまず安心した。もちろん、この時は、家具探しがあんなにも苦難の連続になるとは、知る由もなかった。でもこの夜、何よりも大きかったのは──僕が「人と一緒に車に乗れた」ことだった。パニック障害を発症してからというもの、僕は一人でならなんとか車に乗れるようになっていた。でも、誰かが同乗していると、その場から逃げられないという“拘束感”が襲ってきて、どうしても無理だった。発作が起きるかもしれない…その恐怖が、心を縛っていた。それなのに、今、ハムザーと一緒に、自然な形で車に乗っている。しかも初めて会った相手と、異国の地で、まるで昔からの友人のように──。これは僕にとって、ただの車移動ではなかった。自分の中の“壁”が、音を立てて崩れた瞬間だった。ハムザーはというと、陽気に、ほとんど意味の通じない片言の日本語で、一方的に楽しそうに話し続けていた。その姿がとても無邪気で、なんだかおかしくて、僕は心から笑っていた。「この旅、楽しくなりそうだな──」ふと、そんな予感が胸をよぎった。しかしその希望は、皮肉にも、旅の初日に打ち砕かれることになる。けれど、それはこの旅の本当の始まりでもあった。
道に迷った日、未来に出会った
絶望のロビーに舞い降りた天使
バリに到着した翌朝。僕は1人で、家具を探しに出かけた。観光気分なんて一切なかった。完全に仕事モード。これは、自分にとって良い傾向だった。ハムザーはホテルの仕事があるから今日はガイドできないという。けれど、最初から誰かに頼るつもりなどなかった。そもそも「ガイドを雇う」という発想すらなかったのだ。──全部、自分でやり遂げる。そのつもりで日本を出てきた。でも、それは甘かった。薄暗くなり始めた夕方、僕はトボトボと、何の成果も得られないままホテルに戻った。ホテルのスタッフたちが、ニコニコしながらも心配そうに声をかけてくれる。「あだちさん、家具、見つかりましたか?」僕がバリに家具の買い付けに来たことは、すでにホテル中に知れ渡っていた。チェックインの夜、ハムザーが皆の前で堂々と説明してくれたからだ。「……無かった。ていうか、家具ってどこに売ってんの?」本当に、甘かった。僕はこの日、地図も下調べもなしに、ただ手当たり次第に歩き回った。英語も通じない。日本語なんてもってのほか。道行く人に尋ねても、首を傾げられるか、知らないと言われるばかり。「このあたりには家具屋は無いんだな」そう思って、今度はタクシーに切り替えた。「ファニチャー、知ってる?家具、家具!どこ?」そう尋ねると、決まってドライバーたちは元気に言う。「オッケーオッケー!」……なのに次の瞬間には、「ウブド?キンタマーニ?」と、観光地の名前を出してくる。まったく話が通じていない。僕は、そのたびにタクシーを降りた。4台目に乗ったとき、降りた場所がどこなのかさえわからなくなっていた。でも僕は歩き続けた。必死で家具を探して。後から知ったが、その辺りはイカットという織物を作る村だった。──そりゃ見つかるわけがない。結局、バリ島初日は、家具ひとつ見つけられないまま終わった。ホテルに戻ると、ハムザーはまだ別の観光客のガイドに出ていて不在だった。僕はロビーの椅子に腰かけて、腕を組んで考え込んだ。「やっぱり俺、バカだったんかな……。なんの準備もせずに、いきなりバリに来るなんて」後悔と焦燥が胸を締めつけた。そのときだった。ふいに、ひとりの女性が僕に声をかけてきた。「どうしたん? なんか困ってるみたいやけど?」顔を上げると、そこには20代前半と思しき、綺麗な女性が立っていた。肌は日焼けして健康的で、ぱっと見は外国人のようにも見える。「えっ……日本人ですか?」「そうやで。京都から毎年来てるんよ、このホテル」驚いた。その瞬間、僕のなかの何かが決壊したように、彼女にすべてを話していた。家具を探しにバリに来たこと。言葉が通じなくてどうしようもなかったこと。滞在日数が限られていて、焦っていること。きっと相当、顔に出てたんだと思う。焦りと不安が。すると彼女は、まったく迷いもなく、こう言った。「ええ人、紹介したるわ。もってこいの人が、今ちょうどこのホテルにおるんよ。お兄さん、ラッキーやなぁ!」それが、僕の運命を変える出会いになるなんて。──その時の僕には、想像すらできなかった。
知らない誰かが未来の扉を開けた
たまたまの出会いが、全てを繋ぎ始めた
シャワーを浴び、ホテルのロビーに降りると、ウランさんが椅子に腰掛け、僕を待っていた。「来た来た。この人や」そう言って紹介されたのは、真っ黒に日焼けした男性。Tシャツにビーサン、その場の空気を掌握するような存在感。「何も知らずにバリ来たん? 無茶しよんなぁ〜、昔の俺そっくりや!」流暢な関西弁に驚いた。「え、日本の方なんですか?」彼の名はドイナさん。大阪で貿易業を営み、家具やアートの買い付けにも精通している人物だった。今の僕にとって、これ以上ない案内人だ。「家具を仕入れたいんやろ?ちょっとアドバイスというか、プランがあるねんけど、ちょっと聞いてな?」その一言を皮切りに、僕のバリ滞在の流れは一気に変わった。ドイナさんとの会話で判明したのは、「5日間の滞在では長年のプロでも家具の仕入れは不可能」という現実。僕は迷わず帰りの航空券を破り捨てた。さらに信じられない事が起きたのだ。数日後、ホテルの事務室に呼ばれると、日本人女性が待っていた。ホテルオーナーの奥様で、僕の事情をすでに把握していた。「私たちはあなたに全面的に協力します。ホテルの従業員を家具探しに自由に使ってください」その言葉に、胸の奥で何かがほどけた。なんだこの展開?何が起こっているのかさっぱり分からなかった。これまで「一人でやるしかない」と握りしめていた世界が、その瞬間、静かに書き換わった。そして、現地のホテル全面協力の元、ホテルスタッフと共に、家具探しの旅が始まった。発作の不安はまだ消えていなかったが、「怖くてもいい」と腹を決め、一歩を踏み出した。途中、山奥の村で出会った子どもたちの、曇りひとつない瞳を見た瞬間、不意に涙が込み上げた。——そうだ。俺も、昔はこんな目をしていたんだ。壊れたと思っていた心は、実は壊れていなかった。ただ、長い間忘れていただけだった。家具探しは、もしかしたら口実だったのかもしれない。本当の目的は——もう一度、自分の心を信じるため僕は見えない力によってバリ島に導かれたのかも知れない。
心の中のソファーは、本当に存在していた
思い描き続けたイメージが、現実として訪れた日
バリ島での家具探しは、想像以上に骨が折れた。
「家具通り」と呼ばれる家具屋が密集したエリアを見つけてから、僕はその200軒以上を、一軒一軒、まるでローラー作戦のように回り尽くした。さらには、家具製作の工場まで足を運び、現地の空気を吸い込みながら、黙々と目を凝らし、チェックしていった。でも──見つからなかった。
僕の頭の中に鮮やかに浮かんでいた、あのソファーのイメージに、どこも届いていなかった。似てはいる。悪くはない。価格も手頃だった。
でも、ほんの少しだけ“違う”のだ。質感か、形か、佇まいか……何かが違う。バリで家具屋をやると決めたあの日、僕の中に突然降りてきた、あのソファーの映像。
それは単なる妄想でも理想でもなく、もう“決まっているもの”のように、心の奥に存在していた。だから、妥協することは簡単だったけれど、僕にはできなかった。
自分の目で見て、本当に「これだ」と思えるものを仕入れたい。
これは性格の問題というより、“本気の証明”だった。そんなある日、いつものようにホテルの従業員ハムザーと共に、エミさんの言葉に甘えて家具を探していた時のこと。
運転中のハムザーの電話が鳴った。「ハイ、モシモシ……え? ホント? どこですか?」受話器の向こうで話すエミさんの声に、ハムザーは僕の方を振り向いて、ニッと笑い、親指を立てた。──当たりだ。エミさんの知人が、僕の探していたソファーにぴったりのものを見かけたという情報をくれたらしい。
エミさんは、僕が理想を見失わずにいられるように、陰でずっと情報を集めてくれていたのだった。その言葉だけで、胸が熱くなった。
僕たちは急いで、その家具屋へと車を走らせた。現地に到着し、店舗の外から一瞬だけ見えたソファーのシルエット。
その一瞥だけで、雷のように全身に電流が走った。「あった……これだ!」店内へ飛び込むと、そこにはずっと僕の頭の中にあった、あのソファーが、そのままの形で、静かに置かれていた。信じられなかった。けれど、疑いようもなかった。ずっと探し続けてきた“イメージ通り”のソファーが、まさにそこに、現実として存在していた。なぜ、あのときあのイメージが、あんなにも鮮明に浮かんできたのか。
今も不思議で仕方ない。僕はその場で、迷わずソファーセットを5組、買い付けた。心から言える。あきらめなければ、必ず出会える。
自分の本音を貫いて、探し続ければ、それはちゃんと現実になる。たとえ少し遠回りに見えても──本気の願いは、ちゃんと“こっちに向かってきている”。そう思わずにはいられなかった。──あのソファーを探していたんじゃない。 僕は、本気の自分を信じたかった。だから、あれは“出会い”じゃなくて、約束の場所だった。
パニック障害すらギフトだと気づく
怖くて逃げた過去が、希望の種を蒔いていた
バリ島家具屋を開く。
その夢を叶えるために飛び込んだ、無計画な仕入れの旅も、いよいよ終盤を迎えていた。毎朝、ホテルのテラスでモーニングを食べながら、僕はドイナさんにその日のスケジュールを報告し、的確なアドバイスをもらっていた。
ただひたすらに、それを忠実に実行する毎日。最初は5日間だけの予定だった滞在は、気づけば3週間に延びていた。2週間を過ぎた頃には、すでに大量の家具や雑貨を仕入れていて、ホテルのロビーには僕が選び抜いたアイテムたちが、ぎっしりと積まれていた。
スタッフたちは連日総出で、丁寧に梱包作業をしてくれていた。最後の買い付けを終えてホテルに戻ったとき、ふと、我に返った。
チェックイン当初は20人ほどいた宿泊客たちが、もう誰もいない。
気づけば、広いホテルに残っていたのは僕ひとりだった。不思議なことに、この3週間で出会った全ての宿泊客たちと、僕は親しくなっていた。
毎晩一緒にご飯を食べ、語り合い、笑い合った。
その中には、今でも連絡を取り合っている人が8人もいる。対人恐怖症で、人と話すことさえ怖くなっていた僕が――
こうして心を通わせることができたなんて、奇跡としか思えなかった。
人と繋がることが、こんなにも温かく、尊いものだったと教えてもらった。「地獄のような日々を、あきらめずに生きてきて本当によかった」
そう思える日が来るなんて、ほんの少し前までは想像もできなかった。そして、いよいよ帰国の夜。
あれほど賑やかだったホテルの空間に、今は僕だけが残っていた。部屋で静かに荷物をまとめていると、胸の奥から込み上げる寂しさに、押しつぶされそうになった。
別れがこんなにも切なく感じるなんて。
けれど、ロビーへ向かうと、その思いは一変した。――スタッフ全員が、僕を見送るために並んでくれていたのだ。「足立さん、空港まで送ります」言葉にできなかった。
ただ、心の奥から込み上げるものを噛み締めるだけだった。空港に到着したとき、エミさんが僕にそっと手紙を差し出してくれた。
そして、ひとりひとりと言葉を交わし、最後に深く頭を下げた。
重たい足取りで、ひとりターミナルの中へ入っていった。荷物検査を終え、2階の窓から外を見ると――
そこにはまだ、スタッフ全員の姿があった。
僕は、思い切り手を振った。
そして、その瞬間、不意に涙があふれ出した。みんなが見えなくなるまで、何度も何度も振り返った。深夜1時発、名古屋行き。
飛行機の中は驚くほど静かで、乗客もわずかだった。僕はぼんやりと、バリでの出来事を思い返していた。
夢じゃないか?と、何度も問いかけた。
なにも計画せず、ただ“衝動”に突き動かされて買ったチケットが、こんな奇跡の連鎖を生むとは。やがて、機内で落ち着いた頃、エミさんからもらった手紙を開いた。「足立君、最初はどうなるかと心配したけど、何とかなったね。
足立君の行動力に感動して、私も毎日がとても楽しかったです。ありがとうね。お店、頑張ってね!」読み終えた瞬間、また熱いものがこみ上げた。この3週間で出会えた全ての人、全ての経験――
すべてが、自分の人生を肯定してくれるような、温かな贈り物だった。僕は、あんなにも憎んでいた過去の日々に、初めて「ありがとう」と思えた。パニック障害になっていなければ、この旅はなかった。
心を閉ざしていなければ、ここまで人の温かさに震えることもなかった。過去は変えられない。
でも、「今」をどう生きるかで、過去の意味は変えられる。
僕は、確かにそう実感した。そして静かに、眠りに落ちた。
帰りの機内の窓の向こうに、夜明けの気配が近づいていた。傷ついた過去を連れてきた僕に、 バリ島は、そっと「もう大丈夫だ」と教えてくれた。
僕の家具は、まだ海の向こうだった
2回断られた扉が、30秒で開いた理由
日本に帰ってくると、すぐに新しい店舗の準備に取り掛からなければならなかった。
けれど、バリ島で張り詰めていた緊張がほどけたのか、帰国後しばらくは体が動かなかった。三週間、毎日1時間しか寝ずに走り続けたツケが一気に噴き出したのかもしれない。ようやく体が動くようになったのは1週間後。僕は動き出した。店舗に必要な備品は何も揃っていなかった。
この場所に入れることが決まった2日後にはバリに飛び立っていたからだ。店舗作りを着々と進め、そろそろ、あのバリから送ったコンテナが名古屋港に到着する頃。
僕は、通関手続きをお願いできる業者を電話帳で片っ端から探して電話をかけ始めた。(※通関とは、海外から荷物を正式に日本へ入れるために、税関の検査・申告・許可を受ける手続きのこと)「バリ島でコンテナいっぱいに家具を買ってきたんですけど、通関をお願いできますか?」だが、返ってくるのはどこも同じ答えだった。「個人の方は受け付けていません」愛知県内の業者はすべてかけた。どこも、全滅だった。
そして、ついに港から連絡が入る。――コンテナが名古屋港に到着した。「え?ここまで来て、どんでん返し?」
信じられなかった。どうすればいい?不安がじわじわと体を締めつける。通関手続きをしなければ、あのバリ島で汗水流して買い付けた家具たちは、日本に入って来られない。海外から届いた荷物を検査・審査して、税関を通す――それが「通関」。
そんな当たり前のことすら、僕は何一つ知らなかった。さらに港からの電話は続く。「コンテナを置いたままだと、保管場所の料金が発生しますよ」完全に詰んだ。
「全部、自分が悪い……調べておかなかった、無知だった……どうしよう……」そのとき、ふと頭に浮かんだ名前があった。――イトウさん。まだパニック障害になる前、僕はひとりでニューヨークを旅したことがあった。
そのとき、現地のホテルを手配してくれたのが、僕が尊敬しているイトウさんだった。DONTというメンズショップを長年やってきた人で、雑誌やテレビにも出ているような人。
アメリカから洋服を仕入れていたから、きっと通関にも詳しいかもしれない。僕は急いでイトウさんの店に向かった。4年ぶりの店に入るなり、「お久しぶりです」の言葉も忘れ、勢いのままに伝えた。「イトウさん、バリ島でコンテナごと家具を買ってきたんだけど、どこに電話しても通関を断られちゃって……何か良い方法ないですか?」事情を聞いたイトウさんは、すぐに受話器を手に取り、
なんの迷いもなく、電話をかけ始めた。「よし、俺が電話してやる」かけた先は――伊勢湾海運だという。僕は思わず言ってしまった。「イトウさん……そこは2回電話して断られたとこです……」けれど、イトウさんはまったく気にしていない様子なのだ。「イトウだけど、課長おる?……おぉ、アサイさん。俺の弟みたいに可愛がっとる奴が、バリでコンテナ一杯家具買ってきたんだわ。通関してやってくれんか?……おう、じゃあ頼むわ」……終わった。電話は、わずか数十秒。僕はその場に立ち尽くした。ついさっきまで、何十件と断られ続けていたのに。「たった一声で、世界が動いた――」その瞬間、僕の中の何かが震えた。「大丈夫。やってくれるぞ」あまりにあっさりしたやり取りに、僕はただ驚いていた。なんなんだ、この人は。出会った頃からカッコいいとは思っていたけど、まさかここまでの人脈を持っていたとは――。そうか、これが“本物の大人”なんだ。誰かのために、躊躇なく動ける。言葉が通じる。物事が動く。僕はこの時、心の底から思った。「僕もこんな大人になりたい。困っている若い子たちの力になれるような、そんな存在になりたい」きっと、僕がこの先どんな人生を歩むとしても、
あのときのイトウさんの背中は、ずっと胸の中に残り続けるだろう。「カッコよさって、こういうことなんだ」僕が理想とする“大人”の像が、あの日、はっきりと形を持った。
海を越えた家具と、越えるべき自分
イトウさんの電話が繋いだ、もうひとつの出会い
イトウさんの店を出た僕は、言われた通り、すぐに電話をかけた。
すると電話口に出たのは、伊勢湾海運の課長・アサイさん。イトウさんの長年の知り合いだという。「イトウさんとはもう長い付き合いだからねぇ、大丈夫、安心して」その一言が、当時の僕にはどれほど心強かったか。
実際にお会いしたアサイさんは、物腰柔らかく、話をしっかりと聞いてくれる、頼れる大人だった。何も分からない僕に、アサイさんは輸入や通関の基礎を丁寧に教えてくれた。家具の輸入なんて初めてで、右も左も分からない僕にとって、それはまさに“海の向こうから届いた救いの手”のようだった。やがてアサイさんは、仕事で中国に5年ほど赴任することになる。
けれど日本に戻ったあとも、わざわざ僕の店に顔を出しに来てくれた。出会いを一度きりにしない、そんな人との関係性が、僕の人生を変えていく。通関の準備は、決して一筋縄ではいかなかった。
準備不足のままスタートしていた僕は、何度か港に呼び出され、そのたびにコンテナの中身について細かく尋ねられた。「この家具の素材は?」「これはどう使うの?」「数量は?」「現地での価格は?」一つひとつの質問に答えるたびに、通関書類が整っていく。
実はバリ島でお世話になったドイナさんも、書類の重要性について丁寧に教えてくれていたのに、当時の僕はその言葉の重みを理解していなかった。初めてのことだらけに頭が追いつかず、どこか他人事のように受け取ってしまっていたのだ。けれど、現場で向き合うしかない状況に追い込まれて、ようやく“輸入するということ”の現実を体感していった。分からないことは山ほどあったが、アサイさんのおかげで、僕の最初の通関はどうにか無事に終えることができた。
そしてついに、家具を店舗に搬入する日が決まった。──しかし。僕はまだ知らなかった。コンテナが無事に届いたその日が、新たな地獄の始まりになることを。
安堵する間もなく、次なる大きな問題が、僕の前に立ちはだかろうとしていた。
浅はかな僕と、支えてくれたみんな
倉庫もない家具屋に届いた、人生最大の荷物
買い付けた家具が、コンテナごと店に届く日が決まった瞬間だった。
「ん?待てよ。あの家具の量…全部、店に入るのか?」
その答えは、あっさり“NO”だった。入るはずもなかった。
僕は、自分の浅はかさに嫌気がさしていた。
「倉庫が必要だってことに、なんで気づかなかったんだ? 倉庫がないバリ家具屋?バカか、俺は…」でも、時間は待ってくれない。
翌朝には、コンテナが僕の店が入るテナントビルの搬入口に届く手筈だった。そこへやってきたのは、店を貸してくれた管理事務所のワタベさん。
「いよいよ来たねぇ〜手伝おうか?」
僕は正直に打ち明けた。「家具が来たのは良いんですけど…半分以上、店に入りません」ワタベさんは、笑って言った。
「じゃあさ、今ちょうど3階に空き店舗があるから、倉庫が見つかるまで使っていいよ」…またしても、救われた。
なんて運がいいんだ。いや、これはもう、人の縁に恵まれてるとしか思えなかった。搬入口に届いたコンテナの中身を降ろす作業を手伝ってくれたのは、ワタベさん、そして近所に住む幼馴染のアミちゃんとその友達のユウコちゃんだった。さらに、パニック障害を乗り越える過程で出会った新しい仲間たち6人も駆けつけてくれて、みんなで汗だくになりながら家具を運び込んだ。1階の店舗、そして仮の倉庫となった3階の空きスペースに、ようやくすべての家具が納まった。
僕は、店の壁に、この“店づくりを共にしてくれた人たち”の名前を全員分、書き込んだ。明日はいよいよ、「僕たちの店 ROBIN」がオープンする。
これは、僕だけの物語じゃない。支えてくれた、全員の物語だった。
独りだと思ってた。でも、独りじゃなかった
去ったはずの人たちから届いた、想いの花
オープン当日、朝から次々に花が届いた。もちろんパニック障害の時に去っていった友達たちは、僕が店をオープンする事すら知らないはずだった。それなのに、次々に届く花、花、花。気づけば20人以上の人から花が届けられ、店は花で一杯になったのだった。驚いた事に、去っていったと思っていた友達たちからも花が届いたのだ。「なんて俺は幸せな人間なんだ。みんな本当に、本当にありがとう」そう思って感動していると、最後の花が届いた。送り先住所は大阪だった。「ドイナさんからだ!」僕は心から嬉しかった。バリ島だけで終わりではない、これからもドイナさんとの関係は続くんだ。「ほな、日本でな」と言っていた。社交辞令じゃなかったんだ!僕は、何よりもパワーをもらって新しい気持ちで店をオープンする事ができたのだった。この店の名はROBIN。この店の名前を付けてくれたのは、この店のキッカケをくれたオクヤさんだ。僕がこの場所に店を出すと決まったあの日、「オクヤさん、何か良い店の名前考えてくれない?」と、頼んだのだった。するとすぐにオクヤさんが考えてくれたのが、ROBINという店名だった。「ROBINってどう?意味もあるんですよ」僕はすぐに気に入った。「凄く良い!何ですか?意味って、どんな意味があるんですか?」と、訪ねるとこう言った。「足立君は昔から、バットマン&ロビンって映画に出てくるロビンみたいな感じがするんです。向こう見ずな感じがするんだけど、必ず周りの誰かが助けてくれるって所もピッタリでしょ?」そう言って名付けられたROBINという名前は、
僕がこれから歩く道を、まるであらかじめ見通していたかのようだった。実際、店名が決まったのは、バリ島に家具を買い付ける前のことだった。
けれど、僕のその後の道のりは、まさにROBINという名が示す通りになっていった。
何から何まで、みんなが力を貸してくれた。友達が去り、自分の力だけで家具屋を始めようとしていた僕は、
気づけば、たくさんの人たちに助けられていた。
独りでは、何ひとつできなかったはずなのに──。僕は、孤独で独りぽっちだとばかり思っていたが、実際はそうではなかったのだった。
孤独は、幻想だった
“ありがとう”のために、すべてがあった
ROBINの最初のお客さんのことは、今でも忘れられない。
30代の若い夫婦で、新築の一軒家に似合う大きなアジアンソファを探していた。旦那さんが仕事中にたまたま聞いていたラジオで、ROBINのオープンを知ってくれたという。サーファーの旦那さんも、奥さんも、とても気さくで、話してすぐに打ち解けた。家具の納品には、僕自身が立ち会った。設置が終わると、旦那さんが深くお辞儀してこう言ってくれた。「足立さんに家具をお願いして本当によかった。心から気に入ってます。ありがとうございました」その帰り道、車のハンドルを握ったまま、僕はこらえきれず泣いた。どうしてこんなにも涙が溢れるのか、自分でもわからなかった。
辛かった3年半が一気に蘇った。「ありがとう」という言葉が、ここまで胸に響く日が来るなんて――。今までの苦しみが、すべてこの瞬間のためにあったんじゃないかとすら思えた。
「この仕事を選んで、本当に良かった」
そう思えた瞬間だった。ROBINがオープンして少し落ち着いた頃、僕は倉庫を探し始めた。店には入りきらない家具を置くために、どうしても広い倉庫が必要だった。アルバイトも入り、仕事のリズムができてきた頃だった。2週間ほどかけて、あちこちの不動産会社を回った。でも、条件に合う場所はまったく見つからなかった。「運もここまでか」と思いながら、久々に昔馴染みのサーフショップに立ち寄った。「おう、ひろし!久しぶりやな。店はどうや?」そう声をかけてくれたのは、サーフボードのシェイパーをしているノリさんだった。「店はなんとか。でも、いま倉庫探してるんですよ」そう言うと、ノリさんがサーフショップの目の前にある倉庫を指差して言った。「ここ、聞いてやろか?」その場でノリさんは電話をかけてくれた。そして数分後、「貸してくれるってさ」。
あれほど探しても見つからなかった倉庫が、目の前に突然現れた。
しかも――
・希望していたサイズより広い
・家賃は予算の3分の1
・トレーラーが直接乗り入れ可能な敷地
・フォークリフト貸出OK
・自宅から車で5分
・ROBINまでの通り道
・しかも、二十歳の頃から通っていたサーフショップのすぐ前
すべての条件が揃っていた。「……なんで、こんなに上手くいくんだろう?」
正直、少し怖くなるほどだった。でも、その“理由”がわかるのは、もう少し後のことだった。あの倉庫を見つけた日、僕はまたしても「誰かに助けられた」。そしてまた一歩、「人生が自分を導いている」そんな感覚が強くなっていったのだった。
営業なんて知らない。でも、やってみた
結果はゼロ。それでも、僕は届けた
僕はその後、ついに初めての営業に踏み出した。だけど、営業なんてまるで未経験。どこへ行けばいいのか、何から始めればいいのか、営業に必要なマナーや段取りなんて一切知らなかった。全部が手探りで、「これで良いのかな?」と不安だらけだった。でも、新しいことって、だいたいそんなもんだ。不安を抱えていても、逃げずに動くしかない。正解は分からなくても、自分で決めて進む。それが僕にとって“今後の人生そのもの”でもあった。どうせやるなら、とにかく大胆にいこう。そう決めた僕は、無謀にも、いきなり有名なデパートばかりを訪ねることにした。今思えば、世間知らずだったからこそ、そんな無茶なことができたんだろう。「アポ」という言葉すら知らなかった僕は、恥ずかしげもなく直接、各デパートの総合案内に突撃した。「バリ島の家具屋をしてるんですけど、催事とかを担当してる人に会いたいんですが」我ながらズレた聞き方だったと思う。それでも受付の女性たちは戸惑いながらも、「少々お待ちください」と、意外にも取り次いでくれることが多かった。ある日、名古屋駅のジェイアール名古屋タカシマヤでも同じように総合案内で声をかけた。すると、受付の奥からヒソヒソとした声が聞こえてきた。「どうしよう、こういうの誰に回せばいいの?」しばらくして戻ってきたスタッフが言った。「申し訳ございません、催事担当は今から会議に入るところでして…お引き取りいただけますでしょうか?」僕は即座に食い下がった。「会議前に、これだけでも渡させてもらえませんか?一瞬で済みます」それでも断られそうになったので、今度は少し意地になって言った。「渡すだけです。無理なら終わるまでここで待ちますと、そう伝えてください」すると、根負けしたのか、催事担当の方が現れてくれた。ただ、彼が口にしたのはこうだった。「アジア関係の催事は、今後もやらない方針です」それでも僕は笑って頭を下げた。「それは全然構いません。この資料だけ受け取ってもらえれば、それで十分です。ありがとうございました」目的は果たした。営業としての成果はゼロだったかもしれない。でも、自分で行動して、足を動かして、ちゃんと届けた。その事実が僕にとっては、大きな一歩だった。
正解がわからなくても、あなたが踏み出した“最初の一歩”は、何でしたか?
一脚のソファーが、運命を変えた
「一年前に断られたタカシマヤ」からのオファー
ちょうどROBINをオープンしてから、1年が経った頃のことだった。世の中では、まだ静かだったが、どこか水面下でアジアン家具ブームの兆しが見え始めていた。
そんなある日、思いもよらない訪問者が現れた。――JR名古屋高島屋の催事担当者だった。「ROBINさんの家具をメインにして、全国のアジアン家具店を集めた“アジアンフェスタ”という催事をやりたいんです」僕は、耳を疑った。
どうしてROBINが? うちのような無名の店が、どうして“メイン”に選ばれたのか?
驚きと同時に、込み上げてくる何かを感じながら、思わずその理由を尋ねた。すると担当の女性は、少し笑みを浮かべて、こう言った。「実は以前、こっそりお店に伺ったことがあるんです。あのソファー……バリ島で探してきたという一点モノを見て、直感で思ったんです。“これは、この催事の象徴になる”って」――あのソファー。僕がバリ島の炎天下の中を何日も歩き回り、汗だくで、靴が擦り切れるほど探して、ようやく見つけた、あの一台。まさか、あの一台が、こんな展開を呼び込む“きっかけ”になっていたなんて。
言葉にならなかった。驚きと、何とも言えない感謝の気持ちが、胸の奥からじんわりと込み上げてきた。彼女が広げた催事会場の図面には、20以上の出展区画が描かれていた。
その中で、彼女が静かに指差したのは、会場の中心──誰が見ても、一番目立つセンターの場所だった。「この場所をROBINさんにお願いしたいんです。最初に声をかけると決めていたので」その瞬間、頭に浮かんだのは、あの日のことだった。
営業に慣れていなかった僕が、思い切って飛び込んだ名古屋高島屋。
「アジア関係の催事は今後やらないと思いますよ」と言われて、引き下がった、あの場所。あの時に対応してくれた担当者も、会場に居た。
少し気まずそうに、でもちゃんとこちらを見ていた。
それも無理はない。
まさか1年後に、こんな形でアジアン家具ブームが訪れるなんて、誰にも予測できなかったはずだ。
そして、迎えた「アジアンフェスタ」。全国から名のある20以上のアジアン家具店が一堂に会する、記念すべき“初開催”の大規模催事。
その中でROBINは――
なんと、初めての開催にもかかわらず、売上第1位を記録したのだった。信じられない。けれど、現実だった。その成功はたちまち話題となり、「アジアンフェスタ」はその後も3年間、毎年続いていく。
そしてそのすべての開催で、ROBINには必ず声がかかった。催事を通じて、全国のアジアン家具店のオーナーやスタッフたちとも出会い、繋がり、
ただの競争相手ではなく、互いに刺激を与え、支え合う“仲間”になっていった。時が流れても――「タカシマヤの催事でROBINを知って、ずっと来たかったんです」
そう言って、遠方からわざわざ訪れてくれるお客さんが、後を絶たなかった。あのソファーと。
あの日の営業と。
あの女性との、偶然の出会いと。すべてが、今へと繋がっていた。僕が「何もなかった」と思っていた日々にこそ、ちゃんと意味があったんだ。
今になって、そう思えるようになった。
ROBINは10年で閉店した。でも今、僕は“ROBIN”として生きている
ROBINというバリ島家具の店は、10年という節目で、その役割を終えることになった。もちろん、簡単に決断できたわけじゃなかった。
なぜ続けなかったのかと聞かれれば、それは一言では語りきれない。だけど、あえて言うならば、それもまた「時代の流れ」だったのかもしれない。
世の中のアジアン家具ブームは次第に落ち着き、あの頃のような熱気は、いつの間にか静かに遠のいていった。でも、実はそれ以上に、僕自身がまたしても“人生のどん底”を経験していた。
あのROBINを閉じることは、僕にとって大きな喪失だった。
手塩にかけて育てた店を手放すというのは、やはりどこか、心の一部を引き裂くような痛みがあった。ただ、この話の続きはまた、別の章で詳しく語ろうと思う。
なぜならあの閉店の裏側にも、人との出会いや、自分との再対話がたくさん詰まっていたからだ。「ROBIN」という名には、“勇気を持って踏み出す者”という意味を込めていた。
それは、たくさんの人に助けられてきた僕が、今度は“誰かを助ける側”へとまわるという決意でもある。そう思えば、ROBINの経験も、CANDy BLOODでの挑戦も、すべては一本の線で繋がっている。僕の作品には、いくつもの色が重なり合っている。それは、悲しみと喜び、迷いと決意、絶望と再起が入り混じった、ひとつの“モザイクのような人生”。そんな想いを、今はレザーという素材に込めて、表現している。——人生は、ひとつの色じゃ表現できない。たくさんの欠片と、いろんな色が重なって、ようやく“本当の形”が見えてくる。だからこそ僕は、これからも“色を探す旅”を続けていく。
そしていつか、誰かが自分の色を見失いそうなとき、
そっと背中を押せる存在でありたいと思っている。
そして今、僕は“誰かを勇気づける”という、まったく新しい形の事をしている。
その道の先に、まだ見ぬ誰かの“人生の転機”があるかもしれないと思いながら。ROBINという名前は、これからも、“勇気の象徴”として僕の人生を導いていく。このストーリーは、家具の輸入の話じゃない。
絶望していた僕が、“人との繋がり”に救われて、もう一度人生を歩き直した話だ。最初は「孤独」だった。
でも、気づけば、たくさんの人が助けてくれた。そんな奇跡の連なりが、今の僕をつくっている。もしこの物語が、どこかであなたの心に火を灯したなら——
その光はきっと、あなたの“これから”を照らしてくれるはずだから。
▶︎ 僕の今の活動はこちらから
▶︎ CANDy BLOOD – アートで感情を再起動する
▶︎ [未来の子どもたちへ届ける“あるプロジェクト”も始まっています]